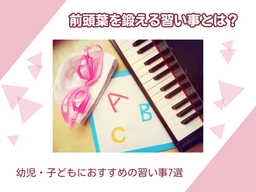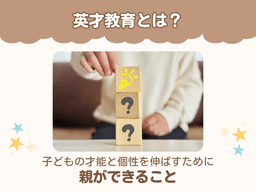なぜ幼児期の習い事が意味ないと感じるのか?

子どもの習い事について、続けるべきかどうか悩む場面は誰にでも訪れるものです。
月謝を払い、時間をかけて通わせているのに「意味がないのでは」と感じてしまう背景にはいくつかの共通する理由があります。
ここでは、習い事が「意味ない」と感じてしまう理由を深掘りし、納得のいく習い事選びや関わり方のヒントをお届けします。
目的が曖昧なまま始めている
「周りがやっているから」「なんとなく良さそうだから」といった曖昧な理由で習い事を始めてしまうケースは少なくありません。
しかし、目的がはっきりしないままでは続けていくうちに「何のために通っているのか」が分からなくなり、意味を見失いやすくなります。
たとえばスイミングを始めた場合でも、「泳げるようになればいい」のか「大会を目指したい」のかが不明確だと、子どもの成長や上達を実感しにくくなってしまいます。
習い事は、明確な目的を持って始めることが大切です。
子どもの関心がない
親の意向で始めた習い事でも、子ども自身が関心を持っていなければなかなか身につきません。
「好き」「楽しい」と思える気持ちがないとやる気が続きにくくなり、自然と関心が薄れてしまうこともあります。
特に未就学児の場合、親が習い事を選ぶことも多くなりますが、体験レッスンなどを通して子どもの反応をしっかり観察することが大切です。
子どもの興味関心に合わせた習い事を選び、「やってみたい」という気持ちを引き出す関わり方が効果的です。
成果が見えず上達を実感できない
習い事を続けていても、成果が見えにくいと「意味がないのでは」と感じてしまいがちです。
たとえばピアノがなかなか弾けない、英語を習っていても話せるようにならないなど、結果が出ないと親も子も不安になります。
ただし、何事も上達には時間がかかるものです。
短期間で成果を求めすぎず、子どものペースに合わせて見守る姿勢が大切です。
少しずつでもできることが増えていることに目を向けて、褒めてあげましょう。
先生や環境との相性が悪い
習い事の充実度は、指導する先生や教室の雰囲気にも大きく左右されます。
先生が厳しすぎる、話しかけづらい、教室の雰囲気が合わないなどという場合、子どもは習い事を楽しめず行きたくなくなってしまうこともあります。
また通う時間帯や立地など、環境的な要素も意外と大きな影響を与えます。
無理なく通えること、子どもが安心して過ごせることは長く続けるうえでとても重要なポイントです。
習い事の経験を意味あるものにするには、親御さんの関わり方が重要なんだって知ってた?

「子どもの習い事が意味ない?辞めようかな?」と感じた事例

習い事に通わせている中で、「これって意味があるのかな?」「続けるべきか迷う…」と感じることはどのご家庭にも起こり得ることです。
その理由は、上達のペースだけでなく子どもとの相性やご家庭の状況など、さまざまな要因が重なって生まれるものです。
ここでは、実際にあったいくつかのケースをもとに、習い事との向き合い方や見直しのタイミングについて考えてみましょう。
幼児教室:プリント中心で子どもが楽しめなかった
ある幼児教室に通った家庭では、「知育」を目的に始めたものの、授業がプリント学習中心だったため子どもが楽しめず、通うこと自体が負担になってしまったという声がありました。
幼児期はまだ文字や数字への興味が育ちきっていない時期。座って学ぶスタイルばかりでは集中が続かず、「勉強させられている」と感じてしまうこともあります。
もちろんそういった教室にも良さはありますが、ベビーパークでは「遊びの中で学ぶ」体験型レッスンを大切にしています。
子どもの発達段階に合わせて、親子で一緒に楽しめる内容が組まれており、「学ぶって楽しい」という気持ちが自然と育っていくのが特徴です。
「学ぶって楽しい」と思える環境に出会えると、子どもは自然と意欲を育んでいきます。
そのためにも、教室選びはじっくり見極める必要があります。
ピアノ:家での練習が続かず親子でストレスになった
ピアノは人気の習い事ですが、「毎日の練習が必要」という点で親子ともに負担に感じることもあるようです。
特に子どもが乗り気でない場合、練習を促すたびに親子で衝突してしまい、せっかく始めた習い事が好きでなくなってしまうこともあります。
練習の頻度や方法も、子どものペースに合わせて柔軟に考えることが大切です。
英会話:習っても話せるようになった実感が持てなかった
英会話は将来の役に立つと人気の習い事ですが、「本当に身についているのかな?」「通っていてもなかなか話せるようになっていない気がする」と感じることもあるようです。
ただし英語は積み重ねが大切な分野で、目に見える成果が出るまでには時間がかかるもの。
まずはお子さま自身が「英語にふれるのが楽しい」と感じているかどうかが大きなポイントです。
おうちでも英語の絵本やアニメを取り入れるなど、教室以外の環境づくりを工夫することで、少しずつ理解や興味が深まっていきます。
スイミング:子どもが嫌がって通うことが苦痛になった
スイミングは体力向上のために人気の習い事ですが、水が怖かったり、寒さを感じたりして苦手意識を持つ子どももいます。
そうなると、毎週通うのが苦痛となり親も気疲れしてしまいます。
そんなときは、いったんお休みする、あるいはおうちで水遊びから慣れていくなど、子どもの気持ちに寄り添ったステップが有効です。
無理なく楽しい気持ちで取り組めるタイミングを見つけられれば、また前向きに挑戦できる日がやってくるかもしれません。
実際、どのようにお子さんの習い事と関わって行けばよいのかを見ていきましょう♪

幼児期の習い事を意味ある経験にする関わり方

子どもの習い事が「意味がある」と感じられるかどうかは、子ども自身の取り組みだけでなく親の関わり方によっても大きく変わります。
ただ通わせるだけではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら一緒に取り組むことでその時間がより充実したものになります。
ここでは、子どもの習い事を前向きで実りある経験にしていくために、親として意識しておきたい関わり方のポイントをご紹介します。
子どもの意欲を尊重する
いちばん大切なのは、子ども自身が「やってみたい」と思っているかどうかを見極めることです。
親の期待や「みんなやっているから」という理由だけで始めると、子どもの気持ちがついてこないこともあります。
自分で興味をもった習い事には自然と集中力が高まり、上達もしやすくなります。
「楽しそう」「もっとやってみたい」そんな気持ちが、学びの原動力になります。
習い事を選ぶときは、子どもの反応をよく観察しながら一緒に選ぶ気持ちで向き合ってみましょう。
子どもの成長に気づき、本人にも言葉で伝える
習い事の成果は、すぐに目に見えるものばかりではありません。
だからこそ、小さな変化や頑張りを見つけて積極的に声をかけてあげることが大切です。
たとえば、「前より大きな声でご挨拶できたね」「今日は集中して取り組めたね」といった具体的な言葉が、子どもの自信になります。
親に認められることで「また頑張ってみよう」と思えるようになり、前向きな気持ちで取り組めるようになります。
親の声がけが、子どものやる気や自己肯定感を育てる大切なサポートになります。
無理に続けない柔軟さを持つ
「せっかく始めたから、できるだけ続けさせたい」という気持ちは自然なことですが、子どもが明らかに嫌がっていたりストレスを感じているようなら、いったん立ち止まって様子を見てみましょう。
無理に続けさせることで、習い事そのものが嫌な思い出になってしまうこともあります。
気持ちが向かないときは、「お休みする」「いったん離れてみる」といった選択も、子どもにとっては前向きな一歩になることがあります。
子どもが何故習い事を嫌がっているのか、子どもの気持ちを聞いてみるようにしましょう。
時間が合わないのか、先生や他の生徒と相性が合わないのか、内容が簡単すぎる・難しすぎるのか、興味のない内容なのかなど、嫌がる理由は様々です。
子どもが興味を持てることに出会えれば、無理なく楽しく学びに向かえるようになるでしょう。
習い事が意味ないと思わない3つの工夫
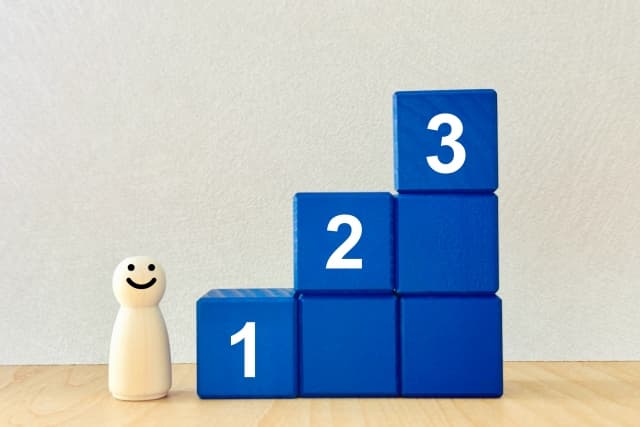
せっかく始めた習い事だからこそ、「やってよかったね」と感じられる経験にしたいものです。
そのためには、始める前の選び方はもちろん、通いはじめてからの関わり方にもちょっとした工夫が大切になります。
ここでは、子どもの興味や成長を大切にしながら、習い事の時間をより豊かにするための3つの工夫をご紹介します。
興味や発達に合った内容を選ぶ
まず大切にしたいのは、お子さまの年齢や発達段階、そして「やってみたい」という気持ちに合った習い事を選ぶことです。
たとえば、まだ集中力が長く続かない年齢で座ってプリントに取り組む内容を選んでも、うまく楽しめないことがあります。
子どもの興味の芽を見つけるには、ふだんどんな遊びに夢中になっているか、どんな話をよくするかといった日常の様子を観察するのがおすすめです。
また、習い事の体験レッスンは実際の反応を見る絶好の機会です。無理なく自然体で取り組める内容を選びましょう。
先生との相性を事前に確認する
習い事を楽しく続けていくためには、先生との相性も大切なポイントです。
教え方が合っていたり、子どもが先生と安心してやりとりできるかどうかで、習い事への意欲も大きく変わってきます。
体験や見学の際には、先生がどんなふうに子どもに声をかけているか、子どもがリラックスして笑顔を見せているかなどを、さりげなく観察してみましょう。
親とのやり取りがしやすく、相談しやすい先生かどうかも安心して通える教室選びのポイントです。
目的と成果を家庭で共有する
習い事を続けるうえで、「どんな経験をしてほしいか」「どんな力を育てたいか」といった目的を、家庭の中で意識しておくことはとても大切です。
年齢によっては、子ども自身が目的を理解するのは難しいかもしれませんが、親が思いをもって関わることで日々の取り組みがより意味のあるものになります。
たとえば、「音やリズムを楽しんでほしい」「少しずつ人との関わりに慣れてほしい」といった気持ちがあれば、子どもの変化や成長に自然と気づきやすくなります。
「今日はたくさん身体を動かしてたね」「前より楽しく参加できたね」といった声かけを通して、子ども自身も安心感や達成感を感じていくことでしょう。
合わせて読みたい
まとめ
この記事では、習い事を意味ある経験にするために、親ができる関わり方や選び方の工夫をご紹介してきました。大切なのは、子どもの興味や発達に合った内容を選び、気持ちに寄り添いながら見守っていくことです。小さな頑張りに気づき、ことばにして伝えることで習い事の時間がぐっと前向きなものになります。
ベビーパークでは、こうした親としての関わり方や声かけの工夫も学ぶことができます。これから習い事を考えている方も、すでに始めている方も、親子で心地よく続けられる環境と出会えることを願っています。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #習い事 #意味ない #効果 #続ける #方法
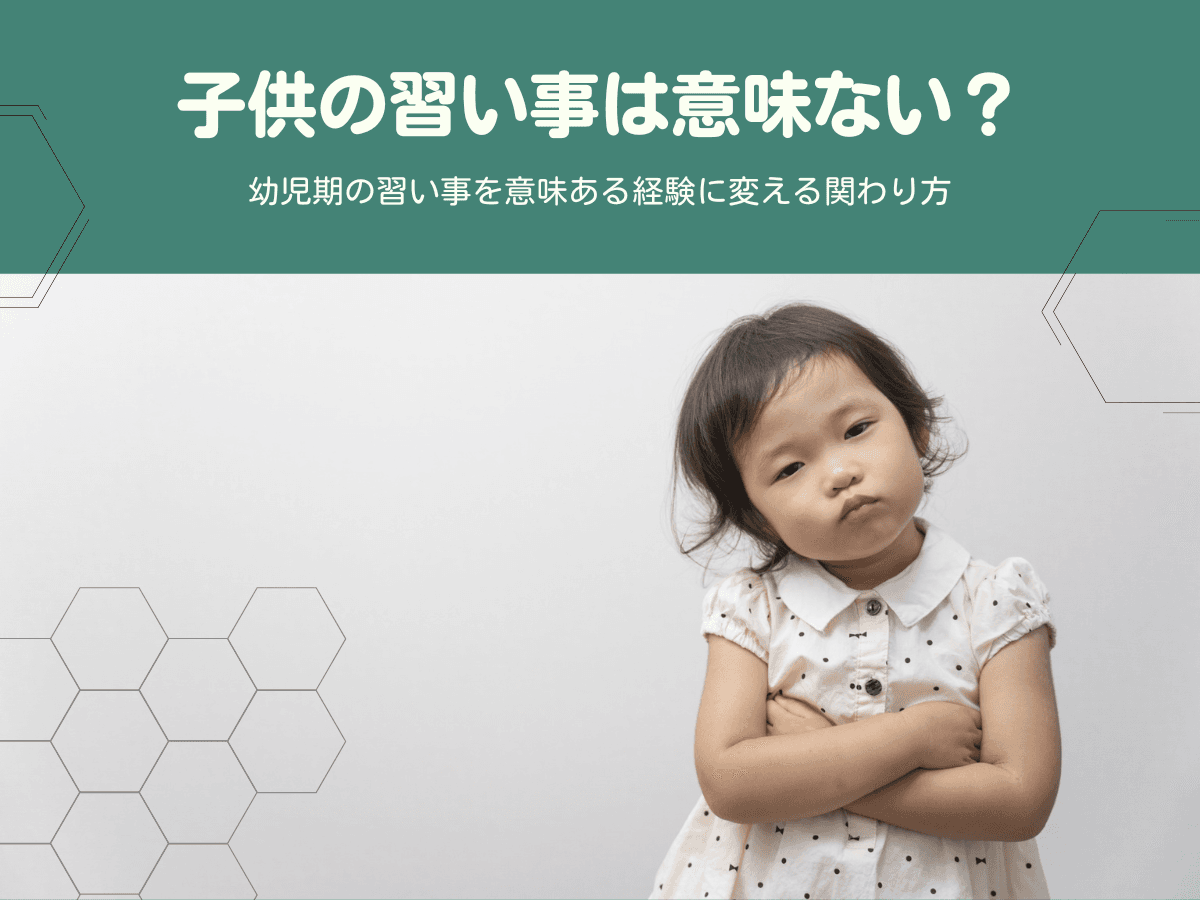
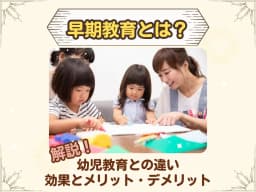
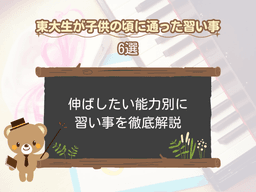
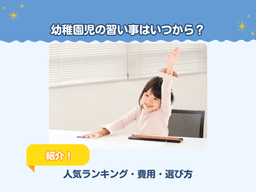
.png&w=256&q=75)
.png&w=256&q=75)