- 幼児教室のベビーパーク ホーム
- 育児がもっとたのしくなるコラム
育児がもっとたのしくなるコラム
ベビーパークの子育てが楽しくなる育児コラム一覧です。子育て中のママが知りたい事やお悩みへのヒントをたくさん掲載しました!
タグから探す
オススメ記事
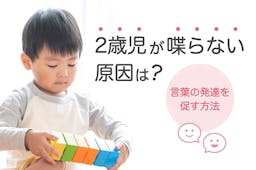
1歳~3歳の育児
2歳児が喋らない原因は?赤ちゃんの言葉の発達を促すには?
2歳になると、自分であちこち歩き回ったり、食事や着替え、トイレなどをある程度自分で行ったりと、生活面で大きな成長が見られるようになります。同時に、言語力や語彙力も伸びてくる時期ですが、子どもによっては「単語しか出ない」「ほとんどしゃべらない」など、言葉の発達に遅れが見られるケースもあります。まわりの子に比べて言葉の発達が遅れていると、「成長に問題があるのでは…」「身体機能に異常があるのかも?」と不安になってしまいがちです。そこで今回は、2歳児の言葉の発達が遅れる原因や、言葉の発育を促す方法について解説します。
.jpg&w=256&q=75)
1歳~3歳の育児
1歳半の言葉の発達はどのくらい?親ができることはある?
子どもが1歳になり、ひとり歩きはできるようになったけど、今度は「言葉が少ない」と親の悩みは尽きないもの。1歳児は発達のスピードも早く、早い子なら2~3語の言葉を話す時期です。しかし、言葉の発達は個人差も大きく、おしゃべりできないからといって問題があるとは限りません。今回は、1歳や1歳半の子の言葉の発達と、言葉が出ない子に親ができることを解説します。言葉の発達に不安を持っている人はぜひ参考にしてみてください。
.jpg&w=256&q=75)
1歳~3歳の育児
2歳児はいつから話す?2歳半の言葉理解の目安
一般的に、2歳ぐらいから言葉を話すといわれています。ただし男の子と女の子とでは異なり、周囲の大人たちとのコミュニケーションや、おかれた環境によって話す時期が異なってきます。いったい、言葉の発達の目安はどれくらいなのでしょうか。また2歳児になると、さまざまな事に興味関心がわいてきます。ここでは、単純に言葉を話す時期の早さ・遅さだけを見るのではなく、話し方や発音の特徴、言葉を楽しく練習するトレーニング方法などを解説していきます。
新着記事

1歳~3歳の育児
おしゃぶりは平均いつまで使う?使い続けるリスクとやめるための8ステップ
子どもが安心して眠るために使用しているおしゃぶりですが、いつまで使うべきか、また使い続けることでどのようなリスクがあるのか、悩んでいる親御さんは多いでしょう。この記事では、おしゃぶりを使用する月齢の平均と目安、使用し続けることによるリスクについて詳しく解説します。そして、おしゃぶりをやめさせるための8つのステップも紹介します。この記事を通じて、おしゃぶりの使用についての不安や疑問を解消し、おしゃぶりをやめさせるための知識と方法を得ることができます。お子さんの健康と成長をサポートし、安心しておしゃぶりを卒業できるよう、ぜひ参考にしてください。

赤ちゃんの育児
哺乳瓶消毒はいつまでやるべき?殺菌のコツや消毒卒業のタイミングを解説!
哺乳瓶の消毒は、赤ちゃんの健康を守るために欠かせない日常的なケアですが、いつまで続けるべきなのでしょうか?この記事では、哺乳瓶の消毒が必要な理由から、効果的な消毒方法、さらには消毒をやめる適切なタイミングについても詳しく解説します。衛生管理を正しく行うための方法と、安心して育児を楽しむための知識を身につけましょう。

赤ちゃんの育児
赤ちゃんの洗濯物はいつまで別にする?正しい洗濯方法と洗剤・柔軟剤の使い方
赤ちゃんの衣類の洗い方について、普段通りの洗濯方法でいいのか迷ったことはありませんか?赤ちゃんの肌はとてもデリケートで、少しの刺激でもトラブルが起きやすいもの。そのため、赤ちゃんの衣類の洗濯方法には注意すべきポイントがあります。この記事では、赤ちゃんの洗濯物を他の家族の洗濯物と一緒に洗うべきか、別にするべきかについての疑問に答えます。また、洗剤や柔軟剤の選び方、赤ちゃん特有の汚れの落とし方、そして肌トラブルを防ぐための洗濯のコツについても詳しく解説します。正しい知識を身に付けて、大切な赤ちゃんの肌を守りましょう。

その他
自閉症の赤ちゃんの特徴とは?早期発見のための視線の動きと育児のヒント
自閉症の赤ちゃんを育てている、もしくはその可能性を感じている親や育児関係者にとって、早期発見と適切なサポートはとても大切です。自閉症は早期に発見することで、必要な支援や療育を受ける機会が増え、その子どもの発達を最大限にサポートすることができます。この記事では、自閉症の赤ちゃんに見られる特徴や早期発見のためのポイント、療育や具体的なサポートの方法についても解説します。ぜひ最後まで読んでその子にとって最適な育児方法を見つけてください。

赤ちゃんの育児
赤ちゃんの寝返りはいつ頃から?兆候や注意点・親ができるサポート法も解説
赤ちゃんが初めて寝返りをする瞬間は、親にとってとても感動的な出来事です。寝返りは赤ちゃんの成長の大切なステップであり、その時期や兆候、注意点をよく知ることが大切です。この記事では、赤ちゃんが寝返りを始める一般的な時期や、寝返りをする前のサインについて詳しく説明します。また、寝返りを助けるための具体的な方法や、寝返りを始めたときに親が気をつけるべきポイントについても紹介します。赤ちゃんの成長をサポートするための情報を知り、安心して育児を楽しみましょう!

赤ちゃんの育児
ベビーマッサージで発達をサポートしよう!効果や時期・やり方や注意点を解説
ベビーマッサージという言葉、聞いたことがありますか?ベビーマッサージは、親子の深い絆を育むだけでなく、赤ちゃんの健康と発達に良いとされています。この記事では、ベビーマッサージの具体的な効果や最適なタイミング、基本的なやり方、そして注意点について詳しく解説します。初心者の方でも安心して始められる内容ですので、ベビーマッサージに興味がある方や具体的な方法を知りたい方は、ぜひご覧ください。

1歳~3歳の育児
赤ちゃんのうつ伏せ寝は危険?SIDSとの関係や安全対策を解説
赤ちゃんの眠る姿は可愛いものですが、うつ伏せで寝ていて心配になったことはありませんか?この記事ではうつ伏せ寝が赤ちゃんにとってどのような影響を与えるのか、リスクはあるのかについて詳しく解説します。また、SIDS(乳幼児突然死症候群)との関係や、赤ちゃんが安全にうつ伏せ寝をするためのポイントについても触れていきます。赤ちゃんの健康と安全を守るために正しい知識を身につけましょう。

1歳~3歳の育児
歯固めはいつからいつまで使う?歯並びへの影響やおしゃぶりとの違い・選び方も解説
赤ちゃんの成長に伴い、小さな歯が生えてくるのは多くの親にとって喜ばしい瞬間です。しかし、赤ちゃんの歯に関するアイテムの一つ「歯固め」は、いつから何のために使うのか疑問に思ったことはありませんか?この記事では、歯固めの基本的な役割から効果、安全な使い方までを詳しく解説します。歯固めに関する疑問を解消し、赤ちゃんのお口の健康を守るためぜひ最後までご覧ください。

赤ちゃんの育児
赤ちゃんの理想的な睡眠時間は何時間?寝不足のサインや上手な寝かしつけ方法も解説
赤ちゃんの成長と健康に、十分な睡眠は欠かせません。しかし、「赤ちゃんの理想的な睡眠時間は何時間なのか?」、「どのような睡眠リズムを作るのが良いのか?」といった疑問を抱えている親御さんも多いでしょう。この記事では、月齢別の睡眠時間の目安や理想的な睡眠リズムの作り方、赤ちゃんの寝不足のサイン、そして上手な寝かしつけ方法について詳しく解説します。赤ちゃんの健やかな成長に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

赤ちゃんの育児
赤ちゃんの寝返り返りはいつから始まる?練習のポイントや安全対策を解説
赤ちゃんの成長は驚くべきもので、毎日新しい発見があります。その中でも寝返りができるようになることは、多くの親が待ち望む大きな一歩です。しかし寝返りが出来て嬉しい反面、寝返りしたうつぶせ状態から元の状態に戻る「寝返り返り」はいつからできるようになるの?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、寝返り返りの一般的な時期やその兆候、練習のポイント、安全な環境作りのコツなどを詳しく解説します。ぜひこれを読んで、赤ちゃんの成長のサポートに役立ててください。








