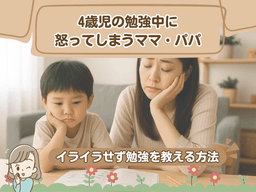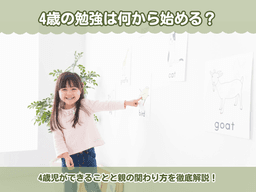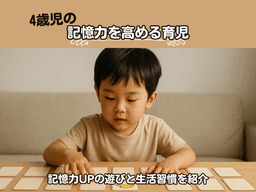5歳児の勉強でイライラしてしまう時はいつ?

年長児を育てていると、「全然勉強してくれない」「言っても聞かない」といった場面に直面することも多いのではないでしょうか。
こちらの声かけが響かない、つい他の子と比べてしまう、注意したのに反発されてしまう…
そんな日常の一コマが積み重なると、どうしてもイライラが募ってしまうものです。
ここでは、どんな瞬間に親のストレスが高まりやすいのかを振り返りながら、その背景にある子どもの姿を見つめ直してみましょう。
何度言っても勉強しないことでストレスがたまる
「また言わせるの?」「何回言ったらやるの?」そんな言葉をつい口にしてしまうことはありませんか?
5歳の子どもは、気持ちを切り替えてすぐに行動に移すことがまだ難しく、指示されたことをすぐに実行できるとは限りません。
今は、自分なりに理解し、少しずつ行動へつなげる力を育てている途中です。
特に年長になると、自立心が芽生えてくる一方で、集中力や注意力の波が大きくなりやすい時期でもあります。
親としては「伝わっていない」と感じてしまうかもしれませんが、子ども自身も「また怒られた」と思って自信を失うこともあるのです。
だからこそ、回数を重ねて指示するよりも、声かけのタイミングや伝え方を見直すことが、親子ともにストレスを減らす鍵になります。
他の子どもと比べてしまい焦りを感じる
「〇〇ちゃんはもうひらがなを全部書けるのに」「近所の子は計算が得意らしい」など、他の子の成長と比較してしまうことは多くの保護者に共通する悩みです。
こうした比較は親自身の焦りにつながりやすく、結果として子どもへの期待が過剰になりがちです。
しかし、子どもの発達には個人差があり、どうなるかわからない未来を心配しすぎても仕方ありません。
「今のわが子」にしっかり目を向けて接することで、焦りや不安は軽減されます。
遊んでばかりで学習習慣が身につかない
勉強の声かけをしても子どもが一向に机に向かおうとせず、朝から晩までおもちゃやテレビ、ゲームに夢中な様子を見ていると、「いつになったら勉強を始めるの?」「遊んでばかりで大丈夫?」とイライラした気持ちになってしまうこともあります。
ですが、5歳児にとっての遊びは、ただの暇つぶしではなく、将来の学びにつながる大切な経験でもあります。
特にごっこ遊びや積み木遊びなどは、集中力・思考力・空間認識力を自然に育んでくれます。
勉強を無理にやらせるよりも、遊びの中に学びのきっかけを取り入れる工夫が、親のストレスも和らげ、子どものやる気も引き出してくれます。
注意すると反発されてさらにイライラする
よかれと思って声をかけたのに、「今やろうとしてたのに!」「うるさい!」といった子どもの反応に、思わず感情的になってしまうこともあるでしょう。
これは、5歳という年齢が“自己主張”の強くなる時期だからこそ起こる現象です。
年長になると、子どもは「自分の意志」を明確に持ち始めるため、命令口調や強制的な言い方には敏感に反応します。
反発されるたびにイライラしてしまうのではなく、「共感」と「選択肢」を与えることが効果的です。
たとえば「どっちのプリントを先にやりたい?」と声をかけるだけで、子どもの態度は変わるかもしれません。
子どものことを思う気持ちが強いあまり、イライラしてしまうのかも!

5歳児が勉強しない・嫌がる理由とは?
子どもが勉強を嫌がる姿を見ると、「やる気がないのかな」「わがままなのかも」と感じてしまうこともありますよね。
でも実際には、子どもなりの理由があるのです。
年長児はまだ言葉で気持ちをうまく説明できないため、表面の行動だけを見て叱ってしまうと、やる気をさらに失ってしまうこともあります。
ここでは、子どもが勉強を嫌がる背景にある心理的・環境的な要因を整理しながら、親がどう関わればよいかのヒントをお届けします。
勉強が「楽しい」と思えない
勉強は本来、「知らなかったことを知る」「できなかったことができるようになる」といった喜びや達成感を感じられる活動です。
しかし、単調なドリルや一方的な作業ばかりが続くと、子どもにとっては“退屈でつまらない時間”になってしまうことも少なくありません。
特に5歳児は、「なぜ勉強しなければいけないのか」を理解するよりも、今この瞬間が楽しいかどうかを重視する時期です。
好奇心を刺激するきっかけが足りない
5歳児は、身の回りのすべてに興味を持ち、「どうして?」「なにこれ?」といった疑問を原動力に成長していく時期です。
こうした好奇心は、学びへの意欲にもつながる重要なエネルギーとなります。
しかし、日々の学習が決まった教材やドリル中心になってしまうとそうした知的好奇心が十分に満たされず、やがて学びそのものへの関心も薄れてしまうことがあります。
大人の視点では「学んでいる」と思えることも、子どもにとっては刺激が足りず退屈に感じてしまうことがあるのです。
子どもが心から「知りたい」と感じられるようなきっかけが少ないと、勉強そのものをつまらないものとして感じてしまうのです。
親のプレッシャーでやる気をなくしている
「そろそろ勉強しなきゃダメでしょ」「お兄ちゃんはもうこれできてたよ」などの言葉は、親としての励ましの気持ちから出てくるものかもしれませんが、子どもには大きなプレッシャーとして伝わってしまうこともあります。
「自分はできない」「ママをがっかりさせた」という気持ちが芽生えると、学習そのものに対する意欲も低下してしまいます。
特に結果だけを評価する声かけは避けたいポイントです。
「頑張って取り組んでいたね」とプロセスを認める関わり方に変えるだけで、子どもの反応が変わることもあります。
長時間の学習が負担になっている
集中力は年齢とともに伸びていくものですが、5歳児の集中時間はせいぜい5~10分程度が限界とされています。
それ以上を求めると、途中で飽きたり集中が途切れたりして逆効果になる可能性があります。
長時間取り組ませるよりも、短く区切って小さな達成感を積み重ねる方が効果的です。
褒められる体験が少なく自信を持てない
「できたね」「すごいね」と褒められる経験が少ないと、子どもは自分に自信を持ちにくくなります。
特に失敗を怒られた経験が強く残っていると、「どうせ自分には無理だ」と感じてしまうこともあるのです。
子どもは成功体験の積み重ねで自己肯定感を育みます。
「昨日よりひらがながきれいに書けたね」など、少しの成長でもしっかり認め、褒める視点が重要です。
子どもの立場になって考えてみると、なるほどな~って思ったりしますね。

イライラせずに5歳児のやる気を引き出す幼児教育

勉強を嫌がる5歳児の姿に、「なんとかやらせなきゃ」とつい焦ってしまう気持ちは分かりますが、無理に押しつけようとすると、子どもは勉強に対して苦手意識を持ってしまうことがあります。
大切なのは、「勉強=楽しい」と子ども自身が感じられる関わり方です。
ここでは、親のイライラを和らげながら、5歳児が前向きに学びに向かえる環境づくりや接し方のポイントを具体的に紹介していきます。
子供の好きなことと勉強を繋げる
子どもが興味を持っていることは、最高の学びの材料です。
好きな遊びや趣味と勉強をうまく結びつけることで、学ぶこと自体がワクワクする体験になります。
例えば、電車が好きなら路線図を見て地理を学ぶ、料理が好きなら材料を数えて足し算をする、絵を描くのが好きなら図形や色の名前を覚えるきっかけにもなります。
子どもは好きなことに取り組むとき、集中力が高まる傾向があるので、好きなものから知的好奇心を引き出す工夫がとても効果的です。
まずは5分から始めてみる
初めから「30分座って勉強しなさい」では、5歳児には重荷になってしまいます。
まずは1日5分からスタートすることが、学習の第一歩としておすすめです。
子どもが「集中できる時間」はごくわずか。その短時間に無理のない内容を設定し、終わったらしっかり褒めることが大切です。
短く始めて、「今日は5分できた」「明日はもうちょっとやってみようか」と段階的に増やしていく方が、やる気の持続につながります。
また、勉強するタイミングを固定するのも習慣化のコツです。例えば「朝食後に5分」「夕飯前に1ページ」など、毎日の生活の中に組み込んでみましょう。
学習環境を整える
環境が変わるだけで、子どもの集中力がぐっと高まることがあります。
「勉強に向かいやすい空間づくり」は親がサポートできる大きなポイントです。
学習環境を整えるポイント
- テレビやスマホが目に入らない場所で勉強させる
- 机の上を片付けて必要なものだけを置く
- デスクや椅子は安定して座れるものを選ぶ
- 照明は目に優しく、十分な明るさにする
さらに、気分が乗らないように見えるときは「特別な場所」で勉強させるのも効果的です。
リビングの一角、ベランダ、親の仕事机など、普段と違う場所だと子どもの気分が変わり、意外とやる気が出るものです。
成果を褒めるのではなく、頑張った過程に注目する
「すごいね、全部できたね!」という結果への評価も大事ですが、それと同じくらい大切なのは努力の過程を認めてあげることです。
たとえば、
- 「最後まで座って取り組んでいたね」
- 「難しかったけど諦めずにやってたね」
- 「昨日より丁寧に書こうとしていたね」
というように行動や工夫に注目して褒めると、子どもは「また頑張ってみよう」と感じます。
この声かけを繰り返すことで、結果にとらわれず「学ぶことが楽しい」という気持ちを育てることができます。
イライラしたくない!トイズアカデミージュニアで「勉強=楽しい」を定着させよう!
家庭での取り組みに限界を感じたとき、専門的なサポートを受けられる教育環境があると心強いものです。
トイズアカデミージュニアは、3歳から6歳の子どもが「遊びの中で学ぶ」ことをコンセプトにした幼児教室で、子どもたちが自然と勉強好きになる工夫が満載です。
ここでは、実際にどのような教育が行われているのか、また親子にどんなメリットがあるのかを紹介します。
トイズアカデミージュニアの遊びながら学べるカリキュラム
トイズアカデミージュニアの最大の特徴は、「遊び=学び」というアプローチを取り入れている点です。
子どもが興味を持ちやすいパズル、カード、ブロックなどの教具を活用しながら、思考力や表現力、集中力を養うカリキュラムを展開しています。
例えば、
- 粘土や専用の教材「かず丸」でおはじきを使い、数の概念を学ぶ
- 物語づくりや漢字かるたを通して言語能力を伸ばす
- ルールのある遊びで社会性や協調性を身につける
といった、子どもが主体的に参加できるプログラムばかり。
「学ぶことって楽しい!」という感覚が自然と育まれるのです。
トイズアカデミージュニアのメリット
トイズアカデミージュニアには、幼児期の学習に悩む家庭にとって魅力的なメリットがたくさんあります。
以下に代表的な3つのメリットを紹介します。
1.子どもの思考力や集中力が自然に育つ
一方的に知識を詰め込むのではなく、子ども自身が「考えてみる」体験を重ねる構成になっているため、思考力や集中力が驚くほど伸びるのが特徴です。
2.子どもの今に必要な学びの環境
低年齢ならではの学習面での悩み。プロにお任せ頂ければ得意を引き出し、苦手をサポートしていくことができます。
3.子どもが「自分からやりたい」と言い出す
楽しい体験を通じて、子どもが勉強に対して前向きになることで、「ママ、これもっとやりたい!」という言葉が自然と出てくるようになります。こうした姿こそが、学びの好循環の始まりと言えるかもしれません。
勉強しない5歳児にイライラしてしまうママ・パパからよくある質問

5歳児の勉強に関して、イライラしたり悩んだりしている保護者の方からは、共通する質問が数多く寄せられます。
ここでは、特に多い3つの疑問に対して、専門的な視点からわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にして下さい。
勉強が嫌いな子の特徴は?
勉強が嫌いな子どもには、いくつか共通する傾向があります。
たとえば以下のような特徴が挙げられます。
- 失敗を極端に嫌がる
- 集中力が続かない
- 注意されるとすぐふてくされる
- 「やりたくない」「面倒くさい」という言葉が良く出る
- 得意なことにしか手を出さない
これらの背景には、「できない経験が多かった」「過度に注意された」「勉強そのものが楽しくなかった」などの原因があることが多いです。
まずは子どもが安心して取り組める環境を整えることが、勉強嫌いの改善には欠かせません。
褒める機会を増やし、成功体験を積ませることから始めてみましょう。
勉強に前向きになれない子への関わり方で気をつけたいことは?
親のかかわり方が、子どもの学習意欲に大きく影響を与えているケースは少なくありません。
以下のような行動が、知らず知らずのうちに「勉強したくない気持ち」を強めてしまっているかもしれません。
- 「なんでできないの?」と責める
- 他の子どもと比べる
- 勉強に対する親の姿勢が後ろ向き
- 結果ばかりに注目して努力を認めない
- 命令口調で勉強を強制する
親の焦りやイライラは、子どもに伝わります。
一緒に楽しむ姿勢を持つことや、「頑張ったね」「考えてたね」と過程を認める言葉がけを心がけるだけで、子どもの反応は変わってきます。
合わせて読みたい
まとめ
5歳児が勉強を嫌がったり、やる気を見せなかったりする姿に戸惑いや悩みを感じるのは、多くの保護者に共通する思いです。しかし、子どもの行動には必ず理由があり、それを理解しながら関わることで、親子の関係もより良い方向へと変わっていきます。
この記事では、「勉強が楽しくない」「好奇心が刺激されていない」「親のプレッシャーが負担になっている」といった子どもの行動の背景を踏まえ、イライラを抑えながら子どものやる気を引き出すためのヒントをご紹介しました。好きなことと学びをつなげる工夫や、短時間から始める学習、努力を認める声かけは、今日からでも実践できる方法です。
この時期に「勉強って楽しい」と思える経験を積ませることは、将来の学習意欲を育てる土台になります。さらに、子どもの特性に合った教育方法や声かけを知りたいと感じたら、トイズアカデミージュニアにお気軽にご相談ください。
親として試行錯誤しながらも、子どもの成長を信じて向き合うあなたの姿勢が、きっと未来を豊かにしてくれるはずです。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #5歳 #勉強 #やらない #嫌がる #イライラ #教える #方法