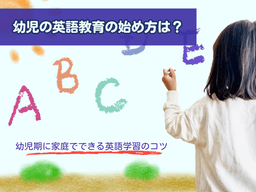情報処理能力は子どもの頃に発達させるべき能力
知能指数(IQ)が高く、学力や理解力・記憶力・処理速度のいずれも優秀。検査でも発達上の問題は発見されないのに作文や人との会話が極端にできず、就職後に大きな問題となって仕事ができなくなってしまう。このような若者の増加が社会問題になっています。
長年精神医学の面から発達問題に取り組んできた、医学博士で日本精神神経学会認定専門医である岡田尊司先生は、これらの原因を「統合機能の弱さ」によるものと分析しました。
「統合機能」とは高次の情報処理能力です。大人になってから訓練するのは非常に困難ですが、子どもの頃から適切な教育によって発達させるのは難しくありません。しかし、現在の日本の学校教育には「統合機能」を発達させる要素が少ないのです。したがって、それを補う教育が不可欠です。
情報処理特性でみた3つのタイプについて

人が脳で情報処理をおこなうときの特性を3つのタイプに分類すると、子どもに合った適切な教育の設計がおこないやすいです。
①【視覚空間型】
以下に特徴を列挙していきます。
- 目で見て、瞬間的に処理するのが得意
- 長時間何かをじっくり考えるということは苦手
- 集中力が続きにくい。気が散りやすい
- 自分の考えや気持ちを表現するのが苦手
- 理解してもらえないと暴力的になりやすい
- 計画性が乏しい。場当たり的、衝動的
- 感覚的に理解する能力に長けている
- 倫理理屈や基礎よりも応用から入った方が伸びる
※代表的な著名人(敬称略):スティーブ・ジョブズ、長嶋茂雄、本田宗一郎
②【聴覚言語型】
- 会話言語に強く、言葉の感覚も優れている
- 人を楽しませる会話が得意。会話の機能を理解し、聞いた言葉もよく覚えている
- 自分で本を読むよりも、誰かに教えてもらう方が頭に入りやすい
- 相手の気持ちを理解したり、場の空気を読んだりすることも堪能
- コミュニケーション能力や共感力が高い
- 映像や空間的な処理が苦手な場合が多い
- 地図が読めなかったり、空間図形の問題を理解しにくかったりしがち
- 立体的な絵を描くのが苦手。描かせると写実的な絵や緻密に計算された絵よりも物語的な絵になりがち
- 論理的で厳密な理論や、記号を用いた抽象的な内容の理解が困難。論理的で理屈っぽい説明には感動せず、興味を感じない
※代表的な著名人(敬称略):バクラ・オバマ、小泉純一郎
③【視覚言語型】

- 文字言語に強く、要旨をまとめることが得意
- 会話は苦手という人も多い
- 抽象的概念を扱うのが得意。物事を論理化や図式化して理解するタイプ
- 自分でオリジナルなものを作り出すのは不得手
- 記憶力がよく、ペーパー試験に強い。丸暗記よりも因果関係をきちんと整理した方が頭に入る
- ロジックがしっかりしていないと納得できない
- 文学・理数の両面に強い。
※代表的な著名人(敬称略):ビル・ゲイツ、井深大
もちろん「この3タイプのどれか1つのみ、当てはまる」というわけではありません。何かにおいて成功している人は、どれか1つの力のみではなく、複数の情報処理モードを使い分けています。
親御さんご自身に当てはめて考えてみると、どれかのタイプに近いかも!なんて感じるかもしれませんね。

子どものうちは異なる情報処理タイプの習得が可能
すでに脳ができあがった大人は、他の情報処理のタイプの習得は困難なので自分の特性を理解し、それにあった学び方や働き方をすることが望ましいです。しかし、子どものうちはまだまだ「複数の情報処理系を鍛える」ことが可能です。特性の長所を伸ばし、弱点を補強するような教育を設定してあげましょう。
子どもの脳は、大人の脳とは比較にならない「高い可塑性(かそせい)」を備えています。現在苦手なことでも、今後の継続的なトレーニング次第ではすっかり得意に変えてしまうことが十分可能です。そのためには、その子の特性に合った方法でトレーニングすることが大切です。
※可塑性…「変形しやすい性質」の意味であり、粘土を細工する様に人格の変化しやすい状態をいいます
子どもの特性を生かす教育法について

ここからは、上述の3つのタイプ別に、その特性に合った教育の仕方について解説していきます。
①「視覚空間型」の教育法
説明の時間をできる限り短くして、手や体を動かしながら体験で覚えていくように教え方を工夫しましょう。
クイズ形式やゲーム形式を多く取り入れ、集中して注意力が高まっている時に、要点のみを短くわかりやすく伝えます。「自分はこれが好きだ!」「これが得意だ!」という意識を抱かせます。
基礎がわからないままで構わないので、応用や実践に触れさせていきましょう。実力と自信を育ててから、改めて基礎や理論を学べばよいのです。基礎を学ぶのは、標準的な時間よりも遅くて構いません。
言葉による説教や解説より、どのように行動したらよいかを絵に描いたり、日課を図表にしたりして、根気よくくり返し行動させて習慣化させましょう。頭ごなしに叱らず、なぜそういうことをしたのか「理由」と「気持ち」を聞き出し「他にもっとよい行動はなかったか」を考えさせます。
このタイプの子が衝動的な行動を制御できるようになるまでには、他のタイプの子より長い年数がかかります。適切な指導をくり返していけば、必ず感情や行動をコントロールする力が育つので、長い目でみて根気よく育てましょう。
②【聴覚言語型】の教育法

3つのタイプの中ではもっとも多い比率で出現しやすいタイプです。論理的なこと、抽象的なことを高度に理解することが苦手で、xやyなど記号ばかりを扱った問題には興味を示しにくいです。常に具体的で身近な話を導入の切り口にしたり、抽象的なルールを説明するときも具体的な例をしめしたりしながら、理解を促しましょう。
例)おこづかいに硬貨を3枚もらいました。合計金額は200円です。もらった硬貨は何か当ててみましょう。
抽象的な言葉で考えることは苦手なので、幼児・小学校の頃から「論理的な思考法」や「具体化←→抽象化」を考えるトレーニングを意識的におこないましょう。【因果関係】【対比関係】【具体化←→抽象化】を意識する問いかけを、日常会話の中に取り入れてあげることが有効です。
【因果関係】を意識させるには「だから」「なぜならば」を活用しましょう。
例)「喉が渇いた~」と言ってきたら「だから?」と問いかけ「だから、お茶が飲みたい」と因果関係を明快な文章に誘導します。「なぜ、のどが渇いたのかな?」と問いかけ「なぜならば、汗をたくさんかいたから」「なぜなら、長い時間何も飲んでなかったから」「なぜなら、外が暑かったから」など原因を考えさせます。
【対比関係】を意識させるには、日ごろから「意味が反対の言葉」に慣れさせておきましょう。「比較の観点」を話題に出すことも大切です。
例)「エレベーター」か「エスカレーター」をお子さんに選ばせるのもよい方法です。「速さの観点」「混み具合の観点」など「観点をそろえて比べる」ということを数多く経験させましょう。
【抽象化】の能力を身につけるには、「つまり?」というキーワードを活用しましょう。
例)
- 「チョコレートケーキが食べたい」→「どうして?絶対にチョコレートケーキじゃないとダメなの?」
- 「チョコレートケーキでなくてもどら焼きでもプリンでもいい」→「つまり、甘いものが食べたい」
- 「ドーナツでも焼きそばでもおにぎりでもいい」→「つまり、お腹にたまるものが食べたい」
このように「抽象的に言い換える」というトレーニングを積極的に日常会話に取り入れます。
③【視覚言語型】の教育法

論理的な因果関係をきちんと説明しましょう。図式化して整理してあげます。ロジックがしっかりしており、わかりやすい図解であれば、学年をはるかに超えた難しい内容でも理解することが可能です。
早い時期から補ってあげたいのは「実体験から学ぶ」経験です。頭の中で上手にイメージできることも、実際におこなってみると思い通りにはいかないのだということを数多く実感させましょう。
動植物の世話や自然事象などの観察、工作や運動、人前で大きな声で話すこと、人に対して心を開き共感を得る話し方の練習、どう話せば相手がよく理解してくれるのかを実際の討論の中から学ぶことなどをトレーニングする機会を積極的に与えます。
難しいことを的確に分析し、抽象的に把握し、倫理的にまとめることができるのですから、コミュニケーション力や「理論と実態をすり合わせる能力」が身につけば大変な強みとなるでしょう。
お子さんがどんなことに強いかな?と意識をしてみることで、どのタイプなのかが見えてくるかもしれません♪

子どものタイプを理解して、複数の強みを育てましょう
今回紹介した効果的な指導のコツは、タイプによって「強みを強化するもの」にもなれば「弱点を補強」するものにもなります。
「実際に手や体を使ってどんどん体験するタイプの学習」は【視覚空間型】の子の強みであり、【視覚言語型】の子の弱みです。
「因果関係・対比関係・抽象化・具体化」を意識させる会話は【視覚言語型】の子の強みであり、【視覚空間型】・【聴覚言語型】の子の弱みです。
「人前で発表したり、クリエイティブな討論をする学習」は【聴覚言語型】の子の強みであり、【視覚言語型】の子の弱みです。

強みをさらに伸ばすときには、次々に高い目標を与えてもよいです。反対に弱点を克服するときには、負荷が大きくならないように小さな目標をスモールステップで少量与え、課題量を増やすことよりも「毎日継続すること」に重点を置きましょう。
静かにじっとしているのが苦手ならば、手や体を使って学ばせます。本を読んでも頭に入らないならば、情感豊かな物語にして耳から聞かせます。理論・理屈に強い子には「理屈と現実とのギャップ」をどんどん体感させます。
その子の特性に合った方法で今の時期からトレーニングしていけば、子どもの「統合機能」は豊かに発達し、将来的な成功のカギとなる自分だけの強みを獲得していけることでしょう。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #子ども #性格 #特性 #教育法 #情報処理特性