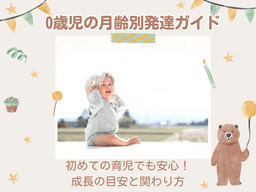1歳に見られる“数字の認識”

「1歳って、もう数字がわかるの?」そんな疑問を持つ保護者の方も多いかもしれません。
確かに1歳の子どもが「1、2、3…」と正確に数えるのはまだ難しい時期です。しかし実はこの時期、すでに“数”に対するごく初歩的な感覚が芽生え始めているのをご存じでしょうか。
ここでは、1歳ごろに見られる「数字の認識」について解説します。
「なんとなくの数がわかる」「多い・少ないを感じ取る」「数字に興味を示す」など、1歳児ならではの微細なサインに注目することで、今のお子さまの成長段階がよりクリアに見えてくるはずです。
1歳は「なんとなくの数」がわかり始める段階
1歳児はまだ言葉で数を言ったり、正確に「数える」ことはできませんが、すでに「なんとなくの数の感覚」を持ち始めています。
たとえば、1つのお菓子と3つのお菓子を並べたときに、量の違いに目を向けたり多い方を選ぼうとする行動が見られることがあります。これは「数量の感覚」が芽生えてきている証拠です。
この段階では、数そのものを理解しているというよりも、視覚的に物の“まとまり”を捉える力が発達している状態です。こうした自然な気づきが、のちの「数を理解する力」へとつながっていきます。
数えられないけど“多い・少ない”に反応できる
1歳児はまだ「1、2、3」と口に出して数を数えることはできませんが、目の前の物の「多さ」「少なさ」には敏感に反応するようになります。
たとえば、おもちゃが急に減ったことに気づいて探し始めたり、いつもよりたくさんお菓子をもらって嬉しそうな表情を見せたりする行動は、「量」に対する理解が始まっているサインです。
こうした反応は、数という“記号”ではなく、“量”という実体を通して理解している段階です。この経験の積み重ねが、次第に「数」という概念への理解に発展していきます。
「数字への興味」が育っているサイン
まだ数字を理解していないように見える1歳児でも、「数字に対する興味」が育ち始めているケースは少なくありません。
たとえば、大人が「1、2、3」と言うのを真似しようとしたり、数字の書かれた絵本やブロックに手を伸ばしたりする様子が見られることがあります。
こうした行動は、数字が“特別なもの”として目に留まり、興味の対象になっている証です。
この興味を大切に育てていくことで、自然と「数字=楽しい」というポジティブな印象を持つようになります。それが、のちの学びの土台となっていくのです。
お子さんとの会話を楽しむ中で、意識的に数に触れていくとお子さんも興味を持ちやすいですね♪

数える力を育む方法は?年齢ごとの発達ステップ
数を数える力は一朝一夕に身につくものではありません。特に1歳児にとっては、数字を読み上げることよりも、日常の中での「まねっこ」や「繰り返しの経験」が、理解への第一歩となります。
ここでは子どもの年齢ごとの発達段階に合わせて、「数える力」がどのように育まれていくのかをわかりやすく整理して解説します。
1歳〜2歳の「カウントごっこ」から始まり、2歳前後で見られる“量と数のつながり”の理解、さらに3歳以降の本格的な「順序としての数え方」へと、段階的に変化する過程を知ることで、お子さまの今の姿に合った関わり方が見えてくるはずです。
1歳〜2歳の「真似」から始まるカウントごっこ
1歳ごろの子どもは、言葉や動作を「まねる」ことから多くのことを学びます。
数字についても同様で、大人が「1、2、3」とリズムよく数える姿を見て、自分でも声に出してみたり、指を動かす「カウントごっこ」を楽しむようになります。
この時期はまだ数の意味を理解しているわけではありませんが、「数字の音」や「繰り返しのリズム」に触れることで、数える行為そのものに親しみを感じるようになります。まねっこ遊びの延長として、積み木やおやつを一緒に数えると、自然な形で「数える楽しさ」が芽生えていきます。
2歳前後に見られる“数と量”の一致理解
2歳になると、数の言葉と実際の“量”とのつながりに気づき始める子が増えてきます。
たとえば、「2つちょうだい」と言われておもちゃを2つ渡せたり、「お菓子は3つだけ」と伝えると、実際に3つを手に取ったりする様子が見られるようになります。
この段階は、「数=言葉」と「量=目に見えるもの」の一致を少しずつ理解していく大切な時期です。この理解が進むことで、数をただ唱えるだけでなく、意味のある行動として使えるようになります。
お手伝い遊びや買い物ごっこなど、実生活に即した場面で数を使うと、学びがより深まります。
3歳以降の「数の順序」と「目的ある数え方」
3歳を過ぎると、単なるまねや感覚的な理解から一歩進んで、「順序を意識した数え方」ができるようになります。
たとえば、1から5までの数字を順番に唱えながら、並んだおもちゃを1つずつ指さして数えるなど、「目的をもって数える」行動が見られます。
この時期には、数が「順番」であること、「最後の数が全体の数を示す」ことを学び始めます。これは、算数の基礎になる非常に重要なスキルです。
数字の順序や意味をしっかり身につけるには、日常の中で繰り返し経験することが何より大切です。遊びの中に取り入れることで、楽しみながら自然と力が育ちます。
意識的に数に触れられる環境作りこそが親御さまができること♪

数字への興味を育てる家庭での関わり方

数字への興味は、日常の中でのちょっとした工夫や声かけから育てることができます。特別な教材を用意しなくても、家庭の中には「数」に触れるチャンスがたくさんあります。1歳という年齢は、まさにそうした日常体験の積み重ねによって、数への親しみが育ち始める大切な時期です。
ここでは家庭でできるシンプルな工夫や、日々の関わりの中で自然と「数」を感じ取れるような習慣づくりのヒントをご紹介します。
また、歌や絵本、おもちゃといった身近なアイテムを活用した楽しい数体験、さらには「もっと学ばせたい」「うまく関われているか不安」と感じたときの選択肢として幼児教室という学びの場についても触れていきます。
無理に教え込むのではなく、楽しさの中に「気づき」がある、そんな関わり方を目指していきましょう。
生活の中で自然に数を取り入れる習慣づくり
数字に対する興味は、日々の暮らしの中での“さりげない体験”から育ちます。特別な時間を作らなくても、たとえば「りんごが2つあるね」「おてては10本あるよ」といった声かけを意識するだけで、子どもは自然と“数の存在”に気づいていきます。
階段をのぼるときに段数を数える、買い物のときに果物の数を一緒に確認するなど、実際の物や動きと数字を結びつけることで、理解がより深まりやすくなります。生活そのものが学びの場になるような、シンプルで続けやすい関わり方が理想的です。
効果的な声かけの例
・「バナナが1本、2本、3本あるね。さあ食べよう!」
・「階段をいっしょに数えよう!いーち、にーい…」
・「クッキーが5枚あるよ。○○ちゃんはいくつ食べたい?」
・「お人形が3人いるね。ベッドも3つあるかな?」
こうしたやりとりを日常に取り入れることで、子どもは“数える楽しさ”を自然に体感していくようになります。
歌や絵本・おもちゃで「数にふれる体験」を重ねる
音楽や絵本、おもちゃは、数字に触れるきっかけをつくる強い味方です。
たとえば、「いち、に、さん」とリズムに合わせて歌う童謡や、数をテーマにした絵本は、1歳の子どもにとって楽しく、覚えやすい形で数の概念にふれる手段となります。
特におすすめなのは「いっぽんばしこちょこちょ」や「いちじくにんじん」など、繰り返しの中で数字が登場する歌です。耳に残りやすく、親子で一緒に歌うことで、言葉のリズムと一緒に数の感覚も育まれていきます。
数字が書かれたブロックや、数に対応する動物の絵が描かれたカードなどの知育玩具も、視覚や触覚を通じて理解を助けてくれます。「数える=楽しい」と感じる体験が、数字への前向きな興味を育てていきます。
数に親しむきっかけを増やすなら幼児教室もおすすめ

「家庭だけでは不安」「もっと体系的に学ばせたい」と感じたときには、幼児教室の活用も選択肢のひとつです。
0~3歳を対象にした幼児教室ベビーパークでは、年齢に応じたカリキュラムの中で「数」と「量」の感覚を育む活動が用意されています。
特に注目されているのが、「Mathリーディング」や「100玉そろばん」などを用いた遊びです。Mathリーディングは「数字の読み方」ではなく「数の意味」を理解することに重点を置いた学習法で、「3つある」「1つ減ったら2つになる」といった数量の変化を視覚的に体験しながら学んでいきます。
たとえば、ベビーパークでは「mathカード(ドッツが描かれたカード)」を使い、「5といくつ」の考え方で数を捉える練習を行います。「7は5と2」「9は5と4」など、数の構造を分解・合成する感覚を無理なく身につけられるのが特徴です。
こうした視覚的なアプローチは、数字の形にとらわれすぎず、数の「量」と「意味」への理解を深めるのにぴったりです。特に集中力や好奇心が芽生え始める1〜2歳ごろにぴったりの学び方として、多くの家庭に選ばれています。
親子で一緒に楽しむことが「数字って楽しい」の第一歩
数字の学びは、親が教えるものというよりも、親子で“共に体験する”ことが何より大切です。
「いくつあるかな?」「どっちが多いかな?」といった問いかけを通じて、子どもと一緒に考えたり、遊びながら数に触れたりすることで、自然と学びが深まっていきます。
親の楽しそうな様子や笑顔が、子どもにとっては何よりの刺激になります。「数字っておもしろい」と感じる気持ちが芽生えると自発的な関心が広がり、将来的な学びにもつながっていきます。学習の土台づくりは、まず“楽しい”という気持ちから始まります。
合わせて読みたい
まとめ
数字の世界にふれることは、決して“教えるべきこと”ではなく、日々の暮らしの中でゆっくり育っていく感覚のひとつです。1歳という時期は、その入り口に立っている段階。だからこそ、子どものちいさな反応や興味に気づきながら、楽しみながら関わっていくことが何より大切です。
数字を覚えさせるのではなく、「いっしょに数えてみる」「なんとなく気づく」を積み重ねることで、子どもの中に自然な理解の芽が育っていきます。親も子も、気負わず一緒に楽しめる時間が、やがて学びの土台となっていくはずです。
「もっとこの子に合った関わり方を知りたい」と思ったときには、専門家の力を借りるのもひとつの方法です。ベビーパークでは、Mathリーディングや100玉そろばんなどを通じて、数字への感覚を無理なく育てるプログラムが用意されています。
気になる方は、ぜひ一度教室体験にお越しください。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #1歳 #数字 #発達 #いつから #言える





.png&w=256&q=75)