「鏡文字」って?
「鏡文字」とは、上下はそのままで左右を反転させた文字のことです。鏡に写すと普通の文字に見えるので鏡文字と呼ばれています。漢字の鏡文字はほとんど見たことがないですよね。一般的にひらがなを書けるようになった5~6歳の子どもが、文字を鏡文字で書いてしまうことが多いようです。「し」や「の」という比較的簡単な文字に多く見られます。
なぜ鏡文字になってしまうのか
なぜ子どもは鏡文字を書いてしまうのでしょうか。明確な理由は判明していませんが、いくつかの要因が重なって起こることと考えられます。では、どのような要因があるかみてみましょう。
左右が上手く把握できない
左右がわかるようになるのは4歳くらいからと言われていますが、成長の具合によって6歳くらいまでは、「右に曲がって」と言っても「どっちだっけ?」と迷ってしまう子どももいます。
鏡文字とはいかないまでも、「お」の点が左側についていたりすることは小学校に入学しても見られることです。
文字をイメージで記憶している
幼児期は右脳の活動が活発であると言われています。右脳はイメージを司る脳なので、小さい子どもは図形などと同じように文字もイメージとして捉えてしまいます。ですから、幼児期には「薔薇」といった難しい漢字もイメージと音で覚えてしまうことがあります。3歳でも「文字が読める」というのは、「あ」「い」「う」といった文字をイメージと音で覚えているからなのです。
左利き
ひらがなや漢字は右手で書くことを前提に作られています。右手で動かしやすいような書き方になっていますから、左利きの子は自分が書きやすいように書くと鏡文字になってしまうのです。
鏡文字を書いているお子さんを見ると、どうして?と思うかもしれませんね。直した方が良いのかどうか、見ていきましょう♪

鏡文字は直した方がいい?

鏡文字は脳の発達が進んでいけば、自然と直っていくものです。ですから、慌てて直したり、否定せずに見守ってあげましょう。
どうしても気になってしまう、という場合には次のような取り組みをしてみてください。
文字に興味を持たせる
文字を書くにも練習するにも、まずは文字に興味を持ってもらうことが大切です。文字に興味を持ってもらうのに、一番役立つのはやはり本を読むことです。
ひらがなで書いてある絵本をたくさん読んであげることで、「自分でも読みたい」と思ってもらうことが第一歩でしょう。文字に興味が出てきたら「あいうえお」の絵本などで「『あり』の『あ』」というように言葉の構成として文字を覚えていくと覚えやすいです。
ひらがなをたくさん見せる
子どもは形から文字を覚えますから、正しい形をしっかり頭にインプットしてあげることも効果的です。「あいうえお」の絵本を見せるのももちろんいいですし、ひらがな表をお風呂に貼って湯船につかりながら一緒にみるのもいいですね。ひらがなが大きく書いてあるかるたをするのもいいでしょう。
自分が書いた文字とひらがな表を見比べていたら、「あれ?なんかこの字がちがうぞ」と自分で気付けると理想的です。人から指摘されるよりも素直に直すことができます。
自信をつけさせる
「これちがうよ!」と、鏡文字であることを「いけないこと」のように言ってしまうと、子どもは文字を書くことが嫌いになってしまいます。鏡文字を指摘するよりも、頑張って文字を書いたことを認めてあげましょう。
「たくさん書いたね、すごいね」「頑張って書いたんだね」と褒めてあげれば、もっと書きたいと思うでしょう。その中で「し、し、し」などと言いながら手をもって一緒に書いてあげると、子どもも自然と正しい形を認識できるようになります。
もしも、ドリルなどをやっているならば、間違えたものにバツをするのではなく、上手に書けているものに花丸をしてあげてください。子どもの自信とやる気を伸ばしてあげましょう。

なぞり書きには要注意
ひらがなの練習でなぞり書きをよくさせますが、なぞり書きはなぞることに集中してしまい、文字を覚えることには役立たない場合もあります。なぞり書きをする時は、できるだけなぞる線が薄いものを選びましょう。
書く練習をするなら、ひらがな表を見ながら書く、指で机や空中に書くなど、「記憶をして書く」ことをくり返す方が正しい形を覚えるのにも役立つでしょう。頭で覚えている文字と自分が書いた文字を比較して「何か違う」と気づけることが大切です。
交換日記をする
文字への興味がつき、文字を書くことにも慣れてきたら、文を書くことへの興味を伸ばしましょう。お友だちにお手紙を書くこともいいですが、お父さんやお母さんと毎日交換日記をするというのも楽しく続けられる方法です。
日付を書くことで平仮名だけではなく、数字を書く練習にもなりますね。はじめは「きょうはおにぎりをたべたよ」のように短い文章でかまいません。それに対して、お父さん、お母さんはひらがなでお返事を書いてあげましょう。文字の間違いや鏡文字があっても指摘はしません。子どもが「書くことが楽しい」と思えることを目標としてください。
左右を覚える遊びをする
左右が認識できていないという観点から鏡文字を直していくなら、左右を正しく認識させることをやってみましょう。
「〇〇は右、××は左」のように両方を一緒に覚えさせようとすると混乱してしまいます。左右を覚える時は、「右手でタッチ!」と声をかけて右手のタッチをする、といったように「右はこっち」ということだけをまず覚えさせます。そうすると、右の逆は左、ということが自然と身に付きます。これが身に付いてから「旗揚げゲーム」のような遊びをしていくと、楽しく左右を覚えられます。
鏡文字を直させたいと思い、つい指摘をしてしまいがちですが、書きたい気持ちを育て、正しい書き方に気づかせてあげるようにしましょう♪

身近にもある鏡文字

鏡文字は子どもの文字のお悩みで聞くことの多い言葉ですが、会社のロゴやデザインなどでもよく使われています。
名古屋の救急車は、ボンネットに「救急」の文字を左右反転させた「鏡文字」で書かれています。
これは前方にいる車両が後方から近づく救急車をルームミラー等でみると、文字は反転した普通の状態に見えるので、接近してきた車両が救急車であることをわかりやすくするためです」とありました。
前を走る車にも、バックミラーやルームミラーなどで救急車であることを気づいてもらうためにしているのですね。
有名な玩具店「Toys “Я” Us」もそうですね。これは文字を習い始めたアメリカの子どもたちの多くが、アルファベットの『R』を鏡文字で書いてしまうことにヒントを得て、子どもたちに親しみを持ってもらいたいという想いからできたロゴだそうです。
私たちの身の回りには、意外とたくさんの鏡文字が隠れているのかもしれないですね。
まとめ:鏡文字で脳トレも
最近は大人の脳トレの手段として、鏡文字を書くことがあるようです。鏡文字を書くことで、記憶や感情の制御、行動の抑制など、さまざまな高度な精神活動を司っている前頭前野を刺激し、脳を活性化するのだとか。大人が実際にやってみようと思うと、結構難しいものです。鏡文字が書けるって、実は凄い能力なのかもしれませんね。
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児

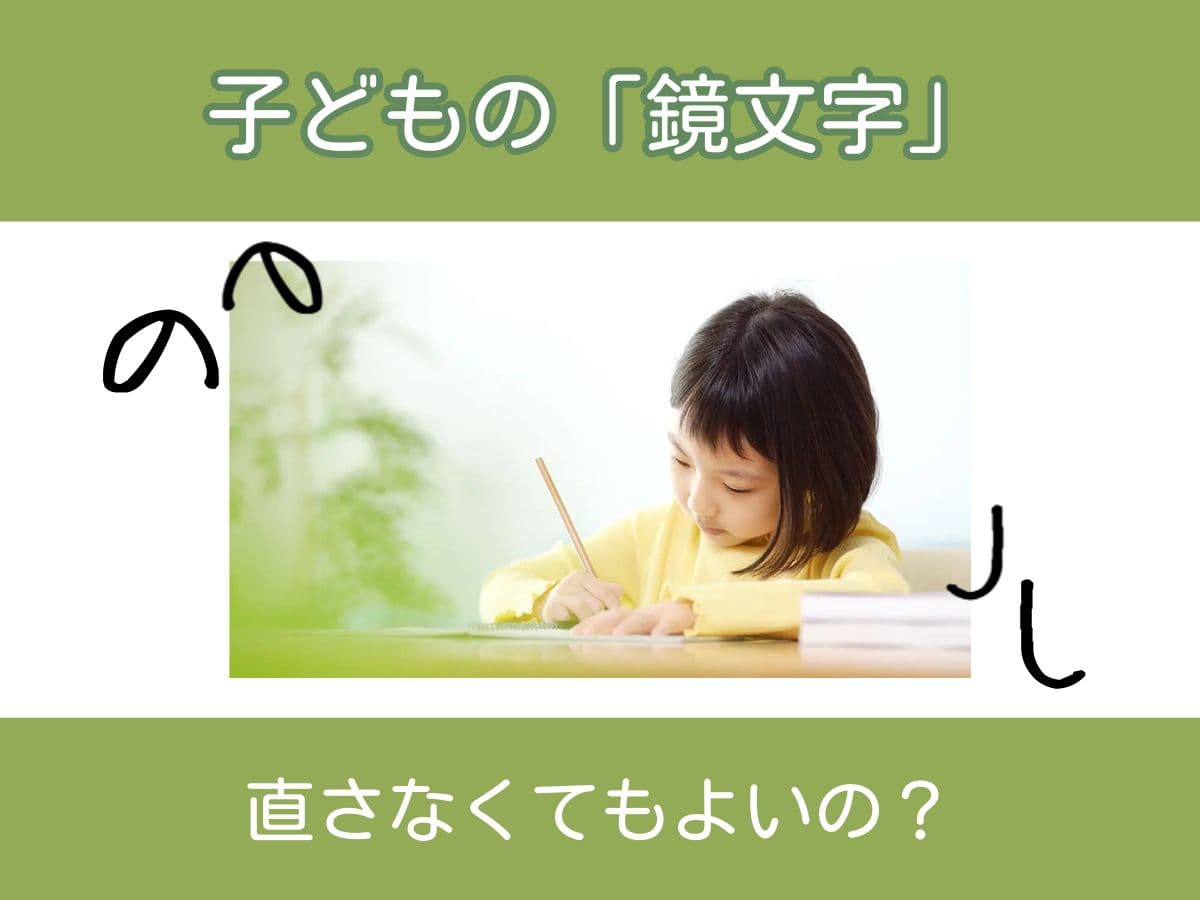










.png&w=256&q=75)












