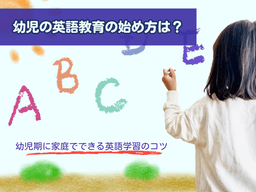子どもが3歳ごろになると、両親の育児の疑問や悩みに新たな局面が訪れます。これまでは食事や睡眠など生活習慣の形成に関するものがほとんどだったのに対し、子どもの「心のあり方」、つまり感情や情動を理性でコントロールする際に「このような時には、こうするべきだ」という自分なりの規範を作り上げていくための悩みが多発してくるのです。
難しい問題ではありますが、それは子どもの知能が動物に近かった発達段階から、ついに知性的な人間の子どもとして成熟してきた証でもあるのです。
子どものうちに「嘘はいけないもの」と意識づける事が大切
乳幼児は明らかな事実のみで構成される単純なパターン暗記であれば、情報の与え方によっては楽々と覚えてしまいますが、抽象的な概念を用いて複雑な判断を求められるような課題は苦手です。
小さい子どもには「このような時にはこう。でも、こういう時にはこう変えるのよ」などと複雑なバリエーションを話してみたところで混乱するばかりです。ですから、まず基本の大原則として「嘘は絶対にいけないもの」という一つの考え方を、子どもが小さいうちに強く意識づけます。
嘘をつくのは悪いことか?
では、「嘘」というものは本当に悪いものなのでしょうか。親がそこに確信を抱いていないと、子どもへの言葉も揺らいでしまいますので、ここはしっかり整理しておきたいものです。
嘘というのは他人や自分自身を欺く行為、真実から目を背ける行為であり、本質的には良くないものです。他人に対して、本当の自分の心を見せないことは不誠実です。どれだけ表面上は良い顔をしていたとしても、心の中で何を考えているのかわからない人に対しては誰も心を許しません。故意であろうとなかろうと、「約束を守れなかった」など結果的に嘘になってしまうものであれ、嘘というのは人の信頼を著しく低下させてしまう、とても恐ろしいものなのです。
また、他人に対しての嘘だけではなく自分自身の心を偽る嘘もよくありません。自分の感情を無理矢理抑え込めば、精神のどこかにひずみが生まれ、いずれ体にまでも影響を与える疾患につながりかねません。自分の能力を過小評価または過大評価することも良くありません。本当の自分を見つめなければ、適切な学びは得られないものです。昨日の自分よりも一歩でも前進するためには、自分自身に対して正直に、真正面から向き合うことが大切だと考えます。
「よい嘘」とはたいてい、真実を正直に伝えることが相手の心を傷つける時ではないでしょうか。言わなくても済むことならば真実を伝えたくないという気持ちは、相手を思いやる優しい心から生まれるものです。
.jpg&w=2048&q=75)
しかし、もしも相手の心が真実を認め、受け入れ、乗り越える強さを持っていたとしたら嘘をつく必要はありません。つまり、お互いに優れた人格者同士であった場合には、嘘をつかずとも済むことになります。
他にも、気の利いたジョークへ用いるような、誰を傷つけることのない嘘もありますが、これは嘘とは分けて「フィクション」や「言葉遊び」に分類するのが適切だと考えます。ですから、わが子を人から信頼される人間に育てたいと願うならば、まずは大原則として「嘘は絶対にいけない」と刷りこむことが非常に重要といえます。
嘘はいけないと分かっていても、つい出てしまう子どもの嘘。これらにどう対応していくべきなのか、考えてきましょう。

「嘘はいけない」だけでは子どもの心に響かない
子どもに「嘘は絶対にいけない」と教えることは大切ですが、ただしそれは今ただちに「子どもが嘘をついたら困る」と考えることと同じではありません。現在、とても正直で素直な子どもでも、いつか必ず嘘をつきます。子どもが大人に成長する過程においてそれは当たり前であり、大変健康で順調な精神発達の証ですから心配する必要はありません。
では、どうやって子どもの「嘘」と向き合えばよいのでしょうか。
小・中学校には道徳の授業がありますが、挨拶の仕方や、人を叩くのはよくない、人の物を取るのはよくない、そんなことを知らない小学生なんているのでしょうか。これらの善悪は2歳児でも本能的に感じ取ることができます。しかし、なぜか人間の悪事は社会からなかなか消えません。
.jpg&w=2048&q=75)
嘘をつくに至った理由まで深く思いやって初めて子どもに響く
人は望ましくない行動をとってしまう時にはそれなりの理由があるものです。その行動を選択せざるを得ないところまでなんらかの形で精神的に追い込まれているものです。悪いことをしてしまった人を非難し責めることは簡単です。悪いことだと指摘されて簡単に悔い改められるくらいならば、最初から誰も悪いことなんかしません。
子どもの行動の表面だけを見てよい悪いと語るのではなく、そういう行動に至った理由まで、深く思いやる姿勢を大人が見せた時に初めて、子どもの心は大きく震えるものです。子どもの嘘への対応も同じです。ですから、子どもに「嘘をついてはいけない」と言いきかせるだけでは不足に感じるのです。
「怒られないようにとっさに出る嘘」への対応
さて、ここからはコラムNo.82「子どもが嘘をつくのはなぜ?~2歳半からの幼児期の子どもの嘘の特徴について~」でもご説明した、子どもに見られる嘘の15種類の分類のうち「怒られないようにとっさにでる嘘」への対処法について詳しく解説していきます。
ちなみに嘘の15分類は以下になります。
相手をだます気がない嘘
1.空想が膨らんで現実と混同してしまう
2.話をよく理解していないためおかしな回答をする
3.表現力〔語彙〕不足のためうまく意思を伝えられない
4.言葉遊び
.jpg&w=2048&q=75)
子ども自身が「嘘をついている自覚のある」嘘(=親としての対応が必要)
5.願望が大きくなって現実と混同してしまう
6.怒られないようにとっさに出る嘘
7.自分をかばうためにつじつまを考えながらつく嘘
8.相手の気を引いて自分に注目してもらいたい
9.本当の自分の気持ちを理解してもらえないいらだち
10.根ほり葉ほり聞かれる面倒を避けるため
11.立場の強い子からの口止め
12.仲間をかばうため
13.親の期待に応えて喜ばせるため
14.ねたみや復讐
15.相手の心を傷つけないため
乳幼児期の嘘は、空想と現実が混ざったり、または語彙が未熟だったりするのが原因で、子ども自身は嘘をつく気持ちなどまったくありません。こちらも嘘だとは見なさないようにすることが大切です。ごく自然に「へえ~そうなのね」と、お子さまが正しいことを言った時と同様に頷いてあげるのがよいと考えられています。知能と言語の成長が進めばこのようなことは自然に言わなくなります。
「怒られないようにとっさに出る嘘」の特効薬は、怒らず穏やかに諭すこと
さて、幼児期につく最初の嘘らしい嘘は、たいてい「怒られるのを回避するため」につくものです(⑥番目の嘘)。おもちゃを壊してしまった、お友だちのものを取ってしまったなど、「悪いことをしてしまった」という自覚が子どもにある時に、大人が怖い顔をして「これ、あなたがやったの?」と問えば、子どもはとっさに「やってない!」と答えます。あるいは「宿題はもう終わったの?」という質問に「終わった!」と答えてしまうのもこのパターンです。
両親は「どうして嘘なんかつくのか」と悩みますが、子どもの単純な思考は目の前の「怒られる恐怖」から逃げ出すことしか考えられなくなっているだけのことです。ですから、このパターンの時に嘘をつかせない特効薬は、「怒らないこと」だといえます。怒るのではなく、「穏やかに諭す」「言い聞かせる」という習慣が身につくと、子どもが嘘をつく回数は減っていくでしょう。
「嘘はいけない」を刷り込むための接し方
また、「怒られたくないから出る嘘」は「嘘は絶対にいけない」と刷りこむ大チャンスにもなります。子どもの「やってないよ」という嘘をあばける明らかな証拠がある時に次のように接します。
1.「嘘は絶対についてはいけません。正直に話せば怒りません。」と約束します。
2.穏やかに「もう一度聞きます、あなたがやりましたか。」とたずねます。
3.正直に自分がやったと打ち明ければ、抱きしめておおいに褒めてあげます。
やってしまったことはいけないことだったという部分はあいまいにせず、言葉で「なぜいけなかったか」をもう一度、「子ども語訳」を意識しつつ端的に伝えます。悪いことは悪いと穏やかに話したうえで、正直に言えた勇気をとても褒めてあげます。
合わせて読みたい
4.子どもがそれでも嘘をつき続けた場合、こちらには明らかな証拠があるのだから、まずはその事実を見せます。そして、「大人だって失敗はします。だから、お母さんはやってしまったことは怒りません。でもね、嘘をつくのは本当にいけないこと。お母さんはあなたが嘘をついたことを怒ります。」と厳しく言います。とはいっても、「怒ってみせる」迫真の演技が重要で、自分の感情で怒ることはしません。
「叱ること」で嘘を抑制することは望ましくない
3歳未満の子どもの困った行動というのは、ほとんどが本能的欲求から生じていることが多く、「叱ること・怒ること」でそれらを抑制することは望ましくないと考えられています。
欲求が小さいうちに満たせるものは満たし、欲求をコントロールする必要があるものは、子ども自身で自分の欲求と周りへの影響のバランスをとることを学ばせる必要があります。恐怖で縛るだけでは、恐怖というタガが外れた時に欲求は増大したり歪んだ形で表れたりしてしまいます。
しかし、本能的な欲求から嘘をつきたくてつく子どもはいません。
.jpg&w=2048&q=75)
この場合の本能的な欲求は「トラブルから逃げ出したい」ということであり、嘘をつくのは知能が発達したことによって覚えた「逃げ出す方法」なのです。
ですから、叱る・怒るという方法で「嘘をつく」という行動を減少させても抑圧にはなりません。もともと怒られたくなくて嘘をついたのですから、「失敗をしても正直に言えば褒められて、嘘をついた方がむしろ怒られる」とインプリンティングされると、次第に子どもの「怒られたくないための嘘」は減少していくでしょう。
まとめ:子どものうちに「嘘はいけないもの」と叱らずにしっかり伝えることが大切
.jpg&w=2048&q=75)
いかがでしたでしょうか?
子どもにまずは「嘘はいけないもの」としっかり伝える重要性と、それは「叱ること」ではなく穏やかに言い聞かせることがポイントである旨が理解いただけたかと思います。
さらに次のコラムNo.129「嘘をつかない子供に育てるために②~「自分をかばう嘘・自分を大きく見せる嘘」への対処法~」では、子どもの「自分をかばう嘘・自分を大きく見せる嘘」への対処法を中心にご説明していきます。もしよかったらあわせて参考にしてみてくださいね。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #子供 #嘘 #うそ
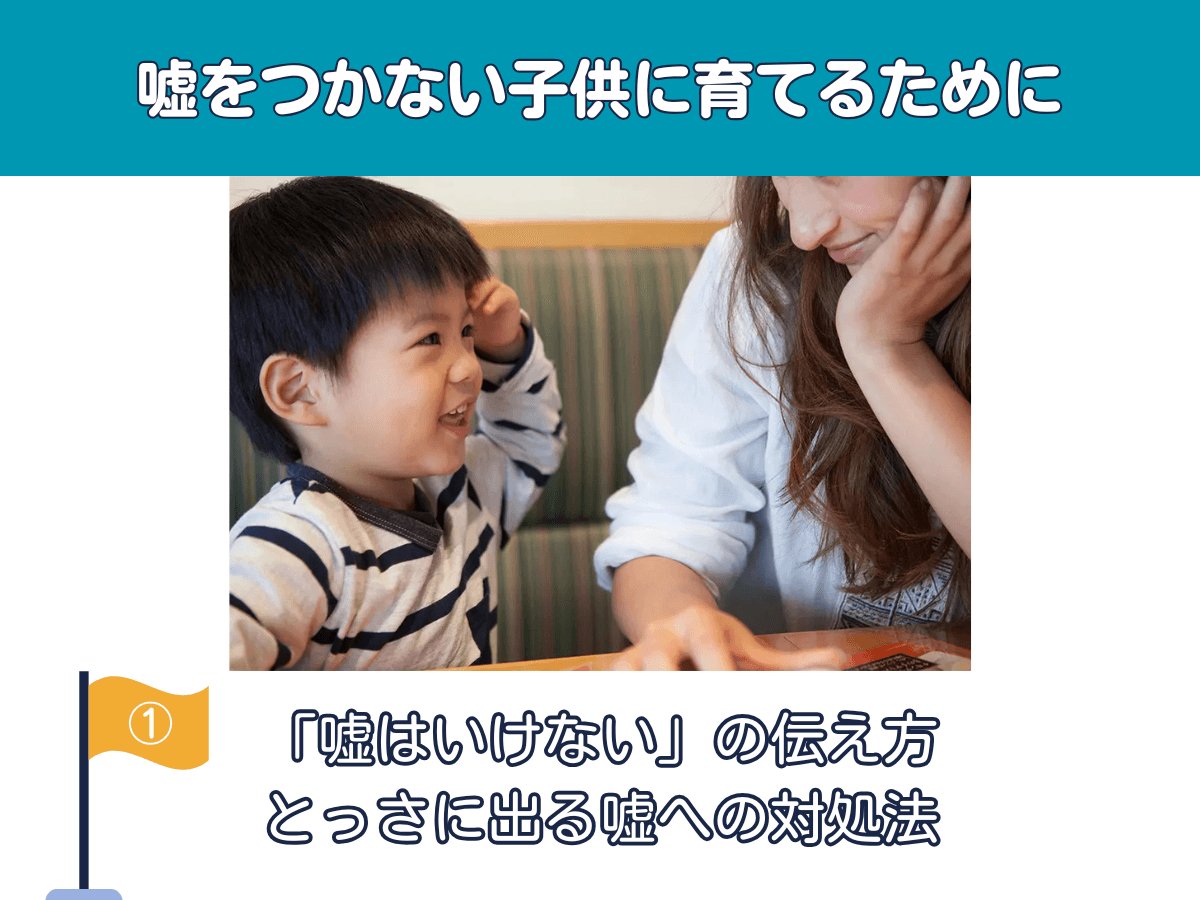
.jpg&w=256&q=75)

.jpg&w=256&q=75)