3歳児の理解力の目安は?
まずは簡単な目安を一覧で見てみましょう。次にあげる13項目が、3歳児の理解力を確認するためのチェックポイントです。
- 人の話をしっかり聞ける
- 集中して物事に取り組める
- 「もしも」の仮定の話が理解できる
- 発想力が柔軟
- 質問に対して適切な答えを返す
- 会話に接続詞を使っている
- 経験したことをしっかり話せる
- 理由をうまく話せる
- 文字・数字に興味がある
- 色の判別ができ、色の名前を覚えている
- じゃんけんができる
- 左右が分かる
- ハサミをうまく使える
.jpg&w=2048&q=75)
全てを上手にこなせる必要はなく、当てはまっている個数が多ければ多いほど理解力が成長している目安になります。ただし子どもの性格によっても左右されるので、注意が必要です。
3歳児がどれだけたくさんのことができるか聞いて、ワクワクしちゃった!話をよく聞いたり、じゃんけんができたりするなんて、すごいよね!数を数えたり、色や形を認識できるようになるって、どんなに楽しい冒険が待っているかな?

数が数えられる
3歳になって数の認識がしっかりでき、なおかつ少ない数を順に数えられるようであれば理解力があると言えます。
成長するにつれ、数の概念が当たり前に身についていきますが、少し前まで言葉をあまり話せなかったり、意味を理解している言葉が少なかったりといった子どもにとってはすぐに数字の概念をとらえるのは難しいことです。
色や形が認識できる
3歳児は言語能力が急速に発達して言葉の意味が理解できるようになる時期ですが、同時に色や形の認識も進みます。
例えば赤色の積み木を見たときに「これは赤だ!」とはっきり理解できたり、「紙に三角を書きたいな」と思ってその通りに描写できたり、赤や三角などの単語と色・図形が結びついていたら理解力がある証拠です。
.jpg&w=2048&q=75)
記憶力の発達
3歳のうちにその日に起こったことや、少し前に起こったことを言葉にして伝えられれば記憶力が発達しており、なおかつ理解力も身についています。もしくは、すでに読み聞かせたことのある絵本のストーリーを簡単に覚えていても、記憶力が順調に成長している証拠です。
前兆としては、以前経験したことをうっすら覚えていて、その記憶をもとに動作を起こしている状態から始まります。
定期健診のために通る道は痛い、悲しい、怖いなどのネガティブな記憶が残っており、泣く動作につながります。一方で楽しいと感じた遊びの準備を始めると駆け寄る動作につながるのです。このように感情として強い印象が残っていると記憶として残りやすく、徐々に記憶できる量も増えていくのが特徴です。
さらに成長すると、時間の流れがある程度理解できるようになります。ただし過去を表す言葉として「きのう」を多用するお子さんが多いようで、徐々に時間軸と言葉が一致していき、最終的にはおととい、明日、明後日などの細かい表現も出現してきます。
「なぜ?」「どうして?」など疑問を持つようになる
.jpg&w=2048&q=75)
3歳児がさらに知識を増やしていくために必要なのが、好奇心や探求心です。3歳になるまでは親が一方的に話しかけたり、教えたりする機会が多かったのが、次第に子ども自ら答えを求めるようになり、「なぜ?」や「どうして?」などの質問を投げかけてきます。
ここでしっかり応答すると言葉や知識のレパートリーが増えるだけでなく、コミュニケーション能力も培われるのがポイントです。子どもにとって会話の中身よりも、自分の問いかけにしっかり応答してくれた事実が大切です。子どもから話しかけられたら、できるだけ応えるように意識してみましょう。
合わせて読みたい
理解力が上がることによるメリット
理解力が上がることによるメリットは、次の2つです。
- 人との対話がスムーズになる
- 仕事ができる
子どものうちはあまり差が出ませんが、成長するにつれて理解力の差が明確になっていきます。
人と会話した際にその内容をスムーズかつ正しく解釈できるかは、理解力が大きく関わっています。勉強やスポーツでも、理解に優れている方がより素早くコツをつかんで取り込めます。
また相手の要求を正しく読み取ったり、自分の状況を正しく把握できたり、状況に沿った対応ができたり、社会人になって仕事をする最中でも理解力は重要です。
さらに理解力がある分、しっかり基礎が固められるので応用力も次第と高くなります。このように理解力は仕事や勉強だけでなく、日常生活でも欠かせない大切な力です。
ただし成長には個人差があるので、神経質になりすぎるのもよくありません。子どもの理解力としっかり向き合う姿勢が大切です。
子どもの理解力を高めるためにできること
子どもの理解力を高めるためには、大人が協力してきっかけを作ってあげるのが重要です。強制的に勉強させるよりも、遊びとして教育プログラムを取り入れ、子どもが乗り気で参加してくれる内容がおすすめです。
子どもの理解力を高めるために、以下のような例があります。
1.日常生活で数字と個数を結び付けてみる
数字の概念を理解してもらうには、日常生活で数字を積極的に使ってみましょう。
例えばごっこ遊びをしているときは、「りんごを3つください」と数字を使ったり、食事中に「トマトを3つ食べてね」と数えやすいものを口に出してみたり、個数と数を結びつける意識が大切です。
2.色を使った遊びを取り入れる
数字と同じように、色を理解してもらう場合にも、遊びの中にうまく取り入れるのがポイントです。
おすすめは色分けがある積み木遊びや、ぬりえ遊びです。特に色は子どもの好みがはっきり出る部分なので、好きな色を中心に教えていくとより理解のスピードが速くなるかもしれません。
またぬりえではなく、お絵描きなら図形の判別にも繋がります。どちらも正しく理解させるよりも、子どもが楽しみながら覚えられるように誘導しましょう。
少しずつ根気よく教えていけば、いつの間にか色と図形の認識ができるようになっています。焦らずゆっくり子どものペースで進めることが重要です。
3.言葉をたくさん使って会話する
3歳になるまでは話せる言葉が少なく、赤ちゃん言葉で話したり、簡単な単語で話したりする機会がほとんどですが、3歳を過ぎてからは徐々に難しい言葉も取り入れてみましょう。
大人同士で話すように難しい言葉を使うのではなく、簡単な日常会話レベルで話すのがポイントです。
子どもは外から取り入れた言葉や知識をどんどん吸収して自分の言葉にしていくので、言葉のレベルを上げていくと自然とその言葉が子どもに身についていきます。子どもの成長速度に合わせて取り入れてみてください。
合わせて読みたい
4.子どもと積極的にコミュニケーションをはかる
子どもの理解力を高めるために、特に大切なのが子どもとのコミュニケーションです。忙しい育児の中ではつい子どもの対応がおろそかになりますが、子どもは親の姿を見て育ちます。
普段からテレビやスマートフォンを見ながら子どもと話すようなことが多い、忙しいからと子どもとのコミュニケーションをないがしろにする、ということがあると、子どもも同じような行動をとりかねません。
わずかな時間でも子どもに対応する時間を作り、コミュニケ―ションを欠かさない努力が大切です。
.jpg&w=2048&q=75)
5.子どもの立場になって話す
先ほど、言葉をたくさん使って会話すると紹介しましたが、難しすぎる言葉は子どもが理解できません。大人同士、仕事で使うような難しい表現は避け、できるだけ短く区切るのがコツです。
3歳の時点では、まだ接続詞や助詞を使い始めた段階なので、子どもに合わせて一文ずつ短く区切ってみてください。
また早口にならず、ゆっくり話すのも大切です。できれば子どもの様子をうかがいながら、頷いたり返答があったり、反応を確かめながら話すとより理解が深まります。
6.理由を述べる叱り方に変える
2歳~3歳にかけてはイヤイヤ期、3歳~4歳にかけては反抗期が始まる時期です。イヤイヤ期は感情を言葉で表現しきれないことに対して癇癪を起こす行動を指し、反抗期は親の言っていることを理解しつつも、それを否定する行動をとるのが特徴です。
イヤイヤ期や反抗期の突入に伴って子どもを叱る回数が増えますが、頭ごなしに叱りつけてはいけません。
何がダメだったのか理由をしっかり伝え、「○○でしょ!」と威圧的になるのではなく「○○されて悲しかったよ」と伝えれば、感受性を高める行動につながります。
子どもも内心でモヤモヤしている感情があるので、まずは子どもの話をしっかり聞いて対応してみてください。
合わせて読みたい
3歳児の理解力に関するよくある質問
3歳児の理解力に関する相談でよくある質問をまとめました。(タップして回答内容を確認)
子どもとたくさん接することで理解力を高めよう
3歳になると、子どもは数が数えられるようになったり、色や形が認識できたり、物事に疑問を持ったりします。また、話す言葉の中に接続詞や助詞が加わり、コミュニケーション能力も発達します。
.jpg&w=2048&q=75)
子どもの理解力を高めるには、子どもとたくさんコミュニケーションをとるのが大切です。日常生活で数字を使ったり、子どもでもわかる言葉で話しかけたりすると、外から取り入れた言葉や知識をどんどん吸収して自分の言葉にして、自然と子どもに身についていきます。
特に3歳の時期は言葉・運動能力・理解力など成長が顕著になり、同時に反抗期も始まります。親の言っていることを理解しつつも否定する行動をとるようになりますが、頭ごなしに叱るのは避けましょう。ダメな理由やこうされて悲しかったといった気持ちを説明することで、より子どもの理解力を高められるでしょう。
合わせて読みたい
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #3歳 #理解力 #チェック #目安 #確認
.jpg&w=2048&q=75)
.jpg&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)




.png&w=256&q=75)

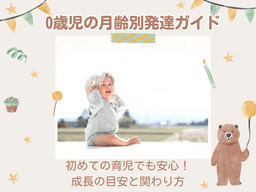












.png&w=256&q=75)







