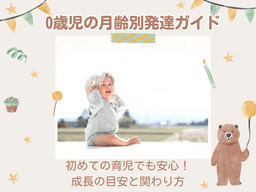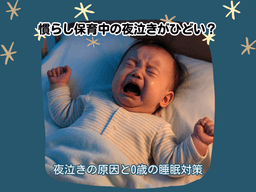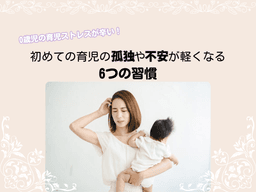新生児の体の大きさや特徴
産まれたばかりの新生児について
新生児期とは生後28日未満のことを言います。新生児の身体は個人差もありますが、身長は約50cm、体重は約3,000g程度が男女ともに平均的といわれています。
体重や赤ちゃんの体調については、特にお医者さんから指摘がない限り心配しなくて大丈夫です。赤ちゃんは「生理的体重減少」という新生児特有の現象で生後3日目くらいからは体重が減りますが、すぐに回復するので心配せずに見守りましょう。それでも心配なときは担当のお医者さんに相談すると安心です。
新生児期の赤ちゃんは1日の半分以上を眠って過ごします。昼と夜の区別もまだついていないため、お腹が空いたら起きる、おむつが汚れたら起きる、といった具合で、「起きては眠る」を繰り返す毎日です。

授乳の間隔も個人差がありますが、母乳でもミルクの場合でも3時間から4時間程度が平均的です。母乳の場合は、うまく飲めずにお腹が満たされる前に疲れて眠ってしまう、母乳が十分に出ていないなどの理由でお腹が空くのが早くなり、授乳の間隔が短くなってしまう事があります。あまりに授乳の間隔が短い場合はちゃんと飲めているか確認してみるとよいですね。
いっぽうミルクの場合は母乳に比べて腹持ちがよいといわれているので、授乳の間隔は平均より少し空くようです。
新生児期は寝ている時間がとても長いよ。ママもこの時期に産後の体を休めるようにするといいね♪

新生児の育て方について
新生児の視力
赤ちゃんが哺乳瓶や母乳を見ても反応がなく不安になるママも多いようですが、心配はいりません。新生児の視界はぼんやりとしか見えておらず、よく見える距離は30cmくらいといわれています。
また、認識できる色にも限りがあり、白、黒、グレーの三色だけです。目を動かすような仕草を見かけることもあるかと思いますが、それは音に反応しているのではないかと考えられています。
今はぼんやりとしか見えていなくても、成長とともに新生児の視力は発達していきます。お腹の中にいるときからママの声はちゃんと分かっているので、赤ちゃんが起きているときには顔を近づけて話しかけてあげましょう。
おむつの替え方は?
新生児用おむつはメーカーや種類もたくさんありますので、好みにあったものを用意してください。
まずは赤ちゃんを仰向けに寝かせて、おしりの下に新しいおむつを敷きます。このとき、新しいおむつはしっかり広げてから敷いてください。
汚れたおむつを外し、うんちのときと同じようにおしっこのときもきちんと拭いてあげましょう。男の子の場合はしわの間に注意して拭いてあげてください。女の子の場合は割れ目もしっかり拭いてあげましょう。拭き終わったら汚れたおむつを抜き取ります。
新しいおむつが敷いてあるので、位置を確認して新しいおむつをつけてください。おむつ替えに使う物などをまとめておくと、替えるときに慌てずにできます。
合わせて読みたい
新生児の生活とお世話
母乳は可能な限り与えよう
昔から【母乳は欲しがるだけあげてもよい】といわれてきましたが、そのとおり、母乳は赤ちゃんが欲しがるだけあげましょう。母乳を飲み過ぎて赤ちゃんが太った気がすると心配するママも多いですが、問題ありません。
哺乳瓶からミルクを飲むよりも母乳は吸う力が必要なので楽には飲めません。そのため飲み過ぎる前に疲れて離してしまうようです。
また、母乳は授乳開始から味や成分が変化し水分が多くなり満足しておっぱいを離すので、飲み過ぎにはならないといわれています。間隔を空けず何度もおっぱいを欲しがる場合は赤ちゃんの飲み方を確認してみるとよいでしょう。
授乳は赤ちゃんとのスキンシップ、赤ちゃんとの時間を大切に過ごせるとよいですね。
合わせて読みたい
うまく寝かしつける方法は?
新生児期の赤ちゃんは1日の半分以上を眠って過ごします。まだ昼と夜の区別もついていないため、時間に関係なく起きては眠る生活を繰り返します。授乳の間隔は3~4時間おきなので深夜に起きてしまうのは仕方がないことですが、新生児のうちから生活リズムを整える準備をしましょう。

夜は電気を暗くして、暗くなったら眠る時間だということを習慣づけていきましょう。赤ちゃんの胸を優しくトントンしてあげるのもおすすめです。
寝る時間を決めて、オルゴールをかけるなど寝るときの合図みたいなものがあると分かりやすいですね。最初はうまくいかないかもしれませんが、習慣化することで赤ちゃんも少しずつ覚えていくので焦らず見守りましょう。
合わせて読みたい
新生児期における落ち着いた環境づくり
新生児のお部屋づくり
産まれたばかりの赤ちゃんは体温調節が未熟なので、快適に過ごせる室温や湿度になるよう心がけます。春~夏は24~28度、秋~冬は20~23度、室温は50~60%が理想です。
エアコンを使用する際はエアコンの風が直接赤ちゃんに当たらない場所に、ベビーベッドやお布団を置きましょう。
上にお兄ちゃんお姉ちゃんがいたりペットと一緒に過ごすことが多い場合は、ベビーベッドが安心です。
また、ねんねスペースのまわりには落下の危険があるものは置かないようにしましょう。特に頭や顔のまわりにクッションやぬいぐるみなどがあると、何かの拍子で赤ちゃんの顔に倒れるととても危険です。
新生児の外出について
新生児のお出かけは、その家庭の環境や生活リズムによって様々だと思います。上に子どもがいるとなおさらですよね。とはいえ、可能であれば生後1カ月未満の赤ちゃんの外出はなるべく避けた方がよいでしょう。産まれたばかりの赤ちゃんは体温の調節がうまくできないため、外と室内の気温差や外気も大きな負担になってしまいます。
新生児は免疫力が低く病原菌やウイルスなどにも感染しやすいことも、外出を避けた方がよい大きな理由になっています。
新生児期の赤ちゃんはまだ外の世界に出たばかりなので、環境に慣れるためにはもう少し時間が必要です。
どうしても外出しないといけない時もあると思いますが、短時間で済むように工夫するなど注意が必要です。
赤ちゃんとの初めての外出が1ヶ月健診という方も多いです。1ヶ月健診では、発育、発達をチェックしてもらいます。気になる事があれば事前にメモでまとめておいたり、授乳時間や回数、飲むのに費やした時間などを記録し、健診の際に見てもらうとよいでしょう。

ママも息抜きしながら子育てを
初めての子育てだとわからないことも多く不安になりますが、授乳、おむつ替え、沐浴など基本的なお世話をしているうちに赤ちゃんはどんどん成長していきます。そして赤ちゃんについて知っていることが増えると、子育てがだんだんと楽しくなっていきます。
赤ちゃんが新生児のうちは、ママも産後疲れで体力的にも精神的にも余裕がないものです。頼れる相手がいるならばどんどん頼ってしまいましょう。特にパパにはできる限り子育てに積極的に関わってもらいましょう。
乳児から幼児への成長ぶりはめざましいものです。あとから赤ちゃん時代をもっと楽しむべきだったと後悔することがないよう、子育てを楽しんでくださいね。
【まとめ】親と子のスキンシップを何よりも大切にしよう
新生児は「0ヶ月の乳児」で、その後1歳になるまで年齢ではなく「1ヶ月児」というように月齢で数えられます。
乳児期は一生のうちで一番成長が著しく、体の発育だけでなく運動発達も精神発達も月単位でおおきく変化します。生まれた時は手足と首、顔を動かすぐらいしかできなかった赤ちゃんが、寝返り、お座り、ハイハイ、つかまり立ちと、日一日と成長していきます。
パパ・ママは積極的にスキンシップをとる事を心がけましょう。なぜなら、この時期に赤ちゃんの視覚、嗅覚、聴覚、触覚、味覚といった五感が、周囲の大人たちからの刺激で発達していくからなのです。ママはもちろん、パパも赤ちゃんと関わりをもってあげることが何よりも大切です。

最初は「快」と「不快」しか感じず、泣くことでしか自分の感情を表現できなかった赤ちゃんが、 3〜4ヶ月ぐらいにはあやされると笑うようになり、 ママやパパの姿が見えなくなると不安を感じて泣いたり、寂しいという感情を抱いたりするように。
感情が芽生え始めたこの時期の赤ちゃんに必要なのは、自分を愛おしく思って世話をしてくれる大人の存在です。パパ・ママは特に、赤ちゃんの感情を読み取ることが重要です。
そうすると、特定の大人への信頼感や安心感が芽生える「愛着」が形成さ、心も育まれていきます。そして、赤ちゃんの「あれは何だろう」という好奇心が芽生え、それが探究心へと繋がっていくのです。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児
.jpg&w=2048&q=75)






.png&w=256&q=75)