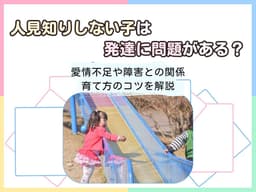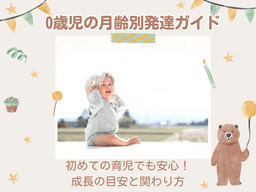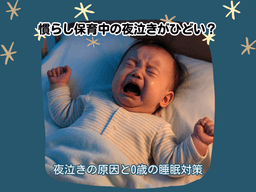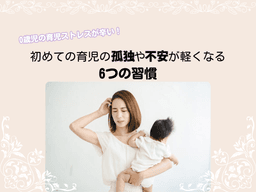ようやく始まった人見知りの研究
日本赤ちゃん学会が設立されたのが2001年、子ども学会は2003年というように、21世紀に入ってようやく脳科学や生理学、言語発達、行動発達、心の発達や進化の道筋など、様々な分野の研究者が自身の専門分野だけではなく、多彩な分野からの赤ちゃん研究の報告を共有しあう土壌ができあがってきました。
東京大学・大学院総合文化研究科の岡ノ谷一夫博士や、京都大学・大学院教育学研究科の明和政子博士らが2008年から2013年にかけて実施された共同研究は、本格的な「乳児の人見知りのメカニズム」を解析しようする試みとしては我が国で初めてのものだと思われます。
これまで人見知りは、単に他人を怖がっているからだと考えられてきましたが、中には快と不快の感情の混在を表す赤ちゃんもおり、「怖がり」だけでは説明がつかず、相手の何を怖がっているのかについても調べられていませんでした。
この研究では、相手に近づきたい「接近行動」と相手から離れたい「回避行動」を指標に人見知りとの関係を調べました。この2つは互いに相反する心理行動であり、最も本質的な行動としてあらゆる動物に見られ、人間の本性の1つと言えます。
この互いに相反する行動を支えるそれぞれの気質を「接近」および「怖がり」と名付けた場合、人見知りの強い赤ちゃんは、両方の気質が共に平均よりも強いことが分かりました。それまでも学童期の子どもを対象とした心理学研究では、すでに「人見知りとは接近と回避の葛藤状態である」と報告されていましたが、この研究によって、1歳前の赤ちゃんの人見知りも「葛藤」を抱えた状態で現れるということが初めて示唆されたといえます。

「近づきたい…でも怖い」は知能発達の証
研究によって人見知りのメカニズムの一端が解明されたからと言って、それを即、遺伝による個人差だと決めつけるのは早計です。また、例え生まれつきの個人差があったとしても、その気質がそのまま学童期や成人後まで変化しないわけではありません。
乳児期最初の人見知りは、0歳7ヵ月頃に訪れる

乳児期最初の人見知りは、大体0歳7ヵ月~1歳の誕生日頃までに訪れます。この発現の時期も赤ちゃんによって実に様々です。それが遺伝によるものなのか、生まれてからそれまでの周辺環境や育児方法の違いによるものなのかを解明する研究はまだなされていません。
しかし、言葉を豊富に耳にする機会のあった赤ちゃんが話し出すのが早く、適切な運動をする機会を多く与えられた赤ちゃんが早くに歩き出すように、人見知りの能力もそれまでの生活環境によって発現の時期が早まると推測するのが妥当です。
何歳何ヵ月だから人見知りをする、というような実際の月齢で判断するのではなく、「社会性や知能の発達がおよそ0歳7ヵ月レベルに達すると人見知りすることが出来るようになる」と考えるべきだと思います。
合わせて読みたい
人見知りの赤ちゃんへ接する時の心構え
一例として、生まれてすぐは反射だけで動く魚類の脳、自分の意志で動くことを覚えたら両生類、四肢が連動する交差パターンが完成したら爬虫類、という発達イメージがあげられます。
そして、「接近」と「回避」の葛藤を感じられるようになったら鳥類に発達するイメージです。決して大脳生理学的に鳥の発達状態に近いとかそういうことが解明されているわけではなく、人見知りの時期の赤ちゃんの相手をする時には鳥の相手をするような気持ちで接すると、赤ちゃんの能力を超えた過剰な要求をしたり、発達の面を心配し過ぎたりすることなく、穏やかな気持ちでお世話をしやすくなります。
魚類から爬虫類までは餌をくれる人を認識することはあっても、犬や猫のように懐いてくれることはありません。恐怖や危険を感じたら即座に逃げるだけです。しかし哺乳類や鳥類は愛情込めてお世話を続けると、他の人に対する時とは明らかに違った態度で懐いてくれるものです。そこには明らかに特別な感情を抱く特定の相手に近づこうとする意志のようなものがあるようです。
「近づきたい」という感情と「怖い」という感情の葛藤という複雑な心理状態を感じ取れるところまで知能が育ち、次は「この人は怖くない」と感じる経験を少しずつ時間をかけて与えてあげればよいのです。
人見知りをする段階まで成長したのだと、先ずはお子さまの成長を喜び、そして何をしてあげたら良いのかを考えると良いんだね♪

「怖い」と感じる能力はとても重要
恐怖感は危険を事前に察知し、自分の身を守るために絶対に必要な感覚です。よくつり橋を一人で渡れない、木登りが出来ない子どもに対して「臆病」「勇気がない」「怖がりだ」と指摘する人もいます。しかしこれは、そういった精神論で片付けてしまうのは乱暴な話です。
恐怖感は脳が発するシグナル
つり橋を渡れない子は恐怖を感じ、渡れる子は恐怖を感じていません。その違いは、渡れる子にはつり橋で少々バランスを崩したとしても、自分自身ですぐに体をコントロールしてバランスを取り戻せる身体能力が備わっているからなのです。その子にとってはさほどの危険ではないから恐怖を感じないのです。怖くて渡れない子は、もしつり橋の上でバランスを崩した時、自分一人では姿勢を立て直せない場合がほとんどです。ですから脳は恐怖感というシグナルで危険を警告しているのです。
人間は年を重ねると次第に体力面で筋力やバランス感覚の衰えを感じ、たとえ階段を数段降りるだけでも恐怖を感じるようになることもあります。丸木橋なども同じです。細い川に丸木一本がそのまま橋としてかけられていて、何度も渡っているので恐怖を感じるはずなどないのに、落ちたくない・濡れたくないと考えると、不思議と一歩を踏み出せなくなります。
私たちが「今まで簡単にできたことができなくなっていく」という経験をするのとは逆に、子どもは「今までできなかったことがこれから簡単にできるようになっていく」という経験をしているのです。どんなことにおいても、簡単にできてしまう時にはできない人の気持ちを真の意味では理解できないものです。
ですから、恐怖を感じている時に、他の人間が「怖くないよ」「勇気を出して」「大丈夫だから」などと言うのは、決してベターな対応ではないと考えます。怖くないのはそう言っている人にとっての感覚であって、怖いと感じている子どもは実際に怖いのです。湧きあがってくる感情というのは理屈や論理だけではそう簡単にコントロールできないのは大人でも同じこと、ましてや小さい子どもには無理なことです。

恐怖感の克服には小さな成功体験が重要
つり橋を渡れない子どもに大人がすべき教育は「勇気を出せ」というものではなく、つり橋から落ちることのない身体運動能力を養ってあげることでしょう。バランス感覚を育てる運動や、崩れた姿勢を立て直す反射やそのために必要な筋肉、身体の必要な部位を動かすための脳や神経の回路を育ててあげることが最も重要であり、「怖がりを治す」ことを目的とすべきではないと考えます。
適切な運動環境を与え、必要な筋肉とバランス感覚を育てる平地での遊びやマッサージを行い、低い平均台から練習を始めていけば、どの子も確実につり橋を渡る能力を獲得します。高さに対する恐怖心も身体能力の高まりに合わせて少しずつ高度を上げていけば次第に薄らぎます。脳がその程度の高さは自分にとって危険ではない、危険を回避する能力を自分は有している、と記憶するからです。
このように適切なアプローチで教育された子どもは、「恐怖感は自分の心で乗り越えられるもの」、つまり「恐怖感の克服」という成功体験を小さな事柄でたくさん経験します。すると3歳以降、前頭葉前野がより発達し、理性的に自分の意志で恐怖という感情をコントロールできるようになるのです。

人見知りの能力によって、恐怖感の克服力が育つ
「恐怖」を感じるのは、身の危険を感じる時です。例えば非常に高い場所や速すぎるスピード、鋭利な刃物、押しつぶされそうなほど重くて大きいものなど、人間の身体能力を超えた巨大なパワーに対して、人は本能的な恐怖を感じます。
また、水の中など呼吸の出来ない場所や、燃え盛る炎のように生存が不可能な状況に対しても恐怖心が生じます。さらに、対動物や対人でも、恐怖を感じるシステムが生まれつき脳の中に組み込まれているようです。食物連鎖の存在や生物の進化の歴史を考えたら当然かもしれません。幼い子どもに恐怖感・恐怖心を克服させるためのアプローチは多くの場合、身体能力面・運動面が考えられます。
しかし、そのように子どもが命の危険を感じるような身体面の恐怖を与えずとも、対人における恐怖心を上手く活用すれば恐怖の克服経験を豊富に与えてあげることは容易です。赤ちゃんは自分にとって友好的・好意的な人物に対しても小さな恐怖を感じてくれるのですから、恐怖感克服の学びとして、これほど安全なアプローチはないでしょう。
【まとめ】赤ちゃんの人見知りは、成長の証
乳幼児期最初の人見知りは、だいたい0歳7ヵ月頃に始まります。
それは「近づきたい」という感情と「怖い」という感情の葛藤が起こす、知能の発達ゆえの現象です。初めて会った人に人見知りするようになった時、ママ・パパはちょっとがっかりしたりしがちですが、むしろ赤ちゃんの成長を喜んであげる気持ちでいることが大切です。
赤ちゃんが自分のこころに芽生えた「恐怖心」の感情を乗り越えていく第一歩なのです。
赤ちゃんの成長の過程を知って、優しく成長を見守ってあげましょう。

#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児

.webp&w=256&q=75)