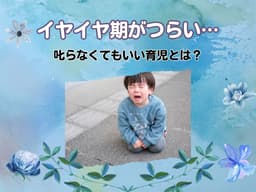子どもの運動神経の発達は、一歩一歩段階を踏むことが大切
コラムNo.132「子どもの運動神経を飛躍的に伸ばすには?~実践編①:ぶら下がりから直立歩行まで~」に引き続き、子どもをより高度な運動へ導く、具体的プログラムをご紹介します。前回までのプログラムにきちんと到達できるようになってから取り組みましょう。
まだそのレベルまで到達していない子どものお父さんお母さんも、この先どのような活動に進むのかを事前に知り、計画しておくことがとても重要です。そして、子どもが何ヵ月後にその目標に到達するのか、具体的な目標、希望の目安をノートなどに書きこんでみてくださいね。
より高度な運動へ
前庭の刺激をより早く脳に届ける回路、深い呼吸を支える心肺機能、手を手として使う機能が育ってきたら、こちらのプログラムに入りましょう。
.jpg&w=2048&q=75)
1.上り坂、下り坂を歩かせる
まだ街中のなめらかな舗装路がよいでしょう。地面のでこぼこが少ないので子どもが足を高くあげずとも上手に歩けるのです。足を高くあげなければならない環境はより高度なバランス能力を必要とします。今はノンストップで歩ける能力を育てることが先決です。
2.横転(いもむしゴロゴロ)・前転・平均台かヒモの上を歩かせる
お散歩コースを工夫しましょう。横転・前転・平均台もしくはヒモ(2m50cm)の上を歩くのはそれぞれ5分程度。子どもが飽きない時間にしてください。
時間:
歩くプログラムは階段や坂道、普通の平地を組み合わせて1日20~30分。
目標:
歩きやすい平地をノンストップで800mを18分以内に歩けること。横転・前転・平均台(ヒモ)歩きを保護者のサポート無しに、子どもが一人でできることです。
無理をしない範囲で、お子さんの成長に合わせて取り組んでみましょう!

走る能力を育てる
ベビーパークに通う1歳4ヵ月~3歳の子どものお母さんの多くが「レッスン中に子どもが走って困る」と嘆かれますが、この時期は「たっぷりと走らせるべき時期」なのです! 走ることこそが最大のレッスンです。子どもは確実に走れるようになり、歩くよりも走る方が好きになってきます。体で風を切るようなスピード感、足で地面を蹴る時の一瞬体が宙に浮く感覚などが混じり合って、何にも代えられない心地よさを感じるのです。
ですから子どもは走るだけで微笑み、声を立てて笑い、嬉しそうに叫ぶのです。
.jpg&w=2048&q=75)
なぜ子どもの体は走ることを求めているのでしょう。それは「走る事で大脳皮質が成長するから」です。また「呼吸器系の機能を格段に向上させるから」です。走りたい時には走らせて、走っていない時に他の教育を与えましょう。
毎日計画的に「走る機会」を与える
両親が一緒に走ってあげることがベストですが、そこは家庭で自由に無理なく取り組んでください。最初は小走りで十分です。途中で歩いてもよいでしょう。距離も少しずつ増やしてください。
継続のコツは、毎日「同じコース」を選ぶことです。最初は子どもは「探究反射」を発揮して、周囲のあらゆるものに興味を持ち、ひんぱんに立ち止まるでしょう。大人が20分で歩ける距離を散歩するのにも2時間はかかります。
しかし、毎日そうやって探究反射を発揮し続けているうちに、同じコースにあるもののほとんどを調べ終わってしまったら、今度は歩くこと・走ることに専念できるようになります。気分転換のためにコースを替えようなどと思ったら、また子どもの足は観察のために止まってしまうことでしょう。
走ることを遊びに取り込む
そして、走ることをなるべく「遊び」に取りこみましょう。電柱を目標にして競争したり、鬼ごっこをしたり、両親が先に何十メートルか先に行っておいて「ゴールはお母さんの抱っこ」なんて工夫をしてみたりしましょう。
また、長距離を走るためのペース作りを習得させるには「お父さんの影の中からはみ出さないように走ること」というゲームをするのも効果的です。お父さんが一定のペースで走り、お父さんの影からはみ出ないように走るというゲームをするのも、子どもの走る能力を効率よく育てます。
.jpg&w=2048&q=75)
ランニングとその他の運動を組み合わせる
子どもが走ることに慣れてきたら、今度はランニングとその他の運動遊びを組み合わせていきましょう。
次のリストの中からやってみたいもの、継続できそうなものを10個選んでください。それを毎日1回ずつおこないます。
- 物を両手にもって歩く(食事の配膳などでも大丈夫です)
- 横転(いもむしゴロゴロ)
- 前転(でんぐり返し)
- 後転(後ろでんぐり返し)
- シーソー
- 階段の上り下り
- 高さが違うところを歩く(塀の上など)
- よじ登り(梯子・塀・木登りなど)
- 跳び降り
- でこぼこの地面を歩く(山道など舗装されていない道)
- 幅跳び
- 高飛び
- 片足跳び(ケンケン遊び)
- 平均台
- 縄跳び
- 腹筋運動
- 屋外のうんてい
- しゃがんだ姿勢から跳び上がる
- ピルエット(バレリーナのようにクルクル回る)
- 後ろ向きや横向きに歩く
- ブランコ
- 石蹴り
- ターザンロープ
- ハイキング
- いろいろな高さの障害物を乗り越えたり、くぐったりしながら走る(ジャングルジムなどを活用)
時間:
ランニング30分とその他の運動遊び30分の計1時間です。
目標:
子どもがノンストップで5km走れるようになること。これができるようになったら「20メートルの全力疾走」から、全力疾走の練習を始めましょう。最終的には「50メートルダッシュ・10本」までもっていきます。
注意事項
※ノンストップで5km走ることは一朝一夕ではできません。両親も一緒になって目標達成まで「2年間」かけるつもりで取り組んでください。
※走り始めたばかりの頃の子どもには「長距離走」も「全力疾走」も区別がつきません。ですから幼稚園児や小学校低学年の運動会の「かけっこ」は、なんともお粗末になっているのが現状です。しかし「規則的な優れた呼吸」を身につけた子どもならば、幼い頃からの「本格的な全力疾走」が可能になるのです。
.jpg&w=2048&q=75)
※大人の不用意な「言葉」が子どもの心を弱くします。お母さんが「寒いわね~、凍えそうだわ」と言えば、子どもはそれまで寒いとも思っていなかったのに、急に寒がって部屋に戻りたがります。お父さんが「疲れた・・・足が痛いな」と言えば、子どもも「疲れた」を連発するようになります。「努力・根気」を折るような「言葉」の見本を子どもに聞かせないように、十分ご注意ください。
お子さんの「走りたい!」気持ちに寄り添って少しずつチャレンジしてみましょう♪

「走るプログラム」の目標レベルアップ表
走ることについての成長の段階を「レベルアップ表」としてまとめていますので、参考にしながら毎日子どもと遊んでみてください。
第1段階(ノンストップで100メートル走れるようにする)
- 1回10m(10m走ったら休んで、また反対に10m走る。徐々に回数を増やし10mを20回走れるようになったら次のレベルに進む)
- 1回12mを15回
- 1回15mを12回
- 1回20mを10回
- 1回25mを8回
- 1回30mを6回
- 1回40mを4回
- 1回60mを3回
- 1回100mを2回
第2段階(ノンストップで1.5km走れるようにする)
- 1日1.5km歩く間に、100mのランニングを4回入れる。
- 1.5kmの間に走る距離を少しずつ増やし、150mを4回走れるようにする。
- 1.5kmの間に180mを4回走れるようにする。
- 1.5kmの間に400mを2回走れるようにする。
- 1.5kmの間に800mを1回走れるようにする。
- 800m連続で走れるようになったら1.5kmの間に毎日20mずつ走る量を増やしていきます。
- 走る距離を伸ばしつつ、歩く距離を減らして、最終的に1.5kmすべて走れるようにしましょう。
第3段階(ノンストップで5km走れるようにする)
1.5km走れるようになったら、毎日少しずつ走る距離を増やしていきます。1.5km走れるようになった時期が3歳だったら、1ヵ月かけて「100m~200m」増やしましょう。1日に5m程度伸ばしてあげればいいのです。4歳だったら、1ヵ月かけて「200m~300m」増やしていきます。1日10m程度ずつ徐々に増やしていくのです。
4歳~6歳の間に「5kmを40分間で走れる」というのが、最終的な目標です。
まとめ:毎日着実に子どもと一緒に一歩一歩楽しもう
今回も、どの段階がどの年齢が対象なのか、あえて解説しておりません。子どもの過去の経験量に合わせて、子どもにぴったりと合ったプログラムを探してください。
よく「理想と現実のギャップに悩む」という方がいます。何も悩むことなどないのです。「理想」は「目標」です。「現実」は「今すぐにできること」です。目標に向かう為ためには、具体的に何をすればいいのか、「今すぐにできること」の中に少しずつ加えていけばいいのです。
両親が「明確な目標」を抱き、日々そこに「近づく努力」を怠らなければ、確実に一歩一歩目標への距離は縮まっていきます。
.jpg&w=2048&q=75)
その「経過」をおおいに楽しみましょう! 悩みも苦労もすべてひっくるめて楽しむこと、不安に思わないこと、つらいと思わないこと、すべてを楽しもうとすることこそが成功の鍵です。
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #子ども #走る #運動能力 #伸ばす #コツ
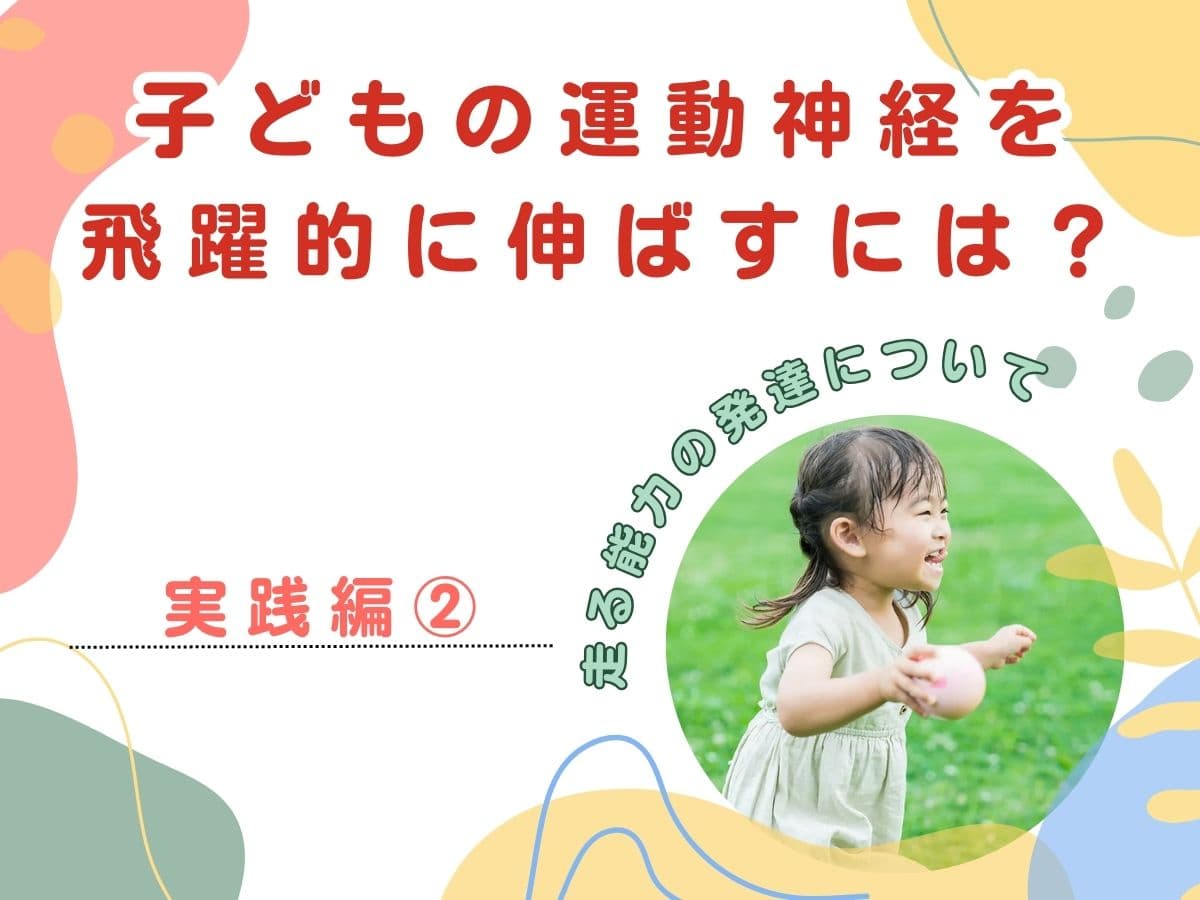
.jpg&w=256&q=75)


.jpg&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)



.png&w=256&q=75)