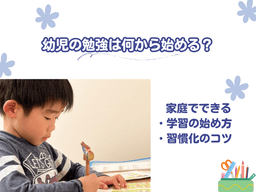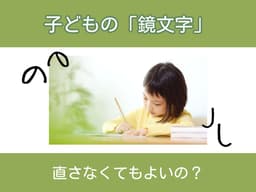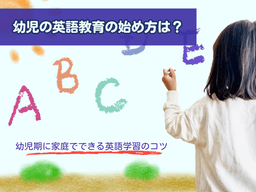保育園ではどんな勉強をしている?

保育園では、いわゆる「勉強の時間」が明確に設けられていることは少ないものの、日常の中でさまざまな学びの機会が散りばめられています。
文字や数字の知識よりも、まずは社会性や自立心、感性を育てることが重視されています。
また、最近では先進的なカリキュラムを取り入れている園も増えており、遊びを通じた学びの可能性が広がっています。
ここでは、保育園でどのような学びが行われているのかを具体的に紹介していきます。
遊びを通じて育つ非認知能力
保育園の活動の多くは「遊び」を中心に構成されていますが、この遊びの中には子どもの将来に重要な力を育てる要素が詰まっています。
特に注目されているのが「非認知能力」です。これは、自己肯定感や協調性、やり抜く力、好奇心など、学力テストなどでは測れない能力を指します。
例えば、ごっこ遊びを通じて役割分担や他者とのコミュニケーションを学び、砂場遊びで集中力や想像力を育てます。
自ら考え行動する経験が、非認知能力の発達につながるのです。これらは、後々の学習意欲や人間関係構築力の基盤になります。
保育園の生活の中で自然に学ぶ言葉と数
保育園の一日は、着替え、食事、片づけといった生活の積み重ねです。
こうした日常の中で、子どもたちは言葉や数の感覚を自然に身につけています。
例えば、「おやつはひとり3つね」と先生が声をかければ、子どもは数を数える機会になります。
また「今日は雨が降っているから、お散歩はお休みね」と先生が話すことで、子どもたちは天候と行動の関係を理解していきます。
学習を“教え込む”のではなく、“気づかせる”ことで興味が育つのです。
STEAMや知育活動など先進的な取り組みも広がる
最近の保育園では、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学を横断的に学び、創造的思考力や問題解決力を育てる教育)や知育教材を取り入れた先進的な学びに取り組む園も増えています。
特に私立や認可外の保育施設では、英語やプログラミング、リトミック、体操、ピアノといった多彩な活動がカリキュラムに含まれている園もあります。
これらの活動は、子どもの好奇心を刺激し、多面的な能力を育てることが目的です。
大人は勉強というと机に向かい教科書とノートと参考書・・・というイメージを持つけれど、幼児は違うのかな?

保育園児は家庭での勉強が必要?

保育園では生活の中に自然な学びが組み込まれていますが、それだけで十分なのか不安に感じる保護者もいるかもしれません。
実際、小学校入学を見据えたときに「もう少し家庭でも学びを取り入れたい」と考える保護者の声も聞かれます。
ここでは、家庭での学びの重要性や親の関わり方、学習環境の整え方について具体的な方法とともにご紹介します。
保育園だけでは補いきれない「学びの土台」
保育園のカリキュラムは「生活や遊びを通しての学び」が基本ですが、子どもによって言葉や数字への関心を示す時期やきっかけはさまざまです。
また、読み書きや計算などの基礎的な力は、保育園では「本人が興味を持ったときに教える」という方針の園もあります。
そのため、園での経験を補うように、家庭でも楽しく学びに触れる機会を持つことが効果的です。
家庭での会話や遊び、読み聞かせなどを通じて「知る楽しさ」「できた喜び」を感じられるような環境を作ることで、自然と学習意欲も育ちます。
親子の関わりが学びの意欲を育てる
子どもの学びにおいて最も重要なのは、親との信頼関係と日々の関わりです。
親が子どもの話に耳を傾け、興味を持ったことに一緒になって取り組むことで、子どもは「知りたい」「やってみたい」という気持ちを持つようになります。
例えば、「この前の公園で見た花、何ていう名前かな?」「一緒に調べてみようか」といった声かけをすることで、調べること=楽しい体験として定着します。
学びは、日常の中に無限に広がっているのです。
無理に教えるのではなく環境づくりがカギ
家庭で勉強をする際に気をつけたいのは、「無理に教え込む」のではなく「学びやすい環境を整える」ことです。
保育園から帰ってきて疲れているときにドリルをさせるよりも、絵本を読んだり一緒に遊んだりする中で自然と学びを得る方が効果的です。
また、子どもが興味を持ったタイミングで学びにつながるおもちゃや教材をそっと用意するだけでも十分です。
子どものペースに寄り添うことが、学習意欲を育てる第一歩になります。
具体的にどんなことをすれば、子どもの能力って伸びるんだろう?

保育園児の学力を高める方法
幼児期は、知識を詰め込むよりも「学ぶって楽しい」と感じる経験を積み重ねることが何より大切です。
家庭でできることは、特別な教材や難しい知識よりも、身近な体験や親子のふれあいを通じて学びの土台を育てることが中心です。
ここでは、保育園児の学力を無理なく伸ばすための実践的な方法を紹介します。
絵本の読み聞かせで語彙力を伸ばす
絵本の読み聞かせは、語彙力の向上に最も効果的な方法のひとつです。
さまざまな言葉に触れることで、言語の理解力だけでなく表現力や感情の理解も深まります。
また、絵本の世界を通じて好奇心や想像力も育ちます。親子で物語の続きを考えたり、登場人物の気持ちを話し合ったりすることで、言葉の力だけでなく思考力や共感力も高めることができます。
1日1冊でもよいので、毎日続けることがポイントです。
日常の中で数や言葉にふれる機会を増やす
日々の生活の中にも、数や言葉に触れるチャンスはたくさんあります。
買い物の時に「じゃがいもを3つ取ってくれる?」と声をかけたり、料理中に「大さじ2杯」などの分量を一緒に数えたりするだけでも、数の感覚がだんだん身についていきます。
また、洗濯物をたたみながら「シャツとズボン、どっちが多いかな?」といった分類あそびも有効です。
さらに、「“あ”で始まる食べもの、なんだろう?」などの言葉探しあそびをするのもおすすめです。
子どもが楽しめる声かけや工夫をすることで、遊びの中で自然に言葉や数に親しむようになります。
学びの楽しさを感じられる遊びを取り入れる
保育園児にとって、「遊び」は最も自然な学びの形です。
パズルや積み木、ブロック遊びなどは、手先の器用さや空間認識力、論理的思考を養う助けになります。
また、簡単なボードゲームやカードゲームを通じて、順番を守る、ルールを理解する、相手の立場を考えるといった社会性も育まれます。
親子で一緒に楽しむことが、学びの土台を育てる一番の近道です。
知育教室を活用して学びの楽しさを広げる
家庭での取り組みだけでは不安な方は、専門的な知育教室の活用もおすすめです。
トイズアカデミージュニアでは、3〜6歳児を対象に、発達段階に応じた遊びと学びのプログラムが用意されています。
子どもが楽しみながら学べる知育教材を活用し、非認知能力や好奇心、自発性を重視した教育を行っているのが特徴です。
幼児期に学びの楽しさを知り、考える力を高めることで自身が生まれ家庭での学びの質を高める手助けになります。
幼稚園と保育園の違い
保育園と幼稚園は、どちらも子どもが日中を過ごし、成長を支える場という共通点はありますが、その目的や教育方針には明確な違いがあります。
特に「勉強」に対する考え方やカリキュラムの違いによって、子どもがどのような環境・方法で学びにふれるかが変わってきます。
ここでは、教育方針・管轄省庁・生活の流れ・学びの内容などの面から、保育園と幼稚園の違いを整理して解説します。
管轄と目的の違い
保育園は厚生労働省のもと「児童福祉法」に基づいた施設です。
働く保護者を支援する目的が強く、0歳から預けられる場合もあり、保育士が生活や遊びを通じて子どもの発達をサポートしています。
一方、幼稚園は文部科学省が所管する「学校教育法」に基づいた教育機関で、3歳以上の子どもが対象です。
小学校の準備段階としての役割を持ち、先生は「幼稚園教諭」という教育者です。
生活リズムと時間の違い
保育園は1日8時間以上預かる長時間保育が一般的です。
子どもが園で過ごす時間が長いため、生活全体を通じて学びを促すスタイルが多くなります。
幼稚園の保育時間は1日4〜5時間程度です。降園後は家庭で過ごしたり、課外活動や習い事に充てたりするケースが多く、家庭の関与が比較的大きくなります。
勉強の方針の違い
一般的に、幼稚園は「読み書き・計算」などの学習的要素がカリキュラムに含まれやすく、保育園では「遊びや生活の中での学び」が中心です。
ただし、最近では保育園でも知育的要素を取り入れる園が増えており、両者の差は以前よりも小さくなってきています。
また、子どもの成長に最も大きな影響を与えるのは園そのものよりも家庭環境や親の関わり方だと言われています。
合わせて読みたい
保育園児の勉強についてよくある質問

保育園児の「勉強」については、何をどこまで取り入れればよいのか迷う保護者の方も少なくありません。
ここでは、よくある質問をもとに、保育園児の勉強について専門的な視点も踏まえたアドバイスをお伝えします。
Q.保育園のうちにひらがなや数字の勉強はするべき?
A.小学校入学前にすべてを教える必要はありませんが、日常の中でひらがなや数字に触れる機会は大切です。
書き取りではなく、名前を書いたり歌に合わせて数えたりするなど、遊び感覚で取り入れるのがポイントです。
Q.保育園児が勉強に興味を持つにはどうしたらいい?
A. 「勉強」と構えず、遊びの中で楽しく学べる工夫をするのが効果的です。
例えば、かるたやお買い物ごっこなど、身近な遊びを通じて自然に興味を引き出しましょう。
Q.保育園児に知育教室は早すぎない?
A. 脳の約9割は6歳までに発達するといわれており、この時期の刺激はとても重要です。
子どもの発達や性格に合っていれば、知育教室はよい経験になります。無理のない内容で楽しめる教室を選び、まずは体験から始めてみましょう。
まとめ
保育園児にとって「勉強」とは、単に机に向かって文字や数字を覚えることではなく、日々の生活や遊びを通じて多様な力を育む過程です。
特に非認知能力のような目には見えにくい力は、将来の学習や人間関係にも大きく影響します。
そのうえで、家庭での学びの環境や親の関わり方は、子どもの学力や学習習慣の土台を育むうえで大切な要素となります。
絵本の読み聞かせや日常生活での数・言葉への働きかけ、そして子どもが学びを楽しいと感じられる工夫を積み重ねていくことが大切です。
さらに、もし専門的なサポートが必要だと感じたときは、トイズアカデミージュニアにお気軽にお問い合わせください。
お子さまの発達段階に合わせた知育活動を通じて、学びの幅と質を高めるお手伝いをいたします。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #保育園 #保育園児 #勉強 #家 #方法
.png&w=3840&q=75)