子どもを褒めることによる効果は?
子どもを正しく褒めることは、子どもの成長に良い影響を与えます。主な効果としては、次の2つが挙げられます。
●子どもの自己肯定感が高まる
●親子の信頼関係が深まる
子どもの自己肯定感が高まる
幼児期にたくさん親に褒められた子どもは、「親に認められた」と実感することで、自己肯定感が高まっていきます。ありのままの自分で良いという自信と、親に愛されている安心感が得られるからです。
自己肯定感が養われた子どもは活動意欲が高まり、チャレンジ精神が旺盛になります。多少ハードルが高いような物事であっても、好奇心と自信を持って取り組めるでしょう。また、親に認められ愛されているという自信は、自分の周りの人に対して優しくし、大切に思う気持ちを持つことにつながります。
内閣府の調べでは、日本の子どもは自己肯定感が低く、自分自身に満足していると応えた若者は50%にも満たないという結果が出ています。[注1]
親に叱られてばかりの子どもは、何事にも自信がなくなり、「自分はダメだ」と思い込むようなります。自尊心を傷つけられた子どもは、当然自己肯定感も育まれません。いつもビクビクし、簡単なことでも失敗を恐れる子になってしまう可能性があります。
親が子どもを正しく褒めることで、社会性や人間性の基礎となる自己肯定感や自尊感情を育むことが大切です。
[注1]内閣府:平成26年版 子ども・若者白書(全体版)「1 自己認識」

親子の信頼関係が深まる
子どもを褒めることは、親子の信頼関係を深めるきっかけにもなります。子どもは親に褒められると、「自分をちゃんと見てくれている」「自分のことを認めてくれている」と実感し、親に対する信頼が高まります。
親子の信頼関係が深まれば、子どもはどんなことにも前向きな気持ちで挑戦できるようになるでしょう。また、子どもが何かにチャレンジし、壁にぶつかったり、悩み事ができたりしたときに、1人で抱え込まず、親に相談できるようになります。
親子の信頼関係は子どもの精神面に大きな影響を与えるので、小さなうちからしっかりと築いていくことが大切です。

合わせて読みたい
上手な褒め方をするには?
子どもの自己肯定感を高め、親子の信頼関係を深めるためには、ただ褒め続ければ良いというわけではありません。次の3つのポイントを押さえて、子どもを上手に褒めることが大切です。
●褒められたいポイントをくみ取って褒める
●具体的な行動を褒める
●努力や過程を褒める
褒められたいポイントをくみ取って褒める

子どもは自分の意思を尊重してもらえていると実感したとき、相手に対する信頼が深まり、自己肯定感が高まります。
まずは子どもを褒める前に、子どもが褒められたいポイントを把握することから始めましょう。トライした感想や、チャレンジを終えたあとどう感じたかを質問し、子どもが褒められたいポイントをできるだけ具体的に褒めてあげることが大切です。
もしトライした感想が「イマイチだった」などあまり芳しくないときは、過剰に褒めることは控えたほうが良いでしょう。
具体的な行動を褒める
子どもを褒めるときは、ただ「すごい!」「えらい!」とほめるのではなく、「毎日計算ドリル頑張ってたから良い点がとれたんだね」など、具体的に褒めてあげましょう。
どんなことを褒めているか子どもにわかりやすく伝わることで、「〇〇をしたから褒められた。次も〇〇を頑張ろう」と、意欲をもって物事に取り組めるようになります。
努力や過程を褒める
具体的な行動を褒めるときは、結果はどうであれ、その努力や過程を褒めてあげることが大切です。「早起きしてマラソンの練習よく頑張ったね」「パソコンの操作が上手くなったね」など、子どもの頑張りをしっかり見ていたことを伝えながら褒めてあげましょう。
結果だけを見て褒めてしまうと、子どもは自分が得意な分野ばかりに目がいくようになってしまいます。また、結果が全てだと思い込み、失敗を恐れるあまりチャレンジ精神が失われてしまう可能性もあるでしょう。
子どもがチャレンジしたことや努力を積み重ねたこと自体が成長の証であることを深く理解し、「結果が振るわなくても努力や過程が大切」だということを、褒めるなかで子どもに伝えることが大切です。

感謝の気持ちや無条件の褒めも大切
「お掃除してくれてありがとう、助かったよ!」など、親から子どもに感謝の気持ちを素直に伝えることも、子どもにとっては最高の褒め言葉になるでしょう。お母さんやお父さんが自分のしたことで喜んでくれれば、子どもは「またお手伝いしよう」という気持ちになります。
また、ときには「あなたが生まれてきてくれて幸せ」など、子どもの存在自体を無条件に褒めることも大切です。
特別なことにチャレンジして結果を出さなくても、親が自分に無条件の愛情を注いでくれていることを実感できれば、子どもの自己肯定感は自然と育まれていくでしょう。
漠然と褒めてあげるより具体的により効率的に褒めてあげることで効果も高まります♪次に、気を付けておきたい点を確認していきましょう!

避けたほうが良い褒め方は?
子どもを褒める際、次の3つの当てはまる褒め方をしている場合は注意が必要です。間違った褒め方は、かえって子どもに悪い影響を与えてしまう可能性があるからです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
漠然となんでも褒める
子どもを褒めることは大切ですが、「すごいね」「えらいね」「上手」など、ただ漠然とした言葉を並べて褒めてもあまり意味がありません。
前述のとおり、子どもを褒めるときはできるだけ具体的に伝えてあげることが大切です。また、子どもをすぐにおだてたり、過剰に褒めることも控えましょう。褒められすぎた子どもは向上が育まれず、すぐに挫折したり、簡単な作業しかやらなくなる傾向があるからです。
また、子どもを褒めることと、叱らないことはイコールではありません。子どもが悪いこともしても叱らず過剰に褒めてばかりいると、自意識過剰な性格になってしまう可能性があります。叱らなければならないときはきちんと叱り、褒めるときとのメリハリを効かせることも大切です。
親の理想に合ったことだけを褒める
親の理想通りの行動をとったときだけ褒め、親が望んでいない行動をとったときは叱る、というやり方は絶対にしてはいけません。子どもは親の顔色ばかり伺うようになり、自信を持てない性格になってしまう可能性があります。
親の理想どおりにしなければ褒められない環境では、子どもの自己肯定感は育まれません。
子どもの自己肯定感を高めるためには、親に認められている、ありのままの自分を愛してくれていると実感することが大切です。親はさまざまな視点から子どもを見守り、長所をたくさん見つけてあげましょう。
他の子どもと比較した言い方をする
「〇〇ちゃんよりも早くできたね」「〇〇くんより良い点数だったんだね」といった、他の子どもと比べるような言い方は避けましょう。常に誰かと比べることが癖になり、自分よりできないと判断した他人に対して優越感を抱いたり、逆に自分よりもできる他人に対して過剰なコンプレックスを抱いたりする可能性があります。
また、「他人に勝てば褒めてもらえる」という考えを持つようになると、他人を蹴落としてでも勝ちたいという心理が生まれてしまうかもしれません。
過剰な競争意識は、学校などの集団生活のなかでトラブルの元になることがあります。他の子どもと比較して褒める・叱るという方法では、自己肯定感を育むつもりが、劣等感ばかりが大きくなってしまう恐れがあります。
他の子どもの結果は気にせず、子ども自身の努力の過程や結果について褒めてあげることが大切です。
合わせて読みたい
子どもの感じたことや頑張ったことに関心を持って褒めることが大切
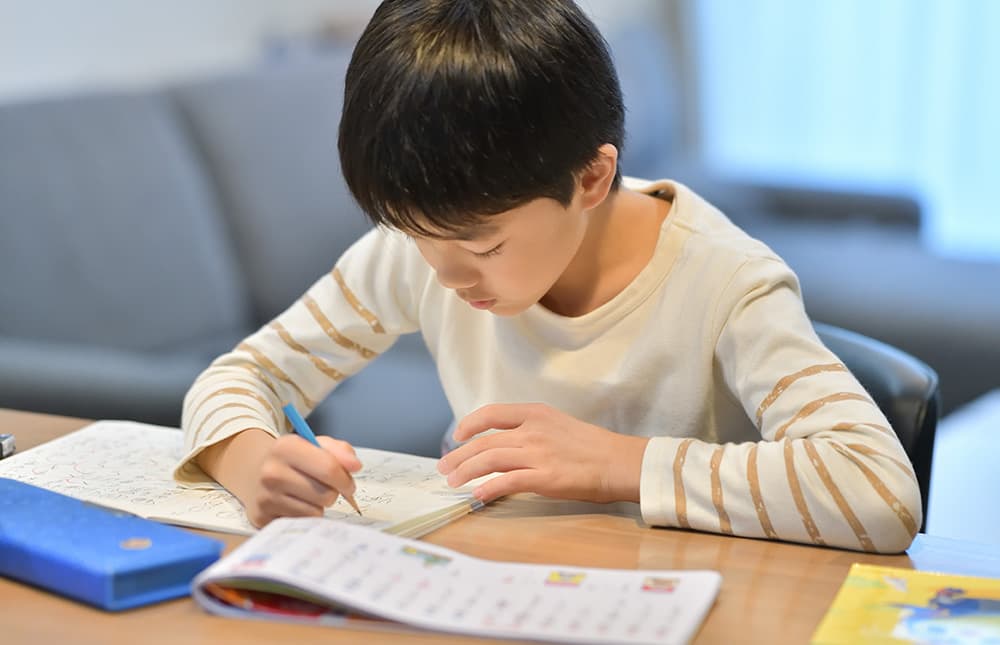
子育てをしていくなかで、褒めることは子どもの自己肯定感を育むために大切な要素です。褒める際は、ただ漠然と褒めるのではなく、チャレンジを通して子どもが何を感じたのかを汲み取り、子どもが褒めてほしいポイントを具体的に褒めてあげましょう。
結果だけでなく、子どもが頑張った努力や過程にも目を向けて褒めることが大切です。また、時には無条件に褒めることも大切です。特別なことにチャレンジして結果を出さなくても、無条件の愛情が注がれていると実感させることで子どもの自己肯定感を高めることにもつながります。
他の子どもと比較したり、親が認めた成果のみ褒めたりというようなことは避け、子ども自身と向き合って褒めることが大切です。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児




















