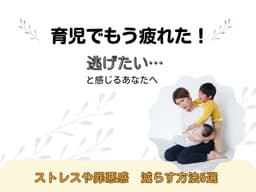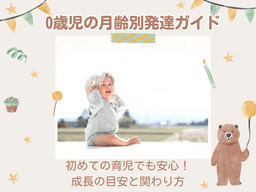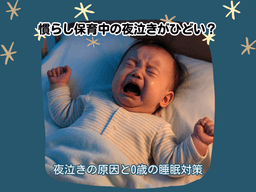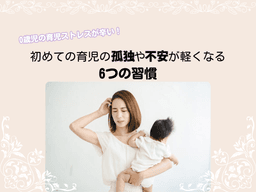新生児の育児が辛いと感じるのはなぜ?

新生児の育児は、喜びや愛情に満ちた瞬間がある一方で、想像していた以上に身体的、精神的に大きな負担を感じるお母さんも多くいらっしゃいます。
特に初めての子育てでは思うようにいかないことが多く、疲弊してしまうことも少なくありません。では、なぜ多くのお母さんが新生児期の育児を辛いと感じるのでしょうか?
ここでは、その理由をいくつかの要因に分けてご紹介します。育児の辛さの原因を理解することで、負担を軽減するためのヒントを見つけていきましょう。
最初の1ヶ月が最も辛いと感じる人が多い
赤ちゃんの育児で最初の1ヶ月が最も辛いと感じるのは、主に体力的な負担が大きいためです。
赤ちゃんはまだ昼夜の区別がつかず、授乳やおむつ替えで頻繁に起きなければならないため、夜間の睡眠がまともに取れないことが続きます。
お母さんはこれに加えて、自分の体調回復や産後のホルモンバランスの変化などに対応するため、自身の体調にも向き合っていく必要があります。
また、赤ちゃんのペースに合わせて生活するため、孤独感や不安を感じることも多いのです。
「ちゃんと育てなきゃ」というプレッシャーと孤独感
初めての育児では「ちゃんと育てなきゃ」というプレッシャーを感じやすかったり、お母さん自身が自分の育児に自信を持てないことも多く、完璧を目指そうとすると心理的な負担が大きくなります。
特に育児は日々繰り返しの作業が多いため、同じことを何度もこなすことに疲れてしまったり、「これで良いのかな?」と自分の育児が合っているのかわからず不安になる場合もあります。
さらに新生児期は外出を控えるケースが多いため、孤独感が加わることがあるのです。
睡眠不足とホルモンバランスの乱れによる心身の負担
新生児期の育児では何度も夜間授乳をしなければならないため、お母さんの睡眠時間が極端に短くなります。
この睡眠不足が長期間続くことで心身の疲れが蓄積してしまいます。
さらに、出産後はホルモンバランスが急激に変化し、気分の落ち込みや不安感が強くなることがあります。
この時期には、体が回復していないことに加えて心も疲れてしまっていることが多いため、無理に頑張らず休むことが非常に重要です。
赤ちゃん中心の生活で自分の時間が取れなくなる
特に初めてのお子さんの場合、お母さんはそれまで自由に使えていた自分の時間が一変、急に赤ちゃんのお世話に追われる日々が始まります。
授乳やおむつ替え、寝かしつけといったお世話は赤ちゃんのリズムに合わせて行わなければならないため、お母さん自身の時間がほとんど取れません。
そのため自分の趣味や休息時間が確保できず、精神的に疲れてしまうことがよくあります。
ですので、この時期はお母さん自身の心と体の健康を心掛けることが大切です。
急激な生活の変化、慣れない子育てを頑張っているのだから、大変だと思うことは当然の感情なんですね!

育児の辛さを和らげる5つの対処法

新生児の育児が辛いと感じることは決して珍しいことではありません。毎日が新しい挑戦の連続で、体力的にも精神的にも厳しい場面が続くことがあります。
しかし、少しでもその辛さを軽減する方法はあります。
育児をしているとどうしても自分を後回しにしてしまいがちですが、少しの工夫で心と体の負担を和らげることができます。
ここでは、育児の辛さを和らげるために役立つ5つの対処法を紹介します。これら実践することで、育児の負担が少しでも軽くなり心の余裕を持つ手助けになるかもしれません。
自分を肯定する言葉を日常に取り入れる
育児の中で最も大切なのは、自己肯定感を持つことです。
新生児の育児は予想以上にハードで、特に初めてのお母さんにとっては自分に自信を持つことが難しいこともあります。
そんな時こそ、自分を肯定する言葉を意識的に取り入れることが効果的です。以下のようなポジティブな言葉を日常に取り入れてみましょう。
- 「今日も一日赤ちゃんが元気でいてくれた。大丈夫、よくやった私!」
- 「おむつ替えをサクッと終わらせられた。少しずつ慣れてきているな。」
- 「今日は昨日より笑顔で接することができた。」
- 「毎日頑張っているから、赤ちゃんが寝たすきに少し休憩しちゃおう!」
このような言葉を意識的に使うことで、自己肯定感が高まり、少しずつ自信を取り戻せます。
また育児に対する耐性も高まり、ネガティブな感情に引きずられず前向きに進むことができるようになります。
自分を責めず、育児の中でできていることに焦点を当てて、日々を過ごすことが大切です。
深呼吸やストレッチで心と体をリセットする時間をつくる
育児の合間に、自分の心と体をリセットすることも重要です。
長時間の授乳やお世話で疲れた体をほぐすために、深呼吸やストレッチを取り入れてみましょう。
深呼吸をすることで、交感神経が落ち着きリラックス効果が得られます。また、軽いストレッチは血行を良くし、身体的な疲労も和らげてくれます。
おすすめの簡単なストレッチ
①肩回しストレッチ
肩こりを感じたら、肩をゆっくり前後に回してみましょう。肩を前に5回、後ろに5回回すだけで、肩周りの緊張がほぐれます。育児で肩に力が入っていると感じたときにおすすめです
②腰回しストレッチ
立った状態で足を肩幅に開き、腰をゆっくりと円を描くように回します。前後、左右に各10回ほど回すことで、腰や背中のこりを和らげることができます。
育児に追われていると、どうしても自分の時間を取ることが難しいですが、短い時間でも心と体をリセットすることで再び元気を取り戻すことができます。無理をせず、少しでも自分のための時間を作るようにしましょう。
「泣いていても大丈夫」と受け止める考え方を持つ
赤ちゃんが泣くと、お母さんは不安や焦りを感じてしまうことがあります。
しかし、「泣いていても大丈夫」という考え方を持つことが、育児のストレスを軽減する一つの方法です。
赤ちゃんは泣くことによって、自分の欲求を伝えようとしています。そのため、泣くことは決してお母さんのせいではなく自然なことです。
赤ちゃんが泣いている間は少し冷静になり、自分の感情を落ち着けてから対応するよう心掛けましょう。育児に完璧はないことを受け入れ、焦らずに最善を尽くすことが大切です。
自宅で受けられる育児支援や産後ケアサービスを活用する
育児が辛いと感じた時は、無理をせずに育児支援や産後ケアサービスを活用しましょう。
自宅で受けられるサポートを利用することで、育児の負担を軽減することができます。
例えば、産後ケアや育児相談を提供しているサービスを利用することで、専門家からアドバイスをもらったり育児の悩みを聞いてもらうことができます。
また、地域の助成金制度を活用して、保育サービスや家事代行サービスを取り入れることも一つの方法です。
お住まいの地域の子育て支援課や福祉課に問い合わせて、育児支援サービスや産後ケア助成金などの詳細を確認してみましょう。自分に合ったサポートを受けることができるかもしれません。
家族や周囲と育児の負担を分かち合う
育児の負担を一人で抱え込むと、心身の疲れが溜まってしまいます。
そのため、パートナーと育児の役割を分担したり、実家や親しい友人にサポートをお願いすることが大切です。育児は一人で全てをこなすものではなく、周囲と協力し合いながら進めていくものです。
例えば、夜の授乳やおむつ替えを交代で行ったり、赤ちゃんを見ていてもらう時間を作り、少し休息の時間を確保することも有効です。
周りに頼ることをためらわず、積極的にサポートを受け入れることで育児が少し楽に感じられるようになるでしょう。
産後は自分が思っているよりも精神的・肉体的に参っていることもあります。ギブアップする前に周囲に助けを求めることが大切です。無理をせず、サポートを頼むことで心に余裕を持つことができるようになります。
妊娠中は赤ちゃんをママ一人でお腹の中で育ててきたけれど、生まれてきてからは周りの手を借りて育てていくことが出来るんだね♪

ひとりで抱え込みそうなときの対処法
新生児の育児は、喜びと同時に多くの挑戦も伴います。
特に初めての育児では、お母さんとしての責任感やプレッシャーからどうしてもすべてを自分一人で背負い込んでしまいがちです。
ここでは、ひとりで抱え込みそうなときに試すべき対処法をご紹介します。早速見ていきましょう。
外出できるようになったら行けるイベントや親子教室を探しておく
新生児期は外出を控えることが多いため、育児に関して孤独感を感じることもあります。
しかし赤ちゃんが成長し外出できるようになった時、地域で開催されている育児イベントや親子教室に参加することが有益です。
自治体主催の育児イベントや親子教室は、赤ちゃんと一緒に参加できることが多く、育児の悩みを解消したり、同じ悩みを持つ親とのつながりを作る貴重な機会となります。
外出できる時期に向けて、これらのイベントをチェックしてみましょう。育児の支えとなるネットワークを作ることができ、今後の育児で孤独感を和らげる手助けになります。
また、育児に悩んでいたり、相談したいことがある場合は親子教室に参加するのもおすすめです。
親子教室ベビーパークでは、育児に役立つ知識を学べるだけでなく他の親御さまと交流することができ、育児の悩みを共有したりアドバイスをもらったりすることができます。
体験レッスンには生後2ヵ月から参加できますので、外出できるタイミングを見計らって検討してみてください。
完璧を目指さず“できること”を大切にする
新生児の育児では、完璧を目指し過ぎると精神的な疲れが増してしまうことがあります。
「ちゃんと育てなきゃ」と自分に厳しくなりすぎず、できる範囲で最善を尽くすことが大切です。
育児には予想外の出来事や困難がつきものですが、すべてを完璧にこなすことは不可能です。自分を許し、できることを大切にすることで、心の余裕を持つことができます。
育児においては「完璧な親」を求めるのではなく、十分に頑張っているということを自覚し、時には肩の力を抜いて自分自身を大切にすることも忘れないようにしましょう。
この心構えが育児の辛さを軽減し、より健やかな育児生活を送るための鍵となります。
新生児の育児の辛さが落ち着く時期

新生児の育児、最初の数ヶ月は育児にもなれず、ペースもつかめず特に大変なものです。
しかし、時間が経つにつれて少しずつ余裕が生まれ、育児の負担が軽く感じられるようになります。
生後3ヶ月を過ぎる頃から、赤ちゃんも成長し、生活のリズムが整ってきます。
ここでは、新生児の時期ごとの変化について解説します。どの時期にどのような変化が訪れるのかを理解することで、育児の見通しを立てることで心も少し軽くなるでしょう。
生後3ヶ月頃から少しずつ余裕が生まれる
新生児期が過ぎると、少しずつ赤ちゃんにも生活のリズムがつき始めます。
特に生後3ヶ月を過ぎる頃から、赤ちゃんは徐々に昼夜の区別がつくようになり、寝る時間と起きる時間が安定してきます。
そのため、親の睡眠時間も改善され、心身の疲れが軽減されることが多いです。
また、この時期には授乳の間隔も広がり、赤ちゃんが授乳以外でリラックスしている時間が増えてくるため、親自身も少し自分の時間を持つことができるようになります。
このように、赤ちゃんの成長と共に育児にもリズムがついてくるため、焦らずに赤ちゃんの成長を見守っていくと良いでしょう。
夜泣きや授乳が落ち着くタイミング
夜泣きや夜中の授乳は個人差があり、早ければ生後間もなく落ち着く子や、生後6ヶ月から1歳半くらいまで続く子、一度落ち着いてもまた続く場合もあります。
ですので、この時期は赤ちゃんの成長に合わせて、お母さんの睡眠時間を考慮した日中のスケジュールを組むようにしましょう。
育児だけではなく、家事も1人で完璧を求めるのではなく、周りの家族や地域のサポートなどを利用しながら過ごしていくことが必要です。
月齢ごとの成長を知って見通しを持とう
新生児期の育児は先が見えづらく、不安や戸惑いを感じやすい時期です。しかし、赤ちゃんの月齢ごとの成長の目安を知っておくことで、少しずつ見通しが立てられるようになり、気持ちが楽になります。
赤ちゃんの月齢ごとの変化
・生後4ヶ月頃
首がすわり始め、視線を合わせたり、周囲に興味を持ち始めます。抱っこの負担が少し軽くなったと感じることもあります。
・生後6ヶ月頃
離乳食がスタートし、授乳だけの生活から少しずつ変化が見られます。食事の時間が生活リズムを作るきっかけになります。
・生後7〜8ヶ月頃
おすわりやハイハイができるようになり、赤ちゃんが自分で動くことで日中ほどよく疲れ、まとまって寝る時間が長くなる場合もあります。
このような成長の段階をあらかじめ知っておくことで、「今は大変だけど、もう少しでこんな変化があるんだ」と気持ちに少しゆとりが生まれることもあります。
赤ちゃんの成長に合わせて心構えをしておくことが、前向きな気持ちを保つ手助けになるでしょう。
合わせて読みたい
まとめ
新生児の育児は、最初の数ヶ月が特に辛く感じられることが多いですが、少しずつその負担は軽減されていきます。育児の辛さを和らげるためには、自分を肯定する言葉を使うことや、心と体をリセットする時間を意識的に持つことが重要です。
また、赤ちゃんが泣いていても大丈夫と受け入れる心の余裕を持ち、周囲のサポートを積極的に活用することも大切です。育児を一人で抱え込まず、家族や地域の助けを得ることで、より楽に育児を楽しむことができます。
もし、さらに育児についての具体的なアドバイスを得たい方は、お気軽にベビーパークにご相談ください。育児は一人でするものではありません。周囲の支援を得ながら、赤ちゃんとともに素敵な成長の瞬間を楽しんでください。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #新生児 #育児 #大変 #授乳 #夜泣き