- 幼児教室のベビーパーク ホーム
- 育児がもっとたのしくなるコラム
- その他の記事一覧
その他 の記事一覧
ベビーパークの子育てが楽しくなる幼児教育のコラム一覧です。 「知育」や「自己受容」など子育てするママが気になるフレーズについて解説しています。
おすすめ記事

「メンタルリープ」って何?~その意味や起きる時期、親としてできることを解説!~
近年、育児に関する記事やニュースを読んでいると、「メンタルリープ」という言葉を目にする機会が増えています。 「メンタルリープ」とは、赤ちゃんがその成長の過程のなかで、ある時期急速に脳が発達することという意味で、その時期にさしかかると子どもの様子が変わったり、ぐずって不機嫌になったりといったことが起きるといわれています。 こちらのコラムでは、この「メンタルリープ」が起こるといわれている時期や、その時に見られる兆候や親としての対処法などを説明していきます。赤ちゃんの時は身体もそうですが、脳が非常に急速に発達する時期です。お子さまの成長の手助けになれれば幸いです。

「3人目、産む?諦める?」平均年齢からメリットデメリット、経済面まで!悩む方への徹底ガイド
3人目の子供を迎えるかどうか、悩んでいませんか?この記事では、3人目の子供を持つ際の平均年齢、メリット、デメリット、そして3人目を迎えた家庭のリアルな声まで、幅広くご紹介します。この記事を読んで、3人目の子供を産むべきかどうか、悩んでいる方はご自身で決める際のヒントにして下さい。

すぐ泣く子供の特徴・心理や接し方、HSPや発達障害との関係について解説!
子供がすぐに涙を見せると、親として心配になることもあるでしょう。この記事では、すぐ泣く子供の心理的特性と、その背景にある感情表現を年齢ごとに解説します。また、HSP(Highly Sensitive Person)や発達障害との関連性にも触れ、親が理解を深めて正しいサポートができるような情報を紹介します。この記事を通じて、子供の感受性を大切にしながら親子の絆を深めるヒントを学んでいきましょう!
.jpg&w=256&q=75)
言うことを聞かない子供の対処法3選|イライラ・疲れた時の正しい𠮟り方
何度叱っても言うことを聞かない子どもっていますよね。どんなに言っても走り回るのをやめない、スーパーのお菓子コーナーで寝転んで買ってほしいと駄々をこねる、、、時に親はヘトヘトなってしまいます。そんな、言うことを聞かない子どもを理解するためには、まず親が冷静に子どもの特性を知る事から始めましょう。初めから大人たちの言うことを全て聞く子どもはいません。実は子どもは考えながら自分にとって良いか悪いかを判断していて、その結果大人の言うことを聞かない場合もありますが、それも子どもが成長しているプロセスの一つだと親が理解しておく事が大切です。子どもが言うことを聞かなかった時、パパ・ママが「どうして私の言うことを聞いてくれないの?」と感情的に叱ってしまうとますます関係が悪くなってしまいます。イライラをコントロールして「子どもが言うことを聞かない理由」を素直に、そして冷静に考えてみましょうね。また、子どもの成長する年齢によっても叱り方や対処法は異なってきます。今回のコラムでは、年齢別での対応の仕方についても学んでいきましょう。※こちらのコラム記事は、三輪田理恵様の記事を引用して作成しています。https://coelog.chuden.jp/child-rearing/never-heard-that-said/

逆さバイバイは健常児もする?自閉症との関係と親ができる対応法
子どもが「さかさバイバイ」をするとき、親御さんは不思議に思うかもしれません。この記事では、逆さバイバイが何を意味しているのか、その理由と、自閉症との関連性について詳しく解説します。さらに、この行動が意味する可能性のある発達のサインに対して、親がどのように対応すれば良いのかについても触れていきます。子どもの行動をより理解し、さかさバイバイについて正しい知識が身につくでしょう。
新着記事

幼児の勉強させすぎはNG?やりすぎラインを見極める5つのチェックポイント
幼児期は学びへの好奇心が芽生える大切な時期です。だからこそ、少しでも成長につなげたいと、つい「もっと勉強をさせなきゃ」と思ってしまう親も多いのではないでしょうか。しかし、幼児に勉強をさせすぎると、ストレスがかかったり学びへの意欲が下がったりすることもあります。「このままでいいのかな?」「勉強やりすぎていないかな?」と不安を感じたら、見直しのサインかもしれません。この記事では、幼児にとって無理のない学習の進め方や、勉強させすぎを防ぐためのチェックポイントを丁寧に解説します。子どもの笑顔と成長を両立させるために、いま一度、日々の関わり方を見つめ直してみましょう。
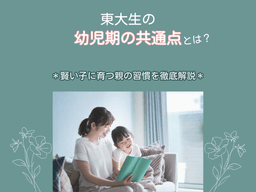
東大生の幼児期の共通点とは?賢い子に育つ親の習慣を徹底解説
幼児期の過ごし方や、親の接し方が、子どもの知性や人間力の土台を築く重要な要素となります。「東大生が幼児期にどのような環境で育ったのか」は、子育て中のお母さんお父さんにとって気になるテーマではないでしょうか。東大生の幼少期の過ごし方を知ることで、「どうすれば賢く育つのか」「どんな習慣が学力に結びつくのか」といった疑問に対するヒントが得られるでしょう。この記事では、東大生の幼少期に共通する生活習慣や遊び方、親の接し方、習い事についてわかりやすく解説します。
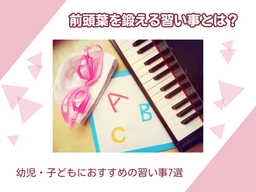
前頭葉を鍛える習い事とは?幼児・子どもにおすすめの習い事7選
幼児期は脳が最も活発に成長する時期です。特に「前頭葉」は、思考や感情のコントロール、社会性など、子どもの将来に大きな影響を与える重要な領域です。子どもの可能性を広げたいと思う保護者の方にとって、どの習い事が前頭葉に良い影響を与えるのか、気になるところではないでしょうか。この記事では、脳科学の視点から前頭葉を鍛える意味を解説し、幼児期におすすめの習い事を7つ紹介します。この記事を読めば、お子さまにぴったりの学びの場がきっと見つかるはずです。

応答的な関わりで0歳児の心を育てる|今すぐ始めたい5つの習慣
0歳の赤ちゃんと過ごす日々は愛おしく感じると同時に「今の育児は合っているのか?」という迷いもつきものです。言葉を話せない赤ちゃんに、どう関わればよいのか戸惑うこともあるかもしれません。そんなお母さん、お父さんにこそ知ってほしいのが「応答的な関わり」です。これは、赤ちゃんの仕草や泣き声に丁寧に応えることで信頼関係や自己肯定感を育む育児法です。この記事では、応答的な関わりやその効果を解説し、今日から始められる具体的な習慣を分かりやすく紹介します。応答的な関わりを知ることで、赤ちゃんとの時間がもっと楽しく、さらに愛おしく感じられるようになるでしょう。
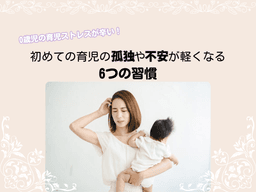
0歳児の育児ストレスが辛い!初めての育児の孤独や不安が軽くなる6つの習慣
はじめての育児に向き合う毎日は、かけがえのない時間である一方で「自分の時間がない」「眠れない」「誰にも頼れない」といったストレスと隣り合わせでもあります。特に0歳児との生活は、授乳や夜泣きの繰り返しで心も体も消耗しやすく思うようにいかないことが続くと、自己嫌悪や孤独感を感じてしまうこともあるかもしれません。そんなときに大切なのは“がんばりすぎないこと”。完璧を目指さなくても、心が軽くなる習慣を少しずつ取り入れることで育児の毎日にゆとりと笑顔が戻ってきます。この記事では、0歳の育児ストレスの原因やその背景、ストレスと上手に付き合う考え方、そして今日からできる6つの習慣をご紹介します。「今のままじゃつらい」と感じている方こそ、ぜひ読み進めてみてください。

生後9ヵ月の赤ちゃんにおすすめ知育玩具10選|発達を促すおもちゃの選び方
生後9ヵ月の赤ちゃんは、視覚・聴覚・触覚がますます発達し、感情表現や好奇心も豊かになってくる時期です。そんな時、赤ちゃんの成長をやさしく後押ししてくれるのが「知育玩具」です。しかし、「どんなおもちゃを選べばいいの?」「どんな効果があるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、9ヵ月の赤ちゃんにぴったりの知育玩具10選を厳選してご紹介します。さらに、この頃の赤ちゃんの発達の特徴や、失敗しないおもちゃ選びのポイントも解説。遊びながら自然に学び、親子の時間を充実させたい方にとってきっと参考になる内容です。選び方のコツを押さえながら、楽しく発達を促すおもちゃを見つけましょう。
1/1







