「言葉育て」は行きつ戻りつ、復習も大切
言葉育てに限らずすべての育児において、子どもの発達は行きつ戻りつです。一つの段階を通り過ぎたからといって、その取り組みをまったくおこなわなくなると、せっかく獲得した能力が次第に消えていってしまうともいわれています。シナプス回路が髄鞘化し本当に強固に定着したと呼べるまでには、何千回ものくり返しが必要です。
現在レベルDと思える子どもでも、時にはレベルAの取り組みの復習を心がけると、さらなる能力の獲得によい効果があると考えられています。
「レベルA」に適した取り組み
.jpg&w=2048&q=75)
まずは、レベルAから解説していきます。我が子がレベルA~Dの発達段階のどちらに位置するかの確認はコラムNo.136「2歳児の「言葉の育て方」~発達段階別に実践的な方法を紹介~①」でできますので、まず確認してみてくださいね。
合わせて読みたい
①今行っていることをより楽しめるように言葉を工夫する
例えば、着替えさせたい時に「ちゃんと服を着て、そうしたらお出かけできるよ」と言うよりも、頭から服をかぶせて「○○ちゃんはどこ~?いた!○○ちゃんの頭、ポン♪」と楽しく言ってあげる方が子どもは喜びます。子ども自身が楽しみながらおこなっていることならば、より親の言葉に集中できるので、文章中に登場した単語がスムーズに記憶に残りやすくなります。
②子どもの表現をふくらましてあげる
今起きていることばかりではなく、過去のことや、明日など少し先の未来に起こるだろうことについて話そうとする機会が増えてきます。
そういう時には、親もよほど忙しくない限りはなるべく丁寧につきあってあげます。そして、子どものたどたどしい表現をふくらませて、具体的な場面をイメージしやすいように手伝ってあげます。
この時期の子どもは、自分のことを名前で呼ぶことが多いですが、例えば「○○ちゃんボール蹴った、みんな跳ぶ」とよくわからないことを口にしたとしても、昼間一緒に公園に行って子どもの様子をよく見ていれば、何のことを話しているのか推測できるものです。
「そうだね、○○ちゃんはボールを蹴ったね。蹴ったボールをお友だちが拾ってくれたの。お友だちはみんなで縄跳びをしていたね。みんな上手に跳んでいたね。○○ちゃんも跳ぶ?」という感じです。
③子どもの意識の移り変わりを敏感に察知する
昨日の思い出や明日の楽しい予定について話していたら、突然子どもの関心が今目の前のことに移ることがよくあります。そういう時、大人はつい今までの会話を継続させようとしがちですが、できればすぐに子どもの新しい興味に話題を移すようにします。
この時期の子どもは、大人に言われれば言われたものに注意を移すことができる段階にきていますが、それは子どもの注意力の発達を遅らせてしまう可能性もあります。集中力をつけるためには、大人がやらせたいことに集中させようとするのではなく、子ども自ら夢中になっていることを大切にしてあげます。
④一つの同じ言葉を、いろいろな場面で聞かせることを意識する
例えば「犬」という言葉を、自分が飼っている犬に対してしか聞いたことがない子どもは、他の犬に対して「犬」という言葉を聞いたことがある子どもよりも、概念形成が遅れてしまうといわれています。
絵本や散歩中の犬、ペットショップの犬など様々なシチュエーションでその言葉を聞いた子どもは、「犬」という言葉が表す概念をつかむ速度が早まります。名詞だけではなく、動詞や形容詞でも同じです。子ども自身がまだよく意味がわかっていないであろう言葉に気づいたら、意識的にその言葉を聞かせる回数を増やしてみます。できる限り多様な場面で用いると効果的です。
「レベルB」に適した取り組み
続いて「レベルB」にある子どもへの具体的な取り組みです。
.jpg&w=2048&q=75)
①一つのカテゴリーに属する細かい単語を教える
細かい部分にとても興味をもつ時期です。体ならまゆげ・あご・つめ・ひじ・ひざ・かかと、洋服ならボタン・えり・そで・ベルトなどです。教えようとするのではなく、親がその単語を自然に口にすることで、着替えのような毎日の生活習慣をすばらしい学習の機会にしていきます。
②すでに獲得している概念を活かして、新しい単語をどんどん教える
目の前にないものでも、言葉だけで物事を理解できるようになります。すでに知っている概念を手がかりに、次々と言葉を増やしていくことができるのです。
例えば、乗り物という概念の中には自動車と自転車があることを知っているので、新しく一輪車を見ればすぐに意味を理解して、言葉と結びつけることができます。
少し難しいと感じるような言葉でもかまいません。教えるといっても覚えさせるのではなく、言葉と意味が正しく結びつく状況でその言葉を聞かせる機会を増やすという方法です。
③何かを指示しなければならない時には慎重におこなう
子どもが何かに集中している時に指示をすることは、イライラを招く原因となります。子どもの集中がそれた瞬間を見計らって、優しく指示を出します。何かどうしても指示しなければならないようなことは、事前に何回も言っておきます。
例えば、テーブルにつかせたい時など、急に指示するのではなく、早めに予告しておき、子どもの遊びへの集中度が落ちた時に行動させるようにします。その際もその行動が面白くなるような声かけをすると効果的です。
例えば、「○○ちゃん列車、テーブル駅に向かって出発します!ぽっぽ~!」と声かけして子どもの肩に両手をかけ、子どもを機関車、親が客車となってテーブルまで誘導すれば喜んで座ってくれます。楽しい行動と共に聞いた言葉からは、たくさんの文法表現を驚異的なスピードで身に付けていきます。
④毎日30分間だけは、子どもに向き合って一緒に遊ぶ時間を作る
この時期、子どもの会話力が急激に発達し、できることも増えてくるため、もうあまり頑張らなくても大丈夫のような気分になってしまうご家庭も少なくありません。しかしこの時期、子どもの親に構ってほしい感情はとても強くなっています。
毎日必ずお母さんやお父さんが自分としっかりと向き合って遊んでくれる時間がある、と確信している子どもは、そうでない時間に無理を言って親を困らせることはなくなっていきます。しかし、その確信が持てていないと、なんとか親の気を惹こうとして様々な問題行動を起こしてしまうことも少なくなく、そういう時には新しい言葉もなかなか子どもの記憶には残らないものです。
⑤荒唐無稽なファンタジーを避ける
子どもと一緒に絵本を読むことは積極的に継続しますが、この時期はファンタジーは避け、現実味のあるお話を選ぶことが重要です。
幼児期の子どもに豊かなイマジネーションを養うことは非常に大切ですが、この段階の子どもはまだファンタジーを受け止められません。ようやく自分の周りの世界を、言葉を通して少しずつ理解し始めたばかりで、もっとたくさん知ろうとしているところですから、現実にありえない話を与えるとすぐに混乱してしまいます。
これまで読み聞かせてきた絵本の中から現実味のあるものをセレクトします。魚や機関車が空を飛んだり、動物がお話ししたりする絵本は少しお休みします。ただし、ミッフィーやしろくまちゃんシリーズのように、動物やオモチャが完全に擬人化されているものはかまいません。子どもが日常生活で経験しているような、身近なテーマを扱ったものを選ぶようにします。
⑥TVは親と一緒に見て、内容についておしゃべりする時間を作る
TVやDVDはまだ一日30分程度までにし、画面の内容理解を深めるために、ごく短い言葉での解説を適宜おこないます。できるだけ短い言葉にすることがコツです。番組の選択基準は絵本と同じです。数やものの大小・色・わらべ歌や童謡などを扱っているものも効果的です。
「レベルC」に適した取り組み
さらに「レベルC」にある子どもへの具体的な取り組みについてご説明します。
.jpg&w=2048&q=75)
①子どもの集中力について正しく理解し、利用する
2~3歳の間、子どもの注意集中力の発達はあまり変化がありません。自分の興味あるものや活動に集中して、大人の言うことをまったく聞かないことがよくあります。時には大人の声に耳を傾けて指示に従うことができる時もありますが、ものすごく集中している時には不可能ともいえます。
かなりお兄さん・お姉さんらしくなってきていますが、実は1歳までと同様に一度に一つのことにしか集中ができません。大人のように同時に複数のことを考えたり行ったりできるようになるのはまだまだ先の話です。
親の指示にむりやり従わせようとすると、かえって集中力の発達を遅らせる場合もあります。どれだけ集中していても、音がしたり何かが動いたりするだけで子どもの集中力は途切れます。指示を与えるのはその時がチャンスです。
綺麗な音のベルを鳴らすなどして意図的に注意をそらすのも一つの方法です。子どもの注意がそれたチャンスを活かして、笑顔で子どもの顔を真正面から見つめて親に意識を移し、その瞬間に指示を与えます。この時期の子どもは、あまり長く待つことはできません。複数の指示を与える場合は、行動すべき時の直前に、楽しい雰囲気でテンポよく指示します。そういう時に耳にした言葉は非常によく覚えていくものです。
②接続詞を意識的に使う
「だから」「そして」「すると」「なぜならば」といった接続詞を理解し、正しく使えるようになってきます。子どもの会話はまだ2、3語文が中心ですが、接続詞を用いて文をつなげられるようになると、親も子どもが言いたいことを理解しやすくなるので、適切な言葉かけがしやすくなります。普段から大人が積極的に接続詞を聞かせることで、子どもの会話も上達します。
③クイズ形式の質問で遊ぶ
正解を要求するような質問ではなく、遊びとしておこなうクイズです。絵本や絵カード、人形などを使って「どちらの人が眠っているかな?」「女の子は何をしているかな?」といった質問で言葉による思考力を高めていきます。
子どもに「間違えた」と感じさせないよう、もしも子どもが答えなければ、親が自然に「右の人が眠っているね」などと答えてしまいます。正しい答えを言った時にはたくさん褒めますが、間違えた時には「この人も眠くなったかな。眠っちゃおうかな。おやすみなさい~」など、物語に作りかえてしまってもよいです。
また、子どもにある出来事を思い出させるような質問もしてみます。「今日公園で、ボールで遊んだあとにお友だちと何をしたか覚えている?」といった質問は、子どもに出来事をしっかりと思い出させます。この質問遊びをする時には、何か子ども自身がとても楽しんでいた出来事を話題にするようにします。会話にのってこなければしつこくは聞かずに、潔く会話は中止します。
「レベルD」に適した取り組み
最後に「レベルD」にある子どもへの具体的な取り組みについてご説明します。
.jpg&w=2048&q=75)
①ジョークで笑いあう時間をたくさん作る
日本語をほぼ正確に習得できているので、おかしなことや間違ったことをいうと気が付いてクスクス笑います。高度な「三次性の笑い」です。この笑いが頻繁に見られるようになってきたら、わざとおかしな文章を作って一緒に楽しみます。空想の翼が広がるファンタジーも解禁しますが、まだ現実と空想が混ざりやすいことは念頭に置いておきます。
合わせて読みたい
②子どもの言葉を直すことは避ける
子どもに自分の話し方を意識させないようにします。ここまで子どもの言葉が上手になってくると、親は間違いが気になり始め、つい直してあげたくなってしまいがちですが、まだそれは早いです。
「行かないかった」などの活用形の間違いや、スプーンと発音できずに「シュプーン」になることもあります。しかし、それを指摘されたところで子どもが得るものは何もありません。それよりも、「そうだね、行かなかったのね」「スプーンがいるのね」と正しい表現で返事をしてあげることが一番です。
この時期、吃音が出る子どももいます。2歳代での知能指数が高い子どもに出やすいと考えられています。通常は3歳後半~4歳代にかけて起こることの多い、言語発達において正常な現象です。
頭の中に言いたいことがいっぱい詰まっているのに、それを全部表現するだけの言葉をもたないために起こります。子どもは考えることに集中しているので、自分が同じ言葉をくり返していることにまったく気がついていません。子どもの言語能力が発達するにつれて、数ヵ月で次第におさまっていきます。
それでも万国共通、周囲の大人が不必要に騒ぎ立てたり落胆してしまったりすることが多いのも現状です。子どもを助けるつもりで「もう一度ゆっくり言ってごらん」や「話す前に深呼吸して」などと言ってしまいがちです。それによって、せっかく何も意識していなかった子どもが、どもるのをやめようと努力し始めてしまい、かえって本当に吃音を引き起こしてしまうこともあるといわれています。
③体験活動を通して、様々な言葉を習得させる
例えば、葉っぱや木の幹に紙をあてて鉛筆でこするような遊びでは、「浮き出る」「浮き彫り」「破片」「突き出る」「葉脈」などたくさんの言葉が使えます。子どもは体験を伴わないペーパープリントだけの学習を非常に嫌がる傾向がありますが、体験を伴ったことについてペーパープリントで思い出すことは嫌いではありません。
実際に五感・体感を伴った行動があって初めて、子どもの言葉や学びは発達します。子どもとの会話に不自由を感じなくなったら、より新しい体験を求めて休日の過ごし方などの計画を立ててみます。これまでに行ったことのある動物園や公園を回りなおしてみても、以前とは違った子どもの成長ぶりに嬉しい発見があるかもしれません。
まとめ:子どもの言葉の成長度合いをよく見て、適切な対応をしよう
いかがでしたでしょうか?
「言葉の発達」は、心配になる両親の気持ちもよくわかるものですが、まずは子どもの言葉の成長がどの位置にあるのかをしっかり見きわめることが重要です。
子どもの発達の度合いがわかれば、あとは適切な接し方を心がけることで、子どもの言葉は大きく成長していきます。まずはお子さまと毎日よく接してあげて、子どもの様子をしっかりつかんでみてくださいね。
.jpg&w=2048&q=75)
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児
.jpg&w=2048&q=75)

.jpg&w=256&q=75)






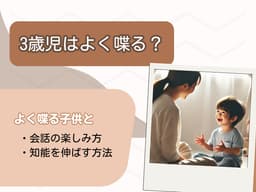









.png&w=256&q=75)












