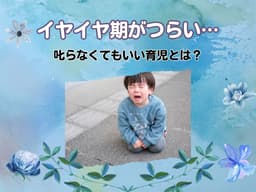栄養学や食育は、様々な説が生まれては消える状況
欧米スタイルの食生活が普及してすでに60年以上がたちますが、その間、アレルギーやアトピー問題、牛乳を学校で強制的に飲ませることへの賛否両論等、様々な食にまつわる問題が生じてきました。
現在は昭和の頃に比べると「物事の本質」に目を向ける専門家もずいぶん増えてきて、60年間の栄養常識に疑問を唱える声が高まってきました。とはいえ、まだまだ科学的にはっきりとした結論は出ておらず、現在も次々と「最新研究の結果」が発表され、様々な説が生まれては消えていきます。
しかし、数多くの「科学の最新研究結果」というものは、その実験方法の範囲内において、こういうことがわかった、という域を出るものではなく、新たな条件を加えたら、まったく違う結果が出るかもしれないものです。

既存の知識だけを鵜呑みにせず、自分の頭で判断する姿勢が大切
私達がわが子のためにできることは、「既存の栄養学」や「世間一般の食育」を鵜呑みにすることなく、情報を集め自分自身の頭で判断する姿勢ではないでしょうか。ここでは、未だ専門家の間でも決着がついていないものの、非常に重要な乳幼児期に避けたほうがよいと考えられる食物の情報をいくつかお伝えいたします。
さまざまな考えがある中、親御さんは親御さんは正しい知識を得ることがとても大切です♪

避けたほうがよい食材1:牛乳・乳製品・フォローアップミルク
コラムNo.90「食育の「脅し文句」に悩まないで!~日本人に適した食事について~」でも解説したドイツの「フォイト栄養学の常識」によって、「牛乳は体によい」という説はきわめて一般的なものになりました。学校・幼稚園の給食や病院食にも、必ず牛乳が入っていることからもその根強さがわかります。
しかし今、「牛乳」に対して警鐘を鳴らす専門家が多数いるのも事実です。また、スウェーデンやフィンランドなど牛乳の消費量が多い国ほど骨粗鬆症や骨折患者の比率が非常に高いこともわかっています。それに引きかえ、牛乳を飲む習慣がなかった頃の日本には骨粗鬆症などありませんでした。
合わせて読みたい
牛乳を大量に摂取すると体内のカルシウム量はかえって減る
現在の科学ではっきりわかっていることは「牛乳を大量に摂取すると体内のカルシウム量はかえって減る」ということです。通常、人間の血中カルシウム濃度は血液100cc中に9~10ミリグラムと一定しています。ところが牛乳を飲むと血中カルシウム濃度は急激に上昇します。飲んですぐに検査すると一瞬カルシウムがより多く吸収されたようにみえますが、実は体は濃度をなんとか通常値に戻そうと、カルシウムを腎臓から尿に排泄してしまいます。
また牛乳にはタンパク質が多く含まれるので大量に摂取すると血液が酸性になります。
これを弱アルカリ性に戻すためには飲んだ牛乳に含まれるカルシウムだけでは足りず、不足分は骨に元々あったカルシウムから使われます。つまりカルシウム摂取のために飲んだ牛乳によって、結果的にはかえって体内のカルシウムが減る…、という現象が起こります。
カルシウムは緑黄色野菜や海草、穀物から十分に摂れます。動物園育ちではない野生の馬や象は草しか食べていませんが、彼らは立派な骨格を持っており、まして野生の馬や象が骨折したという話は聞いたことがありません。
いま、カルシウムが不足してしまう最大の原因は「動物性タンパク質の過剰摂取」によるものといわれています。また牛乳は飲む前は液状ですが、胃に入るとすぐに固まってしまい大変消化が悪いです。
さらに市販の牛乳は脂肪分を均等化させる為に攪拌しますが、この時に空気が大量に混じり乳脂肪分が過酸化脂質になります。それを今度は120度の高温で殺菌するのでタンパク質は変質し、この過酸化脂質を多く含む牛乳は腸内環境を悪化させ、悪玉菌を増やし腸内細菌のバランスを崩します。「母乳からそろそろ牛乳に切り替えなくちゃ」と思って実行してみた人は赤ちゃんの便が急に臭いニオイがするようになった事に気づくでしょう。

牛乳は嗜好品ととらえて子どもに毎日は飲ませない
牛乳や乳製品は子どもにとってジュースと同じ嗜好品として考えた方がよく、毎日飲ませてしまうとアレルギーにつながってしまうこともあるため、まだ消化器官の未熟な乳幼児に早い時期から毎日牛乳や乳製品を与えることは避けたほうがよいと考えます。
「牛乳が健康に良いのか?悪いのか?」の科学的な研究結果は未だ明らかになってはいません。しかし牛乳を与えなくても必要な栄養は別の食品から十分に摂れるのです。もし、20年後に「やっぱり体に悪かった」などという結果が出てから悔やんでも、もう取り返しはつきません。愛するわが子に早期に与えるかどうか、それを判断できるのは両親しかいないのです。
フォローアップミルクは牛乳に非常に近いもののため、同様に扱うべき
また、フォローアップミルクは粉ミルクとは違った位置づけの商品であり「母乳の代替品」として作られてはいません。あくまで「離乳食で他の食品を摂取している事を前提」に「離乳食では不足しがちな栄養素を補う」とした「粉ミルクと牛乳の中間的存在」として成分が調整されているので、粉ミルクよりはるかに「牛乳」に近いものです。0歳児に与える必要はまったくない商品です。
避けたほうがよい食材2:バナナ・パイナップル・マンゴー・パパイヤ・キウイ等、南国のフルーツ

これらはタンパク質が多いので乳児期には避けたい果物です。また南国の食べ物は体を冷やす「カリウム」の含有量が多いので、鼻水・鼻づまりを起こしやすくなり中耳炎の原因にもなりかねません。体調が崩れるのでカンも強くなりがちです。また、南国に限らず果汁には糖分が多いので あげる際には分量や与え方などに配慮しましょう。
避けたほうがよい食材3:エビ・カニ・貝・蕎麦
これらはアレルギー反応がアトピーやかゆみというレベルでなく、命に関わる「アナフィラキシー・ショック」を起こしやすいので、十分に気をつけたい食品です。まだ研究が進んでおりませんが、エビや蕎麦の「抗体」ができるのには十数年かかるのでは、といわれています。
一度「抗体」が出来てしまうと火を通しても受け付けなくなり、これらは抗体ができたかどうか発症するまでわからないので、例えば1歳の時に検査して大丈夫だったとしても油断しないようにしましょう。少なくとも3歳までは絶対に避けたいもので、もう少し厳しい基準にすると解毒器官である肝臓が完成する8歳ごろまでは、極力与えないようにするとよいでしょう。
避けたほうがよい食材4:刺身・なまもの
お刺身は消化が悪いので、戦前の日本では昔から「6歳までは与えないように」といわれてきたものです。またカリウムも多く含むので体や腸を冷やしやすいです。未発見の新たな抗体の可能性もあるので、やはり3歳ごろまで待ったほうがよいでしょう。

昔ながらの日本食への回帰が、母子の健康に貢献した例

直近の半世紀を振り返ってみても、日本人の食事の常識や赤ちゃんの離乳食の常識などは、非常に大きく変わってきました。それらの新しい内容には疑問を感じるものも数多くありますが、そこに、国や大企業の意志が動くと急速に広まっていくもので、いつの間にかそれが現在の「常識」となってしまうのです。
当時、現在の食育常識や離乳食常識に疑問を抱く栄養学や教育の専門家がたくさんおり、「日本に新しく入ってきた海外の流行やブームよりも、私たち日本人が慣れ親しんできた当たり前の食事をもっと見直そう」という説を提唱していました。
そして、一般のお母さん達の中にも、その説に賛同する人が多数おり、乳腺炎や子どものアレルギーのトラブルでどれだけ病院に行っても治らず苦しんでいたのが、専門家の指導に従って昔ながらの日本食に切り替えたところ見事に改善した方々がたくさんいました。
自然育児の提唱者は「こどもの発達に従って、適切な時期が来てから、段階を経ていろいろな食材にふれ合わせるべき」と考えています。小さな子どもにワサビやトウガラシを食べさせたりしないのと同じことです。しかし、それが今の小児科学会や皮膚科学会では「除去食」や「食事制限」と呼ばれてしまい、また最近のお母さんには、昔ながらの「当たり前の日本食」を「極端な食事制限」だと認識されてしまうことが多いようです。
お子さんが成長されるまでの数年間、ご家庭の献立を日本食にしてみるのもおすすめです♪

まとめ:子どもの様子をよく観察して、その子にあった適切な食事を

子どもにとって、その食材が必要かどうか、正しい回答はマニュアル本の中などにはなく、すべてわが子の中にあります。
子どもの表情を見てください。元気に動き回る様子を見てください。毎日、心を砕いて詳細に観察していればわが子が健康かそうでないのかは母親が一番わかります。子どもは一人一人違うのです。「わが子」の「いつもの様子」について一番詳しいのは医師ではなく母親です。
おっぱいを欲しがって泣くならば、与えて正解なのではないでしょうか?必要が無い時期が来れば与えずとも泣かなくなります。
「本当に必要が無い時期」には母乳の出も少しずつ自然に減少していき、乳腺炎などのトラブルの心配もなく自然に卒乳できるものです。
「自然の摂理」を無視する事から様々な育児トラブルは発生しているのです。また、比喩的な意味において、育児に大変悩んでおられるタイプのお母さまは「わが子を見つめている時間」よりも「育児書を見つめている時間」の方が長いことが多いのではないでしょうか。
本に載っている平均値は自分の子どものデータではありません。わが子にとっての適切な食事を与えている時と、体に不要なものを食べさせている時では、子ども達の顔つきや目つきが違ってきます。慣れてくると、わが子の様子を見ることで、栄養が十分に足りているのか、体に悪いものを食べさせていないか、判断できるようになってきます。まずは、お子さんの食事から「体に不要なもの」を少しずつ減らしていきましょう。
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #幼児食 #離乳食 #安全

.jpg&w=256&q=75)






.jpg&w=256&q=75)



.png&w=256&q=75)