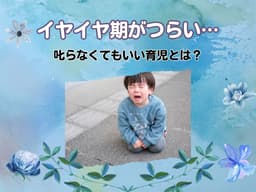「社会性」の定義とは何か?
「子どもの社会性を育てることが重要」ということばをよく耳にしますが、実は「社会性」の正確な定義というのは本当は存在せず、100人の学者や研究者がいれば100通りの「社会性」の定義があるのが現状です。
一般的には「集団を作って生活しようとする人間の根本的性質」や「社会生活を営むうえでの資質や能力」として定義されることが多いです。
発達心理学から見た「社会性」
ここでは「心理学的判断基準」において、社会性発達の一応の目安とされている項目を元に解説いたします。
「発達心理学」では社会性の具体的な中身、つまり子どもの各成長段階に対応した発達課題として「対人行動」「集団行動」「社会的欲求」「社会的関心」の4項目を定めています。
発達課題①【対人行動】
1つめの「対人行動」は“他者・他人に対して適切な対応ができること”です。個人対個人の関係で上手く相手と心を通わせる能力ですね。
発達課題②【集団行動】
2つめの「集団行動」は“集団の中で協調的に行動できること”。すなわち「グループ内での自分」というものを適切に判断し、メンバー達とうまく調和する行動がとれる能力といえるでしょう。
発達課題③【社会的欲求】

3つめの「社会的欲求」は“仲間から好意を受けたい、仲間として認められたい、という欲求を持つこと”。正に人間の本性(本能)です。
子どもは愛情の欲求などが満たされ、かつ脳の海馬や扁桃体も含むA10神経群(感情をつかさどる中枢)が適切に育っていれば、精神年齢が3歳を過ぎるころから「誰かに認められたい・褒められたい」という気持ちと、人に認められることによって「自分自身でも自分を尊重したい」という気持ちの、2種類の「自我尊厳の欲求」が健やかに育っていきます。
ですが、“謙遜が美徳”とされる日本では幼少期にお子さんの「自我尊厳の欲求」を「自慢」や「目立ちたがり」と判断して、ついつい潰しがちになりやすいので注意が必要です。心配しなくても、いずれ先ほどの「集団行動の能力」が年齢に応じて育ってきた時に集団の中での「自分の実力」を客観的に自己評価できるようになり、自発的に自慢などしないようになってきます。
むしろ幼いころに親に認めてもらえなかった子どもほど、いつまでも「認められたい・褒められたい」という欲求を引きずり続けてしまい、大人になった時に“自慢する悪習慣がすっかり身についてしまって直せない“という事があるので気をつけたいものです。
幼い頃にたっぷりと認めてもらった子どもは、大人になった時には他人に認めてもらうことに固執しなくなるものです。
ただしたっぷり褒めたとしても、子どもができないことを叱ってはいけません。親が子どもの「できる・できない」にこだわってしまうと、子どもも「できたか・できなかったか」だけに価値を置く人になってしまいます。
出来の良し悪しは関係なく、お子さんが純粋に「お父さん・お母さんに認めて欲しい」と思っている時には、それを敏感に感じとって、認めて、褒めてあげましょう。その経験を十分にした子どもは「社会的欲求」が豊かに発達します。
子どもをしっかり褒めてあげるということは、大人になってまで影響のあるとても重要なことなんだね。

発達課題④【社会的関心】
4つめの「社会的関心」は、“その時代、時代の情勢や風潮に関心を示すかどうか”です。これついては8歳くらいまでの子どもの教育ではまだ意識せずともよく、両親が時事問題に関心を持つ姿勢を日常的に見せておくだけでよいでしょう。
合わせて読みたい
「社会性」が育つみちすじ
それでは先述の4つの項目のうち、特に「対人行動」と「集団行動」の2つの発達を促すためのご家庭での取り組みについてお伝えしてきます。
まずは、乳幼児が社会性を正常に発達させていくうえで、どの子どもも必ず通る顕著な特徴を確認していきましょう。

乳幼児期の時期別にあらわれる「社会性」の特徴
◆【0歳初期】
それまで笑うことのできなかった赤ちゃんが初めて、人があやすと声を出して笑うようになります。
◆【0歳半ば】
人見知りの感覚が発達しはじめます。
◆【1歳前後】
褒められると同じ動作を繰り返すようになります。自分とは違う相手の存在を確認するために、相手の髪の毛を引っ張ったり、腕を叩いたりなどの行動も見られます。
◆【1歳半頃】
オモチャの奪いあいが見られるようになります。もしお子さんが自分からは人の物を奪わず他の子に取られっぱなしだとしても、それは自分と相手の発育の違いを感じとっているので非常に貴重な体験です。
犬が縄張り争いをする時、自分より圧倒的に強い相手とは争わないように、この時期の子どもも「相手が自分より体が大きいかどうか」「力が強いかどうか」などを感覚的に感じとっています。そして身体面や体力面の勝った子どもがその場において支配的となる関係を経験します。この支配関係は当の子ども達自身にはまったく自覚されません。
◆【2歳前後】
友達が自宅を訪ねてくれることや、友達の家を訪ねることを喜ぶようになります。また、「ここにいけば、いつもあの友だち達がいる」というような場所を好むようになります。さらに、親という権威に対して「イヤ!」と否定してみたいという感情が湧きはじめます。
◆【2歳半頃から3歳過ぎにかけて】
支配―被支配の関係が子ども達の中でも漠然と意識されはじめます。そして立場の強い子の心に、立場の弱い子を助けようとする感情が芽生えはじめます。
◆【3歳以降】
能力的に近い子ども同士の間で頻繁にケンカがみられるようになります。これは遊びの仕方やルールを十分に理解できていなかったり、自己主張の方法が未発達だったりするためです。しかし、幼児期にこのケンカを通して友達関係を十分に経験することで、「自分の気持ちがどうやったら相手に伝わるのか」あるいは「どういうやり方では伝わらないのか」など、互いの主張を押し通すだけではなく「お互いが納得できる解決策を考え出す」といった、リーダーシップのスキルも発達していきます。

「社会性」を育てるために注意するべきこと
上述の特徴はその年齢の時期だけに限るというものではなく、たとえば1歳半頃に目立ってきた「オモチャの奪い合い」は、その後数年に渡って継続することになります。
ここでもし、お母さんが厳しく叱りつけて「友達のオモチャを取らないの!」とムチのモチベーションを使ったとしたら、その子は「オモチャを取らない子」にはなるでしょう。しかしそれは、「お母さんが怖いから、自分の欲求を無理に抑制している」だけで、「オモチャの取り合いから学ぶべき能力」は、「オモチャの取りあい」を十分に経験しなかったら何歳になっても本当の意味では育たないのです。
子どもは実に、オモチャを取ったり取られたりする経験から「自分が取られた時の嫌な気持ち」も「自分が取ってしまった後に、相手の悲しそうな表情を見た時の気まずさ」も学ぶのです。そして「取られた時の痛み」も「取ってしまった時の痛み」もわかるからこそ、他の場面でも「絶対に相手を悲しませないようにしたい」という明確な意志が自分自身の本当の心として芽生えるのです。
ですから乳幼児期に社会性の発達を適切に促すには、先述のような「他人の髪の毛や腕を引っ張る」「オモチャの奪い合い」「支配―被支配の関係」「能力が近い子どもとのケンカ」などを経験するという事柄は大変重要なのです。
しかし、最近の育児事情ではこのような行動をわが子が取ろうとした時、相手のお母さんとのトラブルや、「しつけの悪い親」と思われるのを避けようと、たいていはお母さんが先回りしてその状況を回避することが多く、先程のような経験を与えることはかなり難しくなってきているといえます。

子どもの欲求を無理に抑制すると「社会性」が育たない
とはいえ、やはりこれらの経験は子どもの社会性が発達するために必要な道筋ではないでしょうか? というのも実は現在、これらの乳幼児期にするべき行動が小学生や中学生の間で頻繁にみられるからです。知能や知識の面において非常に優秀な子どもが、行動面では実年齢よりも幼い、ということが多く起きています。
これは実際にあった話ですが、小学生の全国模試でも上位成績で某有名中学にも受かるような子ども達が、小学4年生になっても授業中に机や教室の後ろのロッカーに登るということをしていました。
そこで担任教師は、そのような子ども達にクラスの“掲示物係”に立候補するようにアドバイスをし、係の仕事として堂々とロッカーの上に登れる立場にしたり、国語の授業で「青空」をテーマにした詩があれば、時にはジャングルジムの上で授業をしたりしていった結果、2学期ごろにはどの子もすっかり落ちついて、もう決して机に登ったりせず問題行動が一切なくなるなどの効果があったのです。
その子達はみんな、2~3歳のころから非常に良い子として厳しくしつけけられ、その本性(本能)を心の奥底に抑え続けてきた結果、それがある時期に爆発してしまったようでした。小学4年生くらいで爆発できた子はまだよく、中学校以降も引きずり続けてずっと親の期待する良い子の仮面を被り続けている子は、高校や大学時代に「親の前での自分」と「自分の本当の気持ち」の間でかなり苦しい葛藤を経験してしまいます。
そのため、ベビーパークではお母さま達に「幼稚園や小学校で机に登る子どもにしないためにも、いま机に登りたがる欲求を無理に抑制しないでください」とお願いしています。
つい注意してしまいがちな困った行動でも、本能からくる欲求を抑え込まないことがその後の成長につながってくるんだね♪

子どもがケンカをしてもトラブルにならない関係のママ友を作る

先述のごとく現代の育児事情では「オモチャの奪いあい」「どの遊びをするかでケンカをする」などの経験ができる環境を作りだすのはなかなか難しいことです。
ですから子ども同士がケンカをしても絶対にトラブルにならないママ友の存在は、本当に貴重な「宝もの」です。どうぞ、そのような関係のご友人を一人でも二人でも増やしてみてください。その数が多いほど、お子さんの「対人行動」のみならず「集団行動」のスキルもよりよく育てることができます。
いかがでしたでしょうか?
より具体的な各ご家庭での子どもの社会性の育て方については、コラムNo.142「脳の性差を理解して、子ども社会性の発達を促す方法について」で詳しく解説しています。
よかったらあわせて読んでみてくださいね!
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児


.webp&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)




.jpg&w=256&q=75)




.png&w=256&q=75)