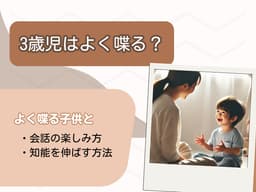2歳児が言葉を話す時期について
一般的には2歳ごろから言語を話すようになりますが、個人差はもちろんのこと、発達の目安やきっかけも違ってきます。
言葉が早い、逆に遅いのは大丈夫なのでしょうか?
2歳の子どもの「言葉の発達目安」ってどれくらいなのでしょうか?
どうすればもっと話すようになるのでしょうか?
このコラムでは2歳の言葉の特徴や、言葉を楽しく練習する方法をご紹介します。
合わせて読みたい
2歳児の言葉の特徴
2歳児では「ママバイバイ」「パパいない」「アンパン、きた」というような2語が出てくるようになります。また、話せる言葉の数が増えてくる他にもこんな特徴があります。
- 質問が増える
「これは何?」「これは?」など質問をしてきます。 - 名前に興味を持つようになる
ママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、友だちの区別がつくようになり、お友だちの名前がわかるようになります。 - 上、下などの理解ができるようになる
空間把握もこの時期から始まっていきます。
話し方の特徴
「指差し要求」や、身近な人の言葉を「真似」するようになります。単語で話す子どもも多く、「やって」「とって」「りんご!」「みかん!」など、とって欲しいものを指しながら要求します。ママやパパといった身近にいる人の話し方を真似したり、テレビの言葉や歌を覚えたりして話す子どももいます。
また語彙の目安として以下の通りです。
| 24ヶ月(2歳) | 30ヶ月(2歳半) | 36ヶ月(3歳) | |
|---|---|---|---|
| 語彙の目安 | 200~300語 | 400~500語 | 1,000語 |
| 言葉の特徴 | 二語文 | 二~三語文 | 三語文 疑問文 質問文 |
発音の特徴
舌もあごも発達段階、まだまだ何を話しているかわからない言葉も多い時期です。幼稚園や保育園で多くの人と関わるようになると、話し始める子どももいます。
「舌がうまく使える」、「あごの発達が良い」と滑舌もよく、聞き取りやすい言葉が出やすい傾向があります。あごを使う食事をとらせ、舌で遊ぶ練習をしてもよいでしょう。徐々に発達しますので焦りは禁物です。また、舌の奥の筋が舌を引っ張っていると滑舌が悪い場合もあります。治療も可能なので、病院に相談してもよいでしょう。言葉の間違いや滑舌を都度注意すると、子どもは話すのを嫌がるようになりますので、ゆっくりと見守りましょう。
男の子と女の子の言葉の発達度合い
男の子と女の子では言葉の発達は違うの?
一般的に女の子の方が早く話すようになる傾向があるのは、言語をつかさどる脳がより早く発達するためといわれています。しかし、性格や家庭環境の違いもあり、よく喋る子ども・喋らない子どもといった差は男女差なくありますので、あまり気にしなくても大丈夫です。「物に名前がある」、「人に名前がある」といったことがわかるようになっています。理解が早い子であれば、要求されていることを言葉で理解しているでしょう。
合わせて読みたい
言葉の発達トレーニング
パパ・ママが育児の上で取り組める言葉の発達方法をご紹介します。
言葉の発達を促すポイントは褒めてあげることだよ!「よくできたね」「上手に言えたね」って褒めてあげよう。
.png&w=256&q=75)
・本を読む
<コツはまずは褒めてあげること>
子どもが話そうとしているのを遮るのは、やめましょう。また、間違った言葉を使った際に毎回止めたり叱ったりすると、話すのをやめてしまう場合もあります。
「ブーブー」や「バイバイ」しか言わなかったのに・・・いきなり喋る量が増えた!もしかしたら、それは「言葉の爆発期」かもしれません。
言葉の爆発期とは、「今まで脳にストックされていた言葉」を急に発するようになる、巧みに操るようになることを指します。爆発期は子どもの成長過程の一環で、男の子に多い傾向があります。

2歳半ころの子どもの言葉の特徴
2歳半ころの子どもの言葉の特徴を紹介します。
- 子供の生活環境によって言葉の発達に個人差がでやすい時期です。
- 子どもの性格や癖も、言葉を発する数に影響します。
- 大人の表情や話し方から相手の動向を読み取る子どももいます。
- 1語が出て、自分の欲求を行動でも伝えられているのであれば問題ないでしょう。
2歳半になると、大人と会話をするくらい言葉の発達がみられる子どももいますが、まだまだ赤ちゃん言葉(喃語)を織り交ぜて話す子どももいます。単語だけしか発しない子どもから、3語以上の文を話せる子どももいて、個人差が大きい時期です。兄弟がいたり、保育園に通っていたりと、子どもの環境によって刺激が変わり、発する言葉には差があります。
言葉の発達が遅いと思っても心配しないで。でも子供に○○をしてあげると言葉の発達が促せるよ。みんなは知ってる?
言葉の発達を促す方法を知る>>

またこの頃は、「思っていることが伝わらない」と癇癪を起こしやすい時期でもあります。癇癪を起こすと何を言っているのかわからない言葉を発して、大人をびっくりさせることもあります。あごや舌の発達によって、徐々にハッキリとした発音で言葉を話せるようになってきています。濁音もハッキリしてきます。

2歳半ごろの子どもは舌や顎の発達がみられますが、それでも未発達の状態です。
発音のよさは、個人差が大きいといわれています。物の形を理解し、覚えているので、大人が思っているよりも多くの言葉を理解し、発しているでしょう。ただし、大人目線で単語を使っているかは、脳・舌や顎の発達にも関係があるので、発音によっては大人が理解できないことが多くあります。
言葉を発する数が少ないのは、子どもの性格や癖なども影響します。単語などの言葉自体が出ていれば、あまり心配することはありません。全く話さないといった状態で気になる場合は、地域の療育相談や専門医を受診しましょう。
2歳半になると、子どもと意思疎通ができる場面も増えてきます。
では、大人の言っていることをどれくらい理解しているのでしょうか?2歳半になると相手の表情・言葉・行動を合わせて、たくさんのことを理解しています。勘がよい子は、言葉だけではなく、大人の表情や話し方から相手の動向を読み取っています。怒っているようであれば近づかないようにしたり、笑顔の人にはついて行ったりしますよね。
2歳半になっても、言葉がなかなか出てこなくて心配だというパパ・ママは、1語が出て、「ご飯」「みかん」など欲しいものが言える、自分の欲求を行動でも伝えられているのであれば、まずは問題ないでしょう。比較的、男の子の場合3歳ごろになり集団生活が始まると急に話し始める場合もあります。同年代のお子さんとの交流を増やしてみたらいかがでしょうか。
合わせて読みたい
なかなか言葉を話さないときは?
言葉の発達が遅れる要因
周りの大人が手をかけすぎると、自分の欲求が全て整っている状態のためあまり言葉を発しない子どももいます。また、聴力に障害があると聞こえが悪く言葉を発しない場合もあります。音に対する反応が鈍い、呼んでもなかなか気がつかない場合は、聴力障害の可能性があります。
言葉の遅れだけでは一概にはいえませんが、以下の特徴がみられる場合は、集団生活を始める前に専門家に一度相談してみてもよいでしょう。
- 一人遊びを好む
- ごっこ遊びが広がらない
- 他の子どもに関心がない
- 1つの事だけに異常に興味を持つ
合わせて読みたい
誰に相談すればいい?
小児科、もしくは地域の児童相談などで専門家を紹介してもらうことができます。
2歳半~3歳になると言葉もなめらかになり、ちょっとした会話も成り立つようになってきます。そして、自分で物事を考える力、思考力もしっかり身に付いてくる頃です。ひとりでできることも増えてくるので、できた時には「できたね!」とたくさんほめることも大事です。たどたどしかった話し方も、ずいぶんとなめらかにしゃべることができるようになり、名前を聞かれたときなどは自分で答えられるようになってくる頃です。
ベビーパークの教室でも言葉の発達の相談ができるよ。悩んでいる親御さんは近くの教室にぜひ来てね。
.png&w=256&q=75)
少し長い会話の内容でも最後まで聞いていられる力がついていきますので、「ダメ!」「やめなさい!」などの短い言葉だけなく、「今日は、もう遅いからお家に帰ろうね」など、きちんと理由を説明するように心がけましょう。
この時期の子どもたちは、今までにママや周りの人からたくさん話しかけてもらって、心の「タンク」に大事にしまっておいた言葉がいっせいに飛び出す頃です。
子どもたちは尋ねることで、言葉の世界、知識をぐんぐん広げていきますので、子どもの「なあに?」には、できるだけていねいに答えてあげてあげましょう。イチゴのケーキを見て「これなあに?」と聞かれたら「ケーキよ」と一言で返すのでなく、「赤いイチゴがのっているね。あまくておいしい食べ物で、ケーキっていうんだよ。おばあちゃんがくれたんだよ。」などと言葉のおまけをつけると、言葉の世界も広がり、その言葉のおまけからまた新たな「なあに?」「なぜ?」につながっていくのです。
合わせて読みたい
子どもからの質問があまり長く続くようなら、「なんでかな?○○ちゃんはどう思う?」と聞き返し、子どもに少し考える時間を与えてあげてもいいでしょう。
食事の基本は、「からだを作る」「栄養を摂る」ことはもちろん、「楽しく食べること」も大切なことです。お箸の使い方、食べ方の指導など、注意ばかりにならないように、気をつけましょう。 お箸を使うときは、振り回したりすると危険ですので、ママや大人がしっかりサポートしましょう。
また、生活のリズムをこの時期から心掛けておくと、幼稚園へ通う頃にとてもラクです。トイレトレーニングの前に、ぜひ生活リズムを整えてみましょう。
自分の気持ちを言葉で上手に表現できない子どもたちは、お絵かきの中に自分の気持ちを表す場合があります。ぜひ、子どもが何を描いたのか聞いてみてください。この時期の子どもは、集中すると1日に何十枚と描く子どももいます。子どもたちが自由にお絵描きができるよう、紙とフエルトペンやクレヨンなど、描きやすいものを用意してあげましょう。この時期の子どもたちは、道具を使ったり細かい作業をすることに興味があるので、遊びに取り入れてみましょう。指先を使うと、集中力も自然とついてきます。
温かく見守る姿勢が大切
絵本を読んであげることは、お話の世界を一緒に楽しむだけでなく、子どもが親のぬくもりを感じ、ほっと安心するひと時でもあります。子どもが絵本に集中するのは、せいぜい10分か15分。お子さんが「絵本を読んで!」と言ってきた時は、食事の支度や掃除などの手を止め、ぜひ絵本を読んであげましょう。
絵本を読んであげる時間にとくに決まりはありませんが、寝る前に絵本を読むようにしたら、眠る習慣ができたというお母さんがいらっしゃいました。毎日、同じことを繰り返すことで、習慣づけになったようです。
絵本の読み聞かせは、いつからスタートしても遅いということはありません。これまで、あまり絵本を読まれなかった方も、ぜひ、今日からスタートしてみてください。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #2歳 #言葉 #話す #いつから #対応
.jpg&w=2048&q=75)


.jpg&w=256&q=75)



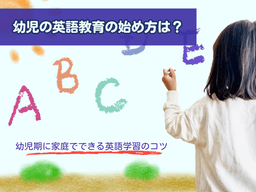
.png&w=256&q=75)