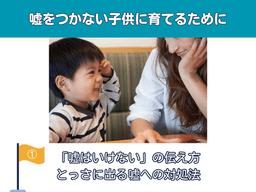子どもが嘘をつくことは知能発達の通過点であり心配する必要はない
近年「子どもの嘘」に関する研究が、欧米や中国を始め世界各国で進み始めています。
そしてどの研究でも共通していわれていることは、「子どもが嘘をつくことは、子どもの知能や道徳観が正常に発達する上で必ず通る通過点」ということです。ですから、わが子が嘘をついたからといって、少しも驚いたり心配したりする必要はありません。
ただし、大人の対応の仕方は子どもの発達のために非常に重要
しかし子どもの嘘に対して、大人がどのような対応をするかは非常に重要です。
それは、子どもの認識力や道徳観を正しく発達させることの鍵になると考えられています。子どもが嘘をつかない誠実な人物に育つか、嘘を嘘で塗り固めるような嘘の常習者に育つかに対して、親の与える影響は大変大きいことを検証する研究が進められています。
ですから私たち親は、「子どもが嘘をつくのは当たり前」と大きな心で構えつつも、子どもたちが誠実に育つよう適切に対応をする必要があるのです。
お子さんが嘘とついていると感じたときにビックリするかもしれませんが、これは成長の通過点なんです。

多くの子どもが嘘をつくもの
子どもの嘘についての研究の第一人者であるカナダのタルワー博士によると、子どもが嘘をつき始めるのは知能発達の早い子で2歳、そして3歳になると全体の3分の1の割合の子が嘘をつくようになるとされています。
4~7歳になると半数以上が嘘をつく経験をもちます。この時期の嘘の理由は、「叱られないため」「相手の注意を惹きたいため」「許可を得たいため」のいずれかに分類できると考えられています。

親は子どもの嘘を意外と見破れない
また同時に、「親は子どもの嘘をあまりうまく見破ることはできない」という研究結果もでています。6歳以下の親子を対象とした実験では、親が子どもの嘘を見破ることができたのは全体の53%でした。これでは運任せの二者択一よりほんの少しだけよい数値に過ぎません。
6~8歳になると嘘を見抜ける確率は33%とますます減少し、9~11歳になると25%まで下がります。つまり小学校高学年ごろになると、親が子どもの嘘を見抜ける確率は4回に1回、残りの3回はだまされてしまっていることになります。
子どもの嘘を見破れないことが子どもの成長にもつながっている
その理由として、研究者は「親は子どもに対して『誠実さの先入観』と呼ぶべき観念を持っているから」としています。つまり、親は子どもが本当のことを話していると信じたいという強い思いを元々持っているということです。そして「その思いを持つことは必要でありよいことだ」と考えられています。
4回のうち3回はだまされるということは、見方を変えれば「4回のうち3回は子どもを信じぬいた」ということになります。しかし、9歳ごろまでに子どもの精神が順調に健康的に育っている場合、自分を信じてくれている親を裏切ってしまっているという気持ちは子どもたちの心に大切な何かを学ばせます。
子どもが親の愛情と信頼を強く信じきっていれば、その大好きなお母さんお父さんに嘘をついているという思いは、強い良心の呵責を生み出します。
しかし、9歳ごろまでに親が普段から「どうせまた嘘でしょう」「約束したって守れないじゃないの!」など、子どもに「自分は信じてもらえていない」と刷りこんでしまうような声がけを続けていると、嘘をつくことに対して抵抗感も持たない子になることも少なくありません。つまり、幼児期に親が子どもの嘘を見抜いて指摘する時と、例え嘘であろうとも信じぬいてあげる時の比率が半々というのは、絶妙なバランスともいえるのです。

親に嘘をつかない子どもに育てることは非常に重要
幼稚園や学校に通い始めると、親は子どもの日中の生活に目が届きません。そして先生たちがどんなに頑張ったとしても、すべての子どものすべての時間を把握することは絶対に不可能です。ですから、子どもがなんらかのトラブルに遭遇した時、それをいち早く察知する情報源は子どもが親に素直に相談してくれるかどうかなのです。
しかし、ほとんどの小学生は学校でのトラブルをあまり親に話しません。早いと幼稚園の年中くらいから話さなくなる子もいます。ですから、親に嘘をつかない子どもに育てることは非常に重要といえるのです。
何でも親御さんに話してくれるお子さんに育ってくれると安心ですよね♪

子どものうちに嘘をつくことで、誠実さの重要性を知ることができる
嘘をつくことに抵抗のない大人に育ってしまうと、他人から信頼を得ることが非常に難しくなります。誠実さのない人物には本当の友人はできにくいものです。「自分を信じてくれる人がいる」という思いは人の心に大きな力を生み出します。
子どもは誰でも当たり前に嘘をつきます。それは、嘘をつくことが自分にどれだけの不利益をもたらすのか、誠実であることが自分をどれだけ幸せにするのかを、自分の五感と感情を伴った確かな経験として時間をかけて学ぶためなのかもしれません。すなわち、生きた問題解決学習を日々おこなっているともいえるでしょう。「誠実さ」が自分にもたらすものの大きさについて子どもと話し合う機会はとても貴重です。何か一つを学ぶにも多くの時間がかかるのだと理解し、子どもの成長を根気よく待ちたいものです。
「自分をかばう嘘・自分を大きく見せる嘘」について
さて、ここからはコラムNo.82「子どもが嘘をつくのはなぜ?~2歳半からの幼児期の子どもの嘘の特徴について~」でもご説明した、子どもに見られる嘘の15種類の分類のうち「自分をかばうためにつじつまを考えながらつく嘘」への対処法についてを中心に詳しく解説していきます。
ちなみに嘘の15分類は以下になります。
相手をだます気がない嘘
1.空想が膨らんで現実と混同してしまう
2.話をよく理解していないためおかしな回答をする
3.表現力〔語彙〕不足のためうまく意思を伝えられない
4.言葉遊び
子ども自身が「嘘をついている自覚のある」嘘(=親としての対応が必要)
5.願望が大きくなって現実と混同してしまう
6.怒られないようにとっさに出る嘘
7.自分をかばうためにつじつまを考えながらつく嘘
8.相手の気を引いて自分に注目してもらいたい
9.本当の自分の気持ちを理解してもらえないいらだち
10.根ほり葉ほり聞かれる面倒を避けるため
11.立場の強い子からの口止め
12.仲間をかばうため
13.親の期待に応えて喜ばせるため
14.ねたみや復讐
15.相手の心を傷つけないため

子どもがつく嘘のパターンの中には、「自分をかばうためにつじつまを考えながらつく嘘」「願望が大きくなって現実と混同してしまう嘘」があります。親の努力の甲斐あって、怒られないためのとっさの嘘がかなり少なくなってきたとしても、知能の発達に伴って、今度は「自分を実際よりも大きく見せたいときにつく嘘」が見られるようになってきます。
自分をより良く見せるために罪のない範囲で物事を誇張して話してしまうというのは、実際大人でもよくあることです。また、「自分をかばうためにつく嘘」というのは、怒られないように言い訳の嘘をつく場合と、このように自分の劣等感を刺激しないための嘘をつく場合の両方にあてはまります。
「自分を大きく見せる嘘」への対処法
この「自分を大きく見せるための嘘」とは、親としてうまく導かなければならない教育課題の一つだと考えます。幼い頃には本人の中に嘘をついている意識がないため、強く叱るような対応は避けます。
しかし、自分を大きく見せたい気持ちが不自然な方向に高じてしまうと、大人になってから深刻な病的症状を示す場合も少なくありません。劣等感を克服する努力を避け、架空の理想化された自己像を作りあげるようになると、俗に虚言癖といわれるような言動をとってしまう事例も多く報告されています。
「自分を大きく見せる嘘」の現れ方
「自分を大きく見せるための嘘」は、最初のうちは純粋に「ボクはすごいんだぞ」という気持ちから生じてきます。例えば「自転車よりも速く走れるんだぞ」「お相撲で10人に勝ったよ」などです。
幼稚園に入る頃になると、空想と現実の区別ははっきりついてきますが、今度は具体的な数字と実際のイメージが結びつかず、適当に大きな数字を言うようになります。しかし子どもは適当な数字と適当な単位を言っているだけで、これまた嘘をついているという意識はありません。
ですから、幼児期の子どもがなんだか大げさな自慢を言っていると感じても聞き流します。

本人には自慢のつもりも嘘のつもりもありません。大人になってからの虚言癖というのは、その大半が強い劣等感から自分の精神を守るために生じていると考えられています。ですから、幼少期に劣等感を植え付けるような対応は逆効果とも言えるでしょう。
子どもの「大げさな自慢」が目立ってくるのは幼稚園の年中ごろからです。謙遜が美徳とされる日本ですから、「何を言っているの!そんなことできないでしょ!」と指摘して子どもの言葉を否定してしまいがちです。
成長に伴い「自分を大きく見せる嘘」は自然と減っていく
子どもが同年齢の友だちの中での自分の本当の能力に気づき始めるのは、大体小学校へ入学する頃です。親がいうまでもなく、いろいろなジャンルにおいて、よくできる友だち、苦手な友だちの様子が認識できるようになり、自然に自分の位置もわかってきます。
その頃になると、友だちの前で能力以上の自慢などすれば「お前何を言ってるんだよ」と仲間から指摘され、次第に大げさなことは言わなくなってきます。その時期がくるまでは、子どもが少々大げさな嘘をつこうとも、親は笑顔で「ふうん、そうなんだ~」と腹を立てずに気楽な気持ちで聞いてあげると良いでしょう。
今回のコラムでは、「自分をかばう嘘・自分を大きく見せる嘘」への対処法を中心にご説明してきました。この次のコラムNo.130「嘘をつかない子供に育てるために③~「他人を思いやるためにつく嘘」への対処法~」では、さらに子どもが成長してきた際にみられる「他人を思いやるための嘘」について詳しく解説していきます。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #子ども #嘘

.jpg&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)