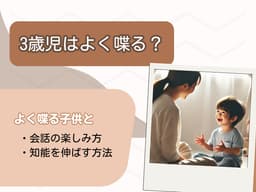叱らない育児を推奨する理由は?
子どもを叱らずに育てる、… それが「理想」だとみんな思いながらも 「現実」はそういう訳にはいかない…と、これまたみんなが悩んでいるものです。「叱らない育児」、本当にそんなことが可能なのでしょうか?
答えとしては、もちろん可能です。それどころか0~3歳期は、絶対に「叱るべきではない」といえます。もし子どもが本来秘めている本当の能力を豊かに引き出したかったら、「叱ること」は害になるばかりなのです。
しかし子どもを野放図なままに、ただ好き勝手にさせていて良いというわけではありません。そんなことをすれば知性も心も育たず、まるで野獣のような子どもに育ってしまうだけです。
では「叱らない育児」を成功させるためにはどうすれば良いのでしょう?
してはいけないこと、危ないことなど、育児をしているとつい叱りたくなる場面はたくさんあるよね!どうしたらいいのか見てみよう。

子どもを「叱る」目的をまず考えてみる
「叱る」目的を考えてみましょう。親は何のために子どもを叱るのでしょうか? 子どもに「よりよい人になって欲しいから」ですね。
では、叱る事によって身につけさせようとしているものは何でしょう?「行儀」「常識」「生活習慣」「心構え」といったところでしょうか。
すなわち、ある場所、ある時においての「望ましい行動習慣」や、何か困難に出会った時または他人との関わりあいの時の「望ましい思考習慣・心の動き方」を身につけてほしいと思って叱っているかと思います。
3歳未満の子どもは「なぜ叱られたか」を理解できない

それならば、子どもに「なぜ、叱られたのか」が確実に理解されなければなりません。しかし、平均的な子どもの発達では3歳の誕生日ごろまでは、子どもは大人が思っているほど物事の因果関係を理解できないのです。
確かに1歳なりの理解、2歳なりの理解はしていますが、それは大人が考えているのとはまったく違う驚くほど未熟な理解にすぎないのです。ですからなぜ叱られたのかが分からず、ただ不快な感情のみが残ってしまいます。
それは子供の成長にとってよくありません。3歳頃までは「記憶」「ことば」「心」の発達が大変未熟なので、言葉で叱ることは効果よりも弊害の方が多いのです。叱ることでは、教えたい事柄を身に付けるよりも、親の「イライラした話し方」「キツイものの言い方」「興奮して感情的に人や物へ攻撃を示す態度」など、望ましくない行動や態度を『模倣反射』(生まれつき子供が持っている本能)によって子どもが身に付けてしまうことになるのです。
3歳未満の子を叱ることは、百害あって一利なしといっても過言ではありません。
合わせて読みたい
叱ってもよい時期は、いつから?
では叱ってもよい時期というのは、子供がどのように成長した時からでしょうか?
1.子どもが「物の用途」を、自分なりの言葉で説明できるようになった時
「座るモノはどれ?」という質問に対して何枚かの絵の中から椅子を選べるというだけでは不足です。「椅子は何をするもの?」「お皿は何をするもの?」などという質問に対して、しっかりと自分の言葉で答えられるようになれば大丈夫です。
2.子どもが「物事の因果関係」を自分なりの言葉で説明できるようになった時
「水の入っているコップにぶつかって、コップを倒したらどうなる?」というような質問に、「水がこぼれる」と正しく回答できるところまで概念理解が進んでいれば大丈夫です。
3.お母さんと子どもの間に強い信頼関係が育っている時

叱る相手(お母さん)と叱られる相手(子ども)の間に、強い信頼関係、愛着の関係が育っていると確信のある状況でしたら、叱ってもお互いの関係には揺るぎがなく問題ありません。
この3つが達成されていれば「叱る育児」も適切なものになる場合があります。それまでは『叱る』ことに意味はなく、「恐怖」や「不快」という感情をより強く育ててしまう、という育児上の害を与えるばかりなのです。
1歳児に対し恐怖を与える叱り方で「決まった行動」を身につけさせることはできるでしょう。しかし、それでは恐怖の対象が無くなった時に好ましい行動をとれなくなってしまいます。また「叱られるから」というだけの理由で、行動するかしないかを決めてしまうことになりかねません。人間は犬や猫と同じようにしつけてはいけないのです。
合わせて読みたい
「叱らない」しつけを実践する方法について
ではどのように子どもをしつければよいのでしょうか?
本能を知性、理性でコントロールできる能力が育ってくるのは3歳前後になります。それまでは叱るのではなく、子どもの本能である「探究反射」や「模倣反射」を利用して「生活習慣」を整えていくのが望ましいです。
具体的には親が望ましい習慣の見本を日々見せ続けること、でしつけをしていくのです。
教育、すなわち人間を育てるためには、いろいろな技術があります。「褒める」「叱る」「手本を見せる」「感動させる」なども教育技術の一つです。 しかし、その中でも「叱る」という方法は、影響が凄まじく強いのです。「叱る」という技を使うためには、叱られる方に十分な準備ができていなくてはならず、高度な理解力も備わっていなければなりません。 叱る方も「叱り方」を十分に学んでいなければなりません。そうでなければ、それは躾ではなく親のイライラや不満をぶつけているだけになってしまいます。「しつけのための叱り方」というのは高度な技術であり、簡単ではないのです。
しつけたい内容は、まず親が実践を徹底することが大切

以下に具体的な実践の仕方をまとめていますので、ぜひ試してみてください。
まずわが子にしつけたい事柄をノートに書き出しましょう。
例えば、「早寝・早起き」「掃除・かたづけ」「脱いだ服をたたむ」「靴を揃える」「正しい茶碗やはしの持ち方」「姿勢のよさ」「あいさつ」など、いろいろ出てくるかと思います。
そして、それらを大人が徹底しましょう。
子どもにさせようと思う前にまず大人が実践するのです。指示・強制は反発心を育てるばかりです。子どもではなく大人がまず徹底的に自分の習慣にしていきます。
あなたは近所ですれ違った人にかならず大きな声であいさつをしていますか?
家の床にモノは落ちていませんか?
埃のたまっているところはありませんか?
家の中でいつも良い姿勢で過ごしていますか?
子どもにさせるのではなく、私達、母親・父親自身が自分自身を厳しく律する必要があります。それこそが、子ども達への最高のしつけの方法となります。子どもは両親の背中を見て学びます。 子どもは親の鏡…、というのは本当にその通りです。
しかし、いきなり無理をする必要はありません。子どもと違って、大人のほうが自分の習慣を変えるのははるかに難しいものです。ノートに書き出して文字に落としこみ、日々それを意識するだけでも人はずいぶん変わってきます。自分の生活習慣の中で甘くなっている部分を発見し、少しずつ理想に近づけていきましょう。時間はどれだけかかっても構いません。得意なことは今すぐにでも修正し、苦手な事柄は1年計画くらいで立て直していきましょう。
#ベビーパーク #キッズアカデミー #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #叱らない #育児 #しつけ #叱る #いつから




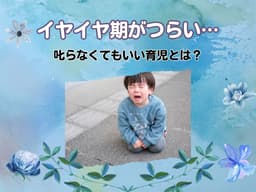







.jpg&w=256&q=75)