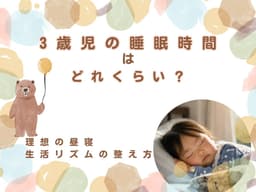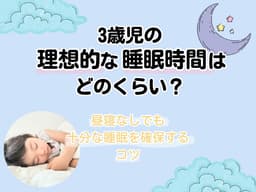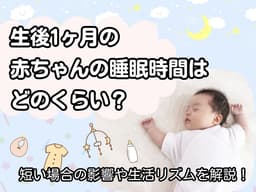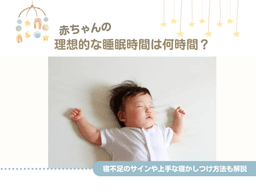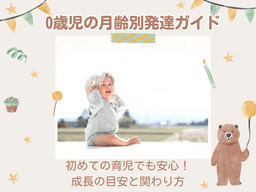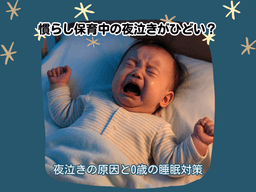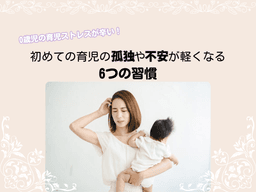新生児はどれくらい眠るの?
新生児期の睡眠時間としては、1日16時間から20時間といわれています。数字だけでみると1日のほとんどを眠っているように思いますよね。これだけ寝ているのにどうして寝不足に悩むお母さんが多いのでしょうか。
それは、お母さんが寝たいタイミングと赤ちゃんが眠っているタイミングが異なるからです。また、まだ眠り方が未熟なため、寝続けずに数分おきに細切れ睡眠の赤ちゃんもいます。それゆえ「あまり寝てくれない」と感じるお母さんも多いのでしょう。
新生児の睡眠サイクルは?
新生児期はレム睡眠とノンレム睡眠が大人よりも頻度高くくり返しおこなわれています。このレム睡眠時に「眠い」「気持ちが悪い」と感じると泣いて起きるのです。それが理由で長くても4時間程度、だいたいは40分ほどのサイクルで目を覚ますといわれています。
また、赤ちゃんは夜行性ともいわれていて、昼よりも夜に行動するようです。夜によく動く理由として、母乳促進を促すホルモン“オキシトシン”は夜中によく分泌され、母乳を促進させるために夜中に泣いてお母さんを起こすのではないかともいわれています。
新生児が寝ない原因

赤ちゃんが寝ない原因として
- お腹がすいている
- 不快感がある
- 寝付きにくい
- 心地よく眠れる環境ではない
という4点が考えられます。
レム睡眠時にこの寝づらくなる原因に遭遇してしまうと寝続けることができず目を覚まし、まだ言葉で表現ができない新生児は“泣く”ということで訴えるのです。
ここからはこれらの原因について詳しく解説します。
お腹がすいている
新生児期の赤ちゃんは1度にたくさんのミルクや母乳を飲むことができません。また飲んでいる途中で疲れて寝てしまい、十分に飲むことができないまま眠ってしまう赤ちゃんもいます。ですので、新生児期は夜中関係なく数時間おきに授乳が必要になります。
また、母乳の場合、母乳はミルクに比べ消化がよいので、初めのころは1時間未満でお腹がすくこともあります。そのためすぐに起きて泣くということがあります。
「母乳が足りないのかな」と心配されるお母さんもいらっしゃいますが、母乳が足りないのではなく、赤ちゃんが1度で飲める量が少ない、または消化がよくすぐにお腹がすくということも考えられます。
不快感がある
オムツがぬれて気持ち悪い、体に当たるシーツのしわが気持ち悪い、布団の温度が不快など赤ちゃんの不快感で眠れないということもあります。『新生児が寝ない原因』のはじめにもいいましたが、赤ちゃんは言葉で表現できないので、その不快感を泣くことで訴えているのです。
また、新生児はぼうこうにおしっこをためる量も少ないのでおしっこをする回数が多くなります。そのため、おむつがぬれる回数も多くなり不快に感じることも多くなるのです。特に布オムツで過ごしている赤ちゃんはダイレクトに不快感を感じるので、泣いて訴える回数も増えるでしょう。
一人では寝付きにくい
赤ちゃんの眠りは未熟なので一人でうまく眠れないこともあります。誰かに抱っこされて安心して眠っていますが、布団に置かれると『背中スイッチ』という布団に置くと目を覚ます現象が起きてしまうことも。抱っこしないと寝てくれないので1日中抱っこしているというお母さんの話はよく聞きます。
また『不快感』のところでもお伝えしましたが、オムツや布団など何か不快な状態であると寝付けないということも考えられます。

心地よく眠れる環境でない
光が明るい、音が気になる、暑い・寒いなど赤ちゃんが心地よく眠れる環境でないことも原因として考えられます。
室温に関しては大人では快適な室温でも、赤ちゃんにとっては寒い・暑いということもあります。衣服を着こませ過ぎ、布団などをかぶせすぎ、逆に寒くて何かバスタオルやブランケットを掛けて欲しいなど、子どもにとって実は心地よい状態ではないこともあり注意が必要です。
また、敏感な赤ちゃんはちょっとした物音ひとつで目をさましてしまったり、日光や照明の明るさで目を覚ますこともあります。
新生児の寝かしつけのコツ
新生児が寝ない原因がわかれば、対策もしていけるものです。具体的にあげていくと
- お腹を満たす
- 不快感を取り除く
- 抱っこなどして安心して眠れるようにする
の3点を対策していけばよいでしょう。眠りに快適な状況を作ることによって赤ちゃんも気持ちよく眠れるのですね。
お腹を満たしてあげる

お腹がすいていそうであれば、母乳やミルクをあげてお腹を満たしてあげましょう。原因の『お腹がすいている』のところでも述べていますが、赤ちゃんは1度にたくさん飲むことができないため、特に母乳の子はすぐにお腹もすいてしまいます。
たくさん飲めるようになれば、すぐにお腹がすくということもなくなってくるので「今の時期だけ」と数時間おきの空腹に付き合ってあげてください。
不快感を取り除く
上述のように赤ちゃんはぼうこうに貯められる量が少ないので、すぐにおしっこをしてしまいます。敏感な赤ちゃんは紙オムツを使用していても少しの濡れで気になり、目を覚まし泣いて訴えます。オムツが濡れていそうであればこまめに替えてあげましょう。
また、シーツがよれていないかなど寝具の状態を確認するようにしましょう。赤ちゃんにとっての快適な室温として、夏は26~28度、冬は20~23度と言われています。最近のお母さんは厚着をさせる傾向にありますが、夏であれば肌着とタオルケット1枚かけてあげることで十分です。それ以外の時期でも布団はブランケットやかけ布団などで大丈夫。着こませるよりも布団などで温度調節しましょう。
また、直接日光が当たったりエアコンの風が直接かかったりしないよう場所を調節してあげることも大切です。
抱っこなどして安心して眠れるようにする
原因のところでもお伝えしましたが、お母さんが抱っこしていると眠っているけど、布団に下ろすと泣いて目をさますという経験はありませんか。赤ちゃんは抱っこされていると肌のぬくもりを感じて安心して眠れるようです。
そういった意味では添い寝をすることは有効です。ただ布団が顔にかかったり、お母さんが寝返りをして赤ちゃんに覆いかぶさってしまうという事故が起こっているので、安全面には気をつける必要があります。
合わせて読みたい
新生児の生活リズムをつけるためにできること
新生児期は昼夜の区別がなくどのような時間帯でも寝たり起きたりをくり返します。まだ「昼にたくさん眠ると夜寝なくなってしまう」と無理やり起こす必要はありませんが、“生活リズム”をつける基盤を作っていきましょう。
そのために
- 太陽の光を入れる
- 生活音は極度に気にしない
- 活動する時間を作る
の3点に気をかけてみるのがポイントです。新生児期から、きちんと昼間と夜の時間があり夜は寝る時間だということを知らせていくことも大切です。

太陽の光を入れる
まだ、昼夜の区別がついていない新生児期ですが、昼間と夜の違いがあるということを知らせていきましょう。朝になったらカーテンを開けて太陽の光をいれて部屋を明るくするとよいでしょう。
新生児期は体内時計のサイクルがきちんとできていません。しかしこういったはたらきかけをしていくうちに、明るい時間は活動する時間だということを覚えていきます。次第に昼夜の区別がついて、夜にしっかりと眠れるようになってくるでしょう。
生活音は極度に気にしない
音に敏感でちょっとした音でも目を覚ましてしまう赤ちゃんもいるでしょう。起こしたくないからと無音の中で生活しているご家庭もありますが、音を出せない生活もストレスになるのではないでしょうか。
歩く音や物を動かすなど少しの生活音に慣れることも必要です。音に敏感の赤ちゃんも次第に慣れていきます。当たり前の生活音は気にせずに過ごしていくようにしましょう。
活動する時間を作る
無理に起こす必要はありませんが、日中に目を覚ましていたら、抱っこしてみたり、スキンシップを取るなど活動する時間を作ってみましょう。日中は活動する時間だということを少しずつ認識するようなります。
また、日中に活動して起きるようになってくると寝る時間が夜にシフトしていき、月齢が過ぎていくと夜にまとまって眠るようになりますよ。
まとめ:お母さんも無理せず、家族で赤ちゃんの睡眠を支えてあげよう

新生児期は16時間から20時間眠っているといわれますが、大人と違いレム睡眠とノンレム睡眠が短期間に交互におこなわれているので、1回の睡眠時間は短く、その短い睡眠が何回も繰り返しおこなわれています。また、昼夜の区別がついていないことや、おっぱいを1回に飲む量が少なくすぐに空腹になることで、夜中でも何度も起きてしまいがちです。
昼夜の区別や飲む量は成長していくうちに改善されていきます。つらいかもしれませんが「今はその時期」と赤ちゃんに付き合うようにしてください。生活リズムが整ってくると夜眠る時間が長くなっていきます。
産後の身体は交通事故と同等のダメージを受けているといわれます。まだ体が万全ではないのに、夜も眠れず何度も起きてくる赤ちゃんに付き合い、授乳・オムツ交換・沐浴など赤ちゃんのお世話もしなければいけません。
基本的に産後はしっかりと休まなければいけない時期です。旦那さんなどのパートナーやお母さんなど身近な人に助けてもらったり、産後ヘルパーさんを利用することも重要です。母乳をあげる以外はお母さんの代わりに誰でもできます。
新生児のお世話は大変ですが、その分癒しもたくさんあります。周りのサポートを受けていきながら、体を戻しつつ今しか味わえない新生児との生活を楽しんでくださいね。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #新生児 #睡眠 #原因 #対策 #コツ