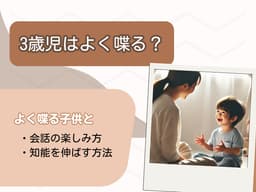発語はいつから?赤ちゃんが初語を話し始める時期の目安
赤ちゃんが発語を始める時期には「いつから」といった明確な基準はありません。これは赤ちゃんの言葉の発達に個人差があるためです。
なお大体の目安としては、平成22年に厚生労働省が発表した「乳幼児身体発育調査」の結果が参考になるでしょう。この調査では、1語以上の単語を発する乳幼児の割合が生後9~10カ月未満で9%、生後1年0~1カ月未満で50%以上、生後1年6~7カ月未満で90%以上となっています。
この結果からわかるように、生後9カ月~1年6カ月ぐらいまでの間に話し始める子が多いようです。ただし、話し始めには個人差があり、今まで喋らなかった子が2歳になって急に話し始めたという例もあります。「うちの子は他の子よりも話し始めが遅い」と発話を無理強いするのは逆効果となりますので、焦らずに子どもの成長を見守ることも大切です。
※出典:厚生労働省:乳幼児身体発育調査 調査の結果 結果の概要(平成22年)
ベビーパークに通っているお母さんの声の中で、子どもの言葉の成長に驚かれている方もいたよ!それだけ子どもの成長は早いんだね。
.png&w=256&q=75)
話せなくても大人の言葉を理解している
赤ちゃんに語りかけるとき、おのずと「ねんねしようね」「まんま食べようね」「ブーブーで遊ぼうね」と赤ちゃん言葉を使う人は少なくありません。こうしたときは、意識せずとも声のトーンが自然と高くなり、ゆっくりと抑揚豊かな口調(「マザリーズ」と呼ばれる話し方)になっているものです。
また、赤ちゃんはマザリーズを積極的に聞いているという研究報告があります。この研究では、生後4カ月の赤ちゃんの両側にスピーカーを置き、どちらか片方から大人の会話とマザリーズをランダムに流したところ、マザリーズを流したスピーカーの方を向く回数が多かったという結果が出たということです。この研究結果が示す通り、赤ちゃんは話せなくても、大人の話す言葉に関心を示して耳を傾けていると考えられます。
幼児の発達段階
赤ちゃんが話し始める時期には個人差がありますが、一般的にはどのような段階を経て言語能力が発達していくのでしょうか。
- 生後0〜1カ月頃
- 生後2~5カ月頃
- 生後6~11カ月頃
- 1歳~1歳半頃
- 1歳半~2歳頃
以下、月齢ごとの言語能力の発達段階をみていきましょう。
月齢ごとの言葉の発達を一緒に見てみよう!ちなみに言葉が遅い・・と思ったら○○をしていないからかも。
言葉が遅い原因を知る>>

生後0〜1カ月頃
.jpg&w=2048&q=75)
生まれて間もない赤ちゃんは声帯や喉が発達していないため、まだ声を上手く出すことができない状態です。
この時期の赤ちゃんが唯一できるのが「泣くこと」。この頃、赤ちゃんは大人に何かをして欲しいという意思はまだ芽生えていません。しかし泣くことによって、空腹や不快感、眠いといった生理的欲求を表現しているといわれています。
合わせて読みたい
生後2~5カ月頃
生後2~5カ月頃になると、唇や舌を使わずに「あー」や「うー」といった母音から始まる言葉を発するようになります。これはクーイングと呼ばれ、声を発するために必要な声帯や喉が成長してきている証です。
「あー」や「うー」とクーイングすることで何かの意思表示をしているわけではありませんが、赤ちゃんの機嫌がよいときやリラックスしているときにクーイングをするといわれています。
生後6~11カ月頃
生後6~11カ月頃では「あー」や「うー」といった単音のみのクーイングから少しずつ「喃語(なんご)」と呼ばれる声を出せるようになっていきます。
喃語とはクーイングとは異なり、2語以上の音を連続で声に出すことです。はじめは「あーあー」や「うーうー」といった母音のみですが、次第に「まぁまぁ」や「ぶぅぶぅ」と子音を含む声が出せるようになっていきます。この時期はまだ舌を使った発音が上手くできないため、両唇音と呼ばれるぱ行・ば行・ま行で始まる発音が多いのが特徴です。
1歳~1歳半頃
この頃になると、赤ちゃんは自分のまわりにある人や物には名前があるということに気づき始めます。まずは身近にある人や物の名前から覚え始め、一語文で意思表示を行おうとします。例えばお腹が空いたときに「まんま」と言ったり、目に映った犬を指さして「わんわん」と言ったりするようなことです。こうして自分の欲求や目にしたものを簡単な単語を使って表現しようとし始めます。
合わせて読みたい
1歳半~2歳頃

1歳半を過ぎると使える単語の数も増えてきて、二語文で簡単なコミュニケーションがとれるようになってきます。例えば「まんま、おいちい」や「ブーブー、どこ?」などです。
二語文が使えるようになると、単語同士の関連性が徐々に分かるようになるため、例えば「おやつ、食べる?」といった問いかけにも次第に答えられるようになります。またこの時期は自己主張が強くなりはじめ「まんま、たべない」や「おふろ、ないない」など否定的な表現も目立つようになってきます。
合わせて読みたい
話しかけるときのポイントは??
前述したように、赤ちゃんは話せなくても大人の言うことを理解しています。そのため話しかけるときは赤ちゃんが健やかに発達するよう、工夫してあげることが大切です。
ここでは赤ちゃんが言葉を喋りだすのを促す話しかけのポイントについて解説します。
合わせて読みたい
たくさん話しかける
赤ちゃんに毎日たくさん話しかけることは、赤ちゃんの脳の発達を促すよい刺激となります。子どもの発話に関する研究で、親が赤ちゃんにたくさん話しかけたグループは、あまり話しかけなかったグループと比べて、単語の習得に倍以上の差がついたそうです。また読み書きの習得も前者の方が早く、IQのスコアも1.5倍の差がついたとの報告もあります。
しかし単に話しかける量が多ければいいという訳でもありません。言葉と意味のつながりに赤ちゃんが気づけるよう、赤ちゃんの興味に寄り添って話しかけることが大切です。例えば、赤ちゃんが犬を指さしていたら「わんわん、いるね」という感じで、赤ちゃんの目線を意識しながら話しかけましょう。こうしたやり取りを繰り返すことで、赤ちゃんがコミュニケーションの楽しさに気づき、言葉の発達につながっていくのです。
ポジティブな言葉をかける
赤ちゃんが思った通りに動いてくれないイライラ感から、つい否定的な言葉を赤ちゃんに使ってしまうことがあります。しかし「~しちゃだめでしょ」「なんで、できないの」といった禁止語や否定語をくり返し使うことで、赤ちゃんは次第に消極的な子になってしまいます。
「~しちゃだめでしょ」と注意するのではなく、具体的に「~しようね」とポジティブな言葉で正しい行動を促してあげましょう。赤ちゃんが言われた通りにできるようになったら、「よくできたね!」「えらいね!」としっかり褒めてあげることも忘れてはいけません。
合わせて読みたい
絵本の読み聞かせも効果的

絵本の読み聞かせは、聴覚だけでなく視覚にも良い刺激を与えますので、赤ちゃんの頃からたくさん読んであげましょう。絵本をくり返し読み聞かせすることで、語彙の数も豊富になっていきます。
絵本を選ぶ際には、赤ちゃんが興味を引きやすい擬音語やオノマトペが多く使われているものを選ぶと良いでしょう。また赤ちゃんの視力はまだ弱いので、色使いがカラフルではっきりしている絵本がおすすめです。ほかにも赤ちゃんが絵本を噛んでボロボロにしたり、紙を破って誤飲したりしないように、厚紙のものや布製のものを選びましょう。
赤ちゃん言葉は避けたほうがいい?
最初から大人と同じ言葉で赤ちゃんに話しかけをした方が、後で言葉を直す必要もなく効率も良さそうに見えます。しかし最近の研究で、赤ちゃん言葉で話しかけた方が言葉を早く覚え、語彙数が多くなる傾向にあるという報告もあります。
例えば、親が「くるま」と言っても、赤ちゃんにとっては発音が難しく、上手く真似することができません。真似することができないと、赤ちゃんは話すことをつまらなく感じてしまいます。
一方で、真似しやすい「ブーブー」と赤ちゃん言葉を使えば、赤ちゃんは比較的簡単に話せるようになることがあります。さらに親が「上手く話せたね!」と褒めてあげることで、赤ちゃんは話すことを楽しく感じ、言葉をたくさん覚えようとします。赤ちゃん言葉を使うことは、赤ちゃんの言語習得意欲の向上につながりますので、たくさん使って話しかけてあげましょう。
発語能力が遅いと感じたときは

他の子どもと比べて、自分の子どもの言葉の成長が遅く感じてしまうと、親としては不安に感じてしまいます。上述したように、話し始めには個人差がありますが、遅い子でも短期間で他の子に追いついて、同じようにお喋りできるようになることも多いです。焦らずにその子のペースに合わせて、たくさん話しかけてあげましょう。
しかし一方で、病気などの要因で話し始めが遅れている可能性もありますので注意も必要です。例えば、音に対して反応しないような場合は、聴覚の異常が考えられます。子どもの様子が何かおかしいなと感じたら、早めにお住まいの市町村の保健センターや専門医まで相談しましょう。
合わせて読みたい
【まとめ】発語の個人差は大きいので焦らず成長を見守ろう
赤ちゃんは生まれたときにはすでに聴力も弱いながら備わっていますので、親の話しかけにもきちんと耳を傾けています。
赤ちゃんの反応が少ないと、話を理解できていなのではないかと感じ、話しかけ自体が無意味なものに思えてしまうかもしれません。しかしたくさん話しかけてあげることが言語機能の向上や語彙数の増加など、赤ちゃんにとって良い効果をもたらします。
赤ちゃんに話しかけるときは、赤ちゃんが言葉を楽しんで習得できるよう、絵本の読み聞かせやポジティブな言葉をかけるなど、親子でコミュニケーションを楽しむのが大切です。赤ちゃんの発語の成長を、焦らず温かく見守りましょう。
#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #発語 #いつ #時期 #対応 #対策


.jpg&w=256&q=75)
.jpg&w=256&q=75)


.jpg&w=256&q=75)

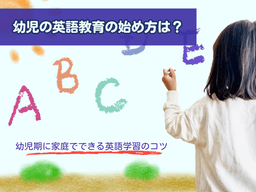
.png&w=256&q=75)