- 幼児教室のベビーパーク ホーム
- 育児がもっとたのしくなるコラム
- 3歳~6歳の育児の記事一覧
3歳~6歳の育児 の記事一覧
ベビーパークの子育てが楽しくなる3~6歳の育児コラム一覧です。 どんどん表現力豊かになっていく3~6歳児のママが知りたい事などをまとめています。
おすすめ記事

【魔の3歳児】3歳児のイヤイヤ期の特徴と反抗期の対処法
「イヤイヤ期」と聞くと、多くの方は「魔の2歳児」という言葉を想像すると思います。その名の通り、イヤイヤ期のピークは一般的には2歳ごろとされています。しかし、実際に育児をされているお母さんとお話をすると、「3歳の時が一番大変だった!」というお話を聞いたりします。実は、イヤイヤ期は早い子では1歳代の後半から始まり、長い子では4歳くらいまで続くものなのです。こちらのコラムでは、特に3歳の時期のイヤイヤ期の特徴と、その対策について説明していきます。【魔の3歳児】、お母さんにとっては大変な時期かもしれませんが、対策を知ってなるべく落ち着いて乗り切っていってくださいね。

子どもが幼稚園や保育園に行きたがらない…~「登園渋り」の理由と対処法を解説!~
忙しい朝、ごはんを作って、子どもを起こして、ごはんを食べさせて、後片付けをして、着替えや歯みがきをして、自分のお化粧をして、さあ幼稚園や保育園へ子どもを連れて行かなきゃ!という時に、急に子どもが「幼稚園行きたくないー!」とぐずって泣いて言うことを聞いてくれない…。小さい子どもを持つ親ならば、多くの方が一度は経験したことがあるシーンではないでしょうか? 頻度は子どもによって違いますが、昨日まで元気に登園していた子どもが急に幼稚園や保育園に行きたがらなくなる「登園渋り」。こちらのコラムでは、なぜ「登園渋り」が起こるのか、その理由と対処法について解説していきます。参考にしていただけますと幸いです。

3歳半でオムツが取れない原因は?発達障害との関係とトイレトレーニングの進め方
トイレトレーニングは、子どもの成長における大きな節目の一つです。子どもの成長には個人差がありますが、特にトイレトレーニングに関しては、その進み具合に親御さんが不安を感じることも少なくありません。3歳半頃になってもオムツが取れないという場合、何か原因があるのか、親はどのように対応すれば良いか、不安になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、トイレトレーニングをスムーズに進めるために、親が知っておくべき情報を詳しくご紹介します。この記事を読んで正しい知識を身につけ、親子で安心してトイレトレーニングに取り組みましょう!
.jpg&w=256&q=75)
子ども・幼児のストレス・情緒不安定に注意!ストレスサインに気付くポイントを紹介
子どものストレスは大人のストレスとは違い、言葉で表現したり自ら対処したりできないケースも多いため、そのままにしておくと心身の成長に大きな影響を与えます。そのため、周囲の大人が早い段階で気付き、適切な対処を行うことが大切です。今回は、子どものストレスサインの特徴や対処法について詳しく解説します。
.png&w=256&q=75)
3歳のひどい夜泣きはいつまで続く?原因とすぐに試せる安心の対処法
子どもが夜中に突然泣き出す「夜泣き」に、多くの親御さんが悩まされています。特に3歳を過ぎてからも夜泣きが続くと、「まだ夜泣きをするのは普通なのか」「何か病気なのではないか」と心配になるかもしれません。この記事では、夜泣きの理由と、それが起きやすい年齢、ひどい夜泣きがいつまで続くのかについて、詳しく解説します。また、夜泣きに対する具体的な対処法も紹介するので、ぜひこの記事を読んで試してみてください。
新着記事

5歳から英語を始めよう!家庭でできる学習法と習慣化のコツ
周囲の子が早くから英語を始めていると、「うちの子はもう遅いかも…」と不安になる保護者の方も少なくありません。しかし実際には、母語の基礎が整い、好奇心や表現力が豊かになり始めるこの時期は英語を始めやすいタイミングです。ここでは、5歳から始める英語学習のメリットや注意点を紹介しながら5歳から英語学習を始めるのが遅くない理由を解説します。さらに、英語を生活の一部として楽しく取り入れるための方法や習慣化のコツについて紹介しているので、ぜひご家庭で活用してみてください。

4歳からの英語は何から始める?家庭でできる英語学習方法を紹介
4歳という年齢は言葉を吸収する力がぐんと伸びるタイミングであり、英語を自然に身につける絶好のチャンスです。「英語教育を始めたいけれど、何から取り組めばいいのか分からない」「家庭で教える方法に自信がない」と感じているお母さんやお父さんもいらっしゃるかもしれません。この記事では、4歳児の発達段階に合わせた英語学習の始め方や無理なく家庭でできるリスニング・スピーキングの習得法、英語フレーズの語りかけやかけ流しのコツなどを詳しくご紹介します。英語学習が親子の「楽しい時間」となるアイデアを紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

5歳の勉強時間はどれくらい?習慣化する3つのコツと効果的な勉強方法を解説
小学校入学を控えた5歳の時期は勉強の習慣を整える大切なタイミングです。勉強時間を長くやらせればいいわけではないと分かっていても、「短すぎて効果はあるの?」「習慣はどうやって身につくの?」と思っている方も少なくありません。本記事では、5歳の子どもに適した勉強時間の目安や集中時間、習慣化のコツ、さらに楽しみながら学べる工夫を紹介します。毎日の小さな積み重ねが子どもの未来の学びの基盤を着実につくっていきます。

勉強しない5歳児にイライラしない!年長児のやる気を引き出す幼児教育
5歳の年長児になると就学に向けて勉強を始めるご家庭も多いと思います。しかし、子どもが机に座るのを嫌がったり、与えた教材に集中してくれなかったりすると、親としては「このままで大丈夫かな」と不安になり、ついイライラしてしまうこともあるでしょう。この記事では、5歳児が勉強を嫌がる理由を丁寧に紐解きながら親子のストレスやイライラを減らし、子どものやる気を自然に引き出す幼児教育の具体策を紹介します。読み終える頃には、接し方に前向きな変化を感じていただけるはずです。

5歳の勉強は何する?おすすめの勉強方法や習慣化のコツを解説
5歳になると「そろそろ勉強を始めた方がいいのかな?」と考える親御さんは多いでしょう。一方で、「まだ勉強は早いのでは?」「何を教えるべき?」と迷う声も少なくありません。5歳児は脳の発達が著しく学習への吸収力も非常に高いため、様々なことに興味をもつ時期です。そんな今だからこそ、どんな風に勉強にふれるかがとても大切です。この記事では、5歳児にとって最適な勉強内容や学習法、習慣化するための実践的なコツを紹介します。子どもが「楽しい」と感じられる工夫や、家庭で無理なく取り入れられる学習法を紹介しているので、お子さんに合った勉強方法が見つかるでしょう。

5歳児の発達目安を解説|5歳児の知能を劇的に伸ばす遊びと関わり方
5歳は小学校入学を目前に控え、心と体の成長が大きく進展する時期です。子ども自身の「自分でやってみたい」という気持ちが強くなり、自己主張が強くなり対応に戸惑うこともあるかもしれません。しかし、この時期は、集中力・記憶力・理解力・判断力といった知能の基礎が飛躍的に伸びるチャンスでもあります。この記事では、5歳児の発達の目安を詳しく解説し、日常で実践できる遊びや関わり方を通じて、知能を効果的に育てるヒントを紹介します。ぜひこの記事を読んで、より前向きな子育てに役立ててください。

5歳の記憶力を高める5つの方法|記憶力低下の原因を解説
5歳の子どもは、遊びや日常の体験を通して学んだことを少しずつ整理し、記憶として定着させる力が伸びていく時期です。「昨日のことを話してくれた」「絵本の内容を覚えていた」など、成長を実感できる場面も多くなるでしょう。一方で、生活リズムの乱れなど様々な原因によって記憶力が低下してしまうこともあります。また、規則正しい生活や親の関わり次第で、記憶力はさらに伸ばすことも可能です。この記事では、5歳児の記憶力の発達メカニズムをわかりやすく解説するとともに、記憶力を下げてしまう原因と高めるための工夫をわかりやすく紹介します。日々の育児に取り入れやすい実践的なヒントを紹介するので、お子様の成長をサポートするヒントを得ていただければと思います。
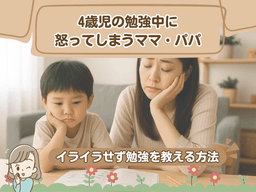
4歳児の勉強中に怒ってしまうママ・パパ|イライラせず勉強を教える方法
4歳児は身の回りのことへの好奇心が広がり、新しい言葉や知識を吸収する力も高まる時期です。だからこそ、そろそろ勉強をしてほしいと考えるママ、パパも多いと思います。一方で、親が勉強を教えようとしても、子どもはすぐにほかのことに興味を向けたり、机に向かう時間が短かったりして思うように進まないこともあります。そんなとき、親は予定通りに進まないことに気持ちが焦り、ついイライラしてしまうこともあるかもしれません。この記事では、4歳児が「勉強って楽しい」と感じやすくなるための環境づくり、怒らずに気持ちを整える方法、そして具体的な教え方のコツを解説します。今日から使えるヒントで、親子の学びの時間を心地よくしていきましょう。
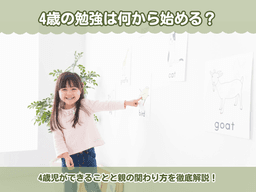
4歳の勉強は何から始める?4歳児ができることと親の関わり方を徹底解説
4歳はひらがなや数字に興味を持ち始める「学びの芽生え期」です。遊びの延長で机に向かって勉強をすることで、学習習慣や自信を少しずつ育むことができます。しかし、焦って勉強を教え込もうとすると、かえって子どものやる気を失わせてしまうこともあります。親の関わり方が、この時期の学びを大きく左右します。この記事では、4歳児の発達に合わせた勉強の始め方や取り組む順番、家庭でできる工夫、さらに親子で楽しく学ぶためのヒントをご紹介します。習い事や日常の中で学びを広げる方法も取り上げていますので、明日からの関わり方にぜひ役立ててください。

4歳児の発達目安|知能を伸ばすためにできる家庭でできる育児
4歳は知能、身体、言葉、心など、あらゆる面で急激な成長を遂げる時期である一方、個人差も大きく戸惑いや不安も増える時期です。「うちの子は順調に育っているのかな?」「子どもの知能、IQを伸ばすためになにか学ばせた方がいいの?」と疑問を抱いている親御さんも多いのではないでしょうか。この記事では、4歳児の発達目安や子どもの知能を育む具体的な遊び方などを分かりやすくご紹介します。明日からの子育てに活かせるヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。







